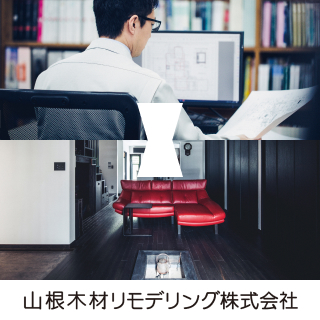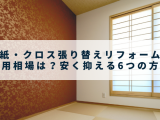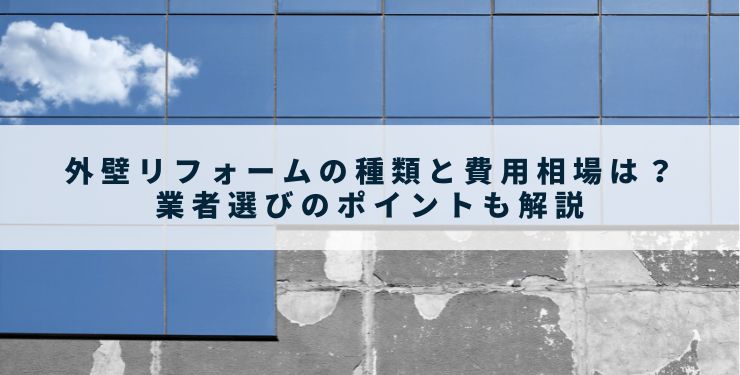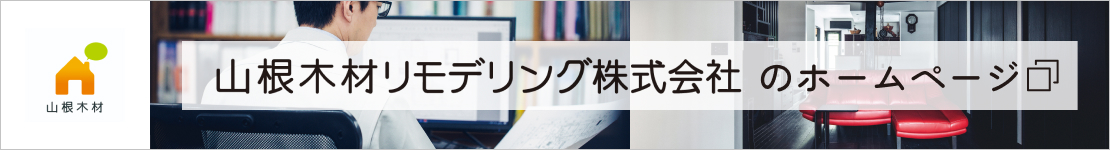毎日使うお風呂は、家の中でも特に劣化が進みやすい場所です。
築15年を過ぎると、汚れや寒さ、設備の不具合が気になり始め、「リフォームしたいけど、費用が心配…」と感じる方も多いのではないでしょうか。
実は、お風呂のリフォームでは、国や自治体が用意する補助金・助成金制度を活用できる場合があります。
これらの制度を賢く利用すれば、費用の負担を大きく軽減できるかもしれません。
この記事では、2025年の最新情報に基づき、お風呂のリフォームで使える補助金の種類から、具体的な申請手順、費用シミュレーションまで、初心者の方にも分かりやすく徹底解説します。
2025年お風呂リフォームで使える補助金は主に3種類

お風呂のリフォームで活用できる補助金は、大きく分けて「国」「お住まいの自治体」「介護保険」の3種類があります。
それぞれ目的や対象者が異なるため、ご自身の状況に合った制度を見つけることが大切です。
まずは、どのような制度があるのか全体像を掴みましょう。
国の補助金 最大148万円【暮らし省エネ支援事業など】

国が主体となって実施する大規模な補助金制度です。
主に、住宅の省エネ性能を高めるリフォームを対象としています。
2025年度は『住宅省エネ2025キャンペーン』が実施されており、お風呂リフォームでは断熱性の高いユニットバスへの交換や節水水栓の導入などが対象です。
窓や給湯器など、他の箇所のリフォームと組み合わせることで、最大148万円といった高額な補助を受けられる可能性があります。
自治体の補助金 最大20万円【お住まいの市区町村】
お住まいの都道府県や市区町村が独自に実施している、お風呂リフォームで使える補助金・助成金制度です。
国の制度とは別に、地域住民のリフォームを支援する目的で設けられています。
内容は自治体によって様々で、省エネ改修だけでなく、三世代同居やバリアフリー改修、地域産材の利用などを条件としている場合もあります。
補助額は数万円から最大20万円程度が一般的ですが、国のお風呂リフォーム補助金と併用できるケースも多いのが魅力です。
介護保険の補助金 最大18万円【バリアフリー改修】
ご家族に要介護・要支援認定を受けた方がいる場合に利用できる補助金制度です。
介護を目的とした住宅改修が対象で、お風呂リフォームでは手すりの設置や段差解消、滑りにくい床材への変更といったバリアフリー工事に適用されます。
工事費用のうち最大20万円までが支給対象となり、自己負担割合(1〜3割)に応じて最大18万円の補助が受けられます。
ご高齢の方が安全に入浴できる環境を整える際に、非常に心強い制度です。
【国の制度】お風呂リフォームで活用できる代表的な補助金
国が実施する補助金は、予算規模が大きく補助額も高額な点が特徴です。
ここでは、お風呂リフォームで中心となる2つの代表的な制度について解説しま
子育てグリーン住宅支援事業

『子育てグリーン住宅支援事業』は、2025年度の住宅省エネリフォーム支援の中心となる制度です。
住宅の省エネ性能向上を目的としており、世帯を問わず、リフォームであれば誰でも利用できるのが大きな特徴です。
お風呂リフォームでは、主に以下の省エネ設備が補助対象となります。
これらの工事を組み合わせ、合計補助額が5万円以上になる場合に申請できます。
リフォーム会社が申請手続きを行うため、制度に詳しい事業者を選ぶことが重要です。
- 高断熱浴槽の設置 32,000円/戸
- 高効率給湯器の設置 30,000円/戸
- 節湯水栓の設置 6,000円/台
- 浴室乾燥機の設置 23,000円/戸
また、これらのエコ設備の設置と同時に行うバリアフリー改修(手すりの設置や段差解消など)も補助対象に追加できます。
長期優良住宅化リフォーム推進事業
「長期優良住宅化リフォーム推進事業」は、住宅の寿命を延ばし、長く快適に住み続けられるようにするためのリフォームを支援する制度です。
省エネ改修だけでなく、耐震性の向上やインスペクション(住宅診断)の実施などが条件に含まれる、より専門的なリフォームが対象となります。
お風呂リフォームにおいては、ユニットバスへの交換やバリアフリー改修などが補助の対象です。
この制度を利用するには、リフォーム工事前にインスペクションを行い、維持保全計画を作成する必要があります。
補助額は工事費用の3分の1(上限100万円)と高額ですが、手続きが複雑なため、この制度の利用実績が豊富なリフォーム会社によく相談することが成功の鍵となります。
国の補助金の併用可否と注意点
国の補助金を複数利用したいと考える方もいるかもしれませんが、注意が必要です。
原則として、同一の工事箇所に対して、国の複数の補助金を重複して受け取ることはできません。
例えば、「高断熱浴槽の設置」という工事に対して、『暮らし省エネ支援事業』と「長期優良住宅化リフォーム推進事業」の両方から補助金をもらうことは不可能です。
ただし、リフォームする箇所が異なれば、併用できる場合があります。
例えば、お風呂の工事は『暮らし省エネ支援事業』を、窓の断熱工事は『先進的窓リノベ2025事業』を利用する、といった形です。
複雑なルールが多いため、どの制度をどのように組み合わせるのが最適か、経験豊富なリフォーム会社に相談しながら進めるのが最も確実な方法です。
お風呂リフォームで使える補助金をお住まいの市区町村で探す方法

お住まいの地域によっては、国とは別に独自の補助金・助成金制度が用意されています。
ここでは、ご自身の地域の制度を探す方法と、具体的な制度の例をご紹介します。
全国の制度を探せる検索サイトの使い方
全国の自治体が実施している多種多様なリフォーム支援制度を自分で一つひとつ調べるのは大変です。
そこで役立つのが、一般社団法人 住宅リフォーム推進協議会が運営する「地方公共団体における住宅リフォーム支援制度検索サイト」です。
このサイトを使えば、お住まいの都道府県と市区町村を選択し、支援内容(省エネ化、バリアフリー化など)を絞り込むだけで、利用可能な制度を簡単に探し出すことができます。
多くの自治体では年度ごとに予算が決められており、申請期間が限られていたり、予算上限に達すると早期に締め切られたりすることが多いため、リフォームを計画し始めたら、まずはこのサイトで情報収集を始めることをおすすめします。
広島県の助成金例「ひろしま住まいづくり支援ネットワーク」
地域に根差した工務店などが会員となっているネットワークを通じて、リフォームの支援を行うユニークな取り組みもあります。
例えば広島県では、「ひろしま住まいづくり支援ネットワーク」が県の支援を受けて、県民の住まいづくりをサポートしています。
このネットワークに登録された事業者が行うリフォームに対して、補助金が交付される場合があります。
内容は耐震改修や省エネ改修、バリアフリー改修など多岐にわたります。
市町村単位でさらに手厚い制度が用意されていることもありますので、まずはお住まいの地域のホームページで、どのような制度があるか確認してみましょう。
東京都の助成金例「既存住宅省エネ改修促進事業」
大都市圏では、独自の省エネ関連の助成金が充実している傾向があります。
例えば、東京都では「既存住宅省エネ改修促進事業(災害にも強く健康にも資する断熱・太陽光改修支援事業)」という制度があります。
これは、高断熱浴槽の設置や節湯水栓への交換といったお風呂の省エネリフォームに対して補助を行うものです。
この制度の特徴は、お風呂だけでなく、高断熱窓や高効率給湯器など、他の省エネ設備と組み合わせて申請する必要がある点です。
補助額は対象経費の3分の1以内で、上限額が設定されています。
このように、自治体の制度は国とは異なる独自の条件を設けている場合が多いため、応募する際には要綱をしっかりと確認することが大切です。
【介護保険】お風呂におけるバリアフリーリフォームの住宅改修費

ご家族の介護のためにバリアフリーのお風呂リフォームを検討している場合、介護保険制度が補助金として大きな助けとなります。
これは、高齢者や障害を持つ方が自宅で安全に暮らし続けるための支援を目的としています。
対象者と対象となる工事内容
介護保険の住宅改修費支給制度を利用できるのは、要介護認定で「要支援1・2」または「要介護1〜5」のいずれかの認定を受けている方です。
その方が実際に居住している住宅(介護保険証に記載の住所)のリフォームが対象となります。
お風呂リフォームにおける対象工事は、自立した生活を助け、介護者の負担を軽減するためのバリアフリー改修が中心です。
具体的には、転倒防止のための手すりの設置、浴室の出入り口や浴槽またぎの段差解消、滑りにくい床材への変更、開閉しやすいドア(開き戸から引き戸など)への交換といった工事が挙げられます。
支給上限額と自己負担の仕組み
介護保険を使ったお風呂リフォーム補助金の支給限度基準額は、要介護度にかかわらず、1人あたり20万円です。
これは生涯にわたる上限額ですが、転居した場合や、要介護度が著しく高くなった(3段階以上上昇)場合には、再度利用することが可能です。
実際に補助される金額は、この20万円を上限として、かかった費用のうち自己負担分を除いた額となります。
自己負担の割合は所得に応じて1割、2割、または3割と定められています。
例えば、自己負担1割の方が20万円のバリアフリー工事を行った場合、自己負担額は2万円となり、残りの18万円が介護保険から支給される仕組みです。
補助金を使ったお風呂リフォームの費用シミュレーション
補助金を使うと、実際にお風呂リフォームの自己負担額はどのくらい変わるのでしょうか。
ここでは具体的な2つのケースを想定して、費用をシミュレーションしてみましょう。
【総額100万円】ユニットバス交換の自己負担額例
古いユニットバスを新しい高機能なユニットバスに交換する、最も一般的なリフォームのケースです。
- リフォーム総費用 100万円
- 工事内容 高断熱浴槽、節湯水栓を備えたユニットバスへの交換
このリフォームで、国の『暮らし省エネ支援事業』とお住まいの自治体の補助金(仮)を併用できたとします。
- 国の補助金(高断熱浴槽+節湯水栓) 35,000円
- 自治体の補助金(省エネ改修支援) 100,000円
- 補助金合計 135,000円
【計算結果】 リフォーム費用 1,000,000円 – 補助金合計 135,000円 = 自己負担額 865,000円
補助金を活用することで、10万円以上も負担を軽減できることがわかります。
【総額150万円】断熱・バリアフリー工事の自己負担額例
冬場の寒さが厳しい在来浴室(タイル張りのお風呂)から、断熱性と安全性を高めたユニットバスへリフォームするケースです。
- リフォーム総費用 150万円
- 工事内容 高断熱浴槽、節湯水栓、浴室乾燥機の設置、手すりの設置、段差解消
このリフォームで、国の『暮らし省エネ支援事業』と「介護保険」を併用できたとします。
- 国の補助金(上記設備+バリアフリー改修) 84,000円
- 介護保険の住宅改修費(手すり・段差解消費用20万円分として) 180,000円(自己負担1割の場合)
- 補助金合計 264,000円
【計算結果】 リフォーム費用 1,500,000円 – 補助金合計 264,000円 = 自己負担額 1,236,000円
より高額なリフォームでも、目的の異なる制度を組み合わせることで、25万円以上の大きな補助を受けられる可能性があります。
お風呂リフォームで使える補助金の申請方法
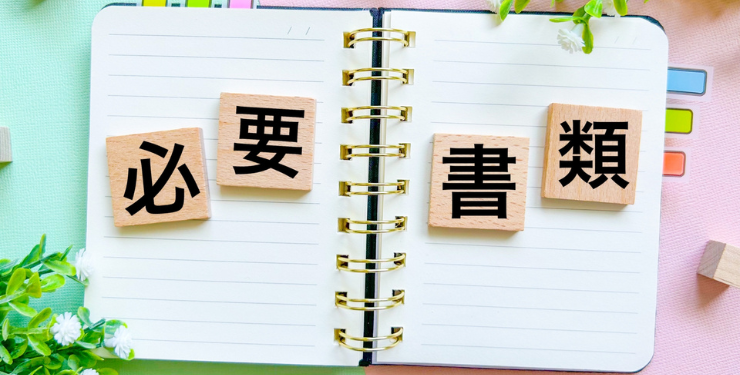
補助金の申請は複雑に思えるかもしれませんが、基本的な流れとポイントを押さえれば大丈夫です。
ほとんどの場合、リフォーム会社が手続きをサポートしてくれます。
STEP1 補助金に詳しいリフォーム会社探し
補助金活用の成否は、リフォーム会社選びで決まると言っても過言ではありません。
補助金制度は種類が多く、申請期間や条件も複雑です。
そのため、利用したい補助金制度の申請実績が豊富で、最新情報に詳しい会社を選ぶことが非常に重要です。
会社のホームページで施工事例を確認したり、最初の相談時に「補助金を利用したい」と明確に伝え、的確な提案をしてくれるかを見極めましょう。
STEP2 対象工事の見積もりと交付申請
リフォーム会社と相談し、利用する補助金と対象となる工事内容を決定したら、正式な見積もりを取ります。
その後、リフォーム会社を通じて補助金の交付申請を行います。
最も重要な注意点は、必ず「工事契約前」または「工事着工前」に申請を済ませることです。
多くの制度では、すでに始まっている工事や完了した工事は補助の対象外となってしまいます。
STEP3 工事の実施と完了報告
自治体や国から「交付決定通知」が届いたら、正式に工事請負契約を結び、リフォーム工事を開始します。
工事中は、補助金の申請内容通りに進んでいるかを確認し、工事前後の写真など、必要な記録をリフォーム会社に撮ってもらいましょう。
工事が完了したら、請求書や写真などの必要書類を揃え、リフォーム会社が期限内に事業完了の実績報告を行います。
STEP4 補助金の受領
実績報告が受理され、補助金額が確定すると、指定の口座に補助金が振り込まれます。
多くの制度では、一度リフォーム会社に補助金が支払われ、その後にお客様(施主)へ渡される流れとなります。
会社によっては、最終的な工事代金から補助金額をあらかじめ差し引いて請求してくれる場合もあります。
補助金の受け取り方法については、契約前にリフォーム会社とよく確認しておきましょう。
お風呂リフォーム補助金のよくある質問

最後に、お風呂リフォームの補助金に関して、お客様からよくいただく質問とその回答をご紹介します。
マンションや中古住宅でも補助金は使えますか?
はい、多くの場合で利用可能です。
国の『暮らし省エネ支援事業』や「介護保険」は、戸建てかマンションかといった住宅の形態を問いません。
中古住宅を購入してリフォームする場合も同様に対象となります。
ただし、自治体の制度によっては、独自の条件(耐震基準を満たしていることなど)を設けている場合があります。
また、マンションの場合は管理規約でリフォームの範囲が定められているため、事前に管理組合への確認が必要です。
トイレや洗面所のリフォームも同時に申請できますか?
はい、対象工事に含まれていれば同時に申請できます。
例えば『暮らし省エ-ネ支援事業』では、節水型トイレの設置や洗面化粧台の交換も補助対象となっています。
お風呂リフォームと合わせてこれらの工事を行い、合計補助額が規定(5万円以上)を満たせば、まとめて申請することが可能です。
複数の工事を同時に行うことで、補助金が受けやすくなるだけでなく、工事の効率も良くなるため、水まわり全体のリフォームを検討するのもおすすめです。
申請手続きは自分でやるのですか?
ほとんどの制度で、リフォーム会社が申請を代行します。
特に『暮らし省エネ支援事業』のような国の補助金制度では、あらかじめキャンペーンに登録された「登録事業者」でなければ申請ができません。
お客様自身が複雑な書類を作成することはほとんどなく、身分証明書のコピーなど、必要書類の準備にご協力いただく形になります。
介護保険の申請はケアマネジャーがサポートしてくれます。
お風呂リフォームは補助金・助成金を賢く使おう!
お風呂のリフォームは決して安い買い物ではありませんが、国や自治体の補助金を上手に活用することで、費用負担を賢く抑えることができます。
- 補助金は主に「国」「自治体」「介護保険」の3種類
- 省エネ、バリアフリー、長寿命化など、目的に合った制度を選ぶことが重要
- 申請は「工事着工前」が鉄則。補助金に詳しいリフォーム会社選びが成功の鍵
補助金制度は情報が更新されることも多いため、リフォームを計画する際は、最新の情報を確認しながら進めていきましょう。
山根木材では「永く住み継がれる家づくり」を目指し、これまでに累積1万件を超える施工を手掛けてきました。
私たちはお客様の住まいと暮らしに寄り添うライフパートナーとして、ご家族の思いに耳を傾け、ライフステージの変化も見据えた、お客様の暮らしに寄り添ったリフォームプランをご提案します。
今なら「リフォームまるわかり大辞典」を無料進呈中です。お問い合わせ・資料請求は、下記お問合せフォームからお気軽にご連絡ください。
※弊社では、広島県内を施工エリアとさせていただいています。