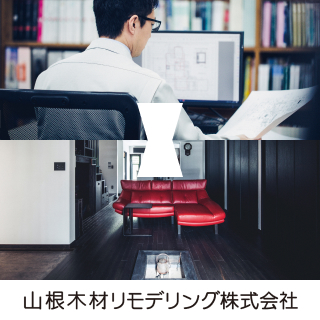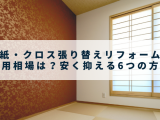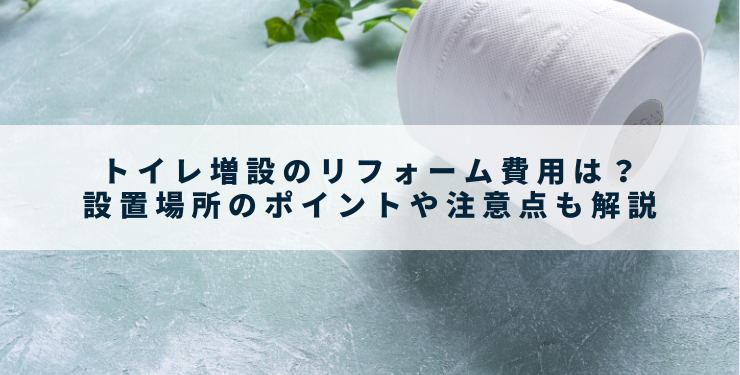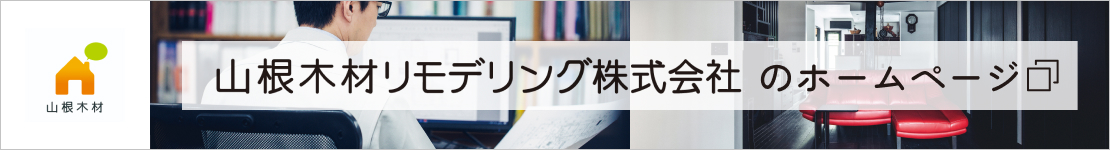大きな地震が起こるたびに、「うちの家は本当に大丈夫だろうか」と不安に感じていませんか。
特に、長年住み続けているお住まいの場合、その心配はさらに大きくなるかもしれません。
大切なご家族とご自身の命を守るためには、住宅の耐震性を高める「耐震リフォーム」が非常に重要です。
しかし、多くの方が「費用がいくらかかるか分からない」「手続きが難しそう」といった不安から、なかなか一歩を踏み出せないでいるのも事実です。
実は、耐震リフォームには国やお住まいの自治体から手厚い補助金(助成金)が用意されており、さらに税金の優遇制度も活用できます。
これらの制度を賢く利用すれば、自己負担額を大幅に抑えて、安心できる住まいを手に入れることが可能です。
この記事では、耐震リフォームの費用や補助金に関する疑問を解消し、安心して計画を進めるための情報を解説します。
耐震リフォームの補助金活用後の自己負担額は50万円〜150万円が目安

耐震リフォームを検討する上で最も気になるのが「最終的にいくら必要か」という点でしょう。
結論からお伝えすると、補助金制度を最大限に活用した場合の自己負担額は、50万円から150万円程度になるのが最も一般的な価格帯です。
もちろん、これは建物の状態や工事の規模によって変動しますが、まずはこの金額を目安として計画を立て始めることができます。
なぜこの金額になるのか、その内訳である「リフォーム費用相場」と「補助金額」を詳しく見ていきましょう。
耐震リフォーム費用の相場は120万円〜200万円
耐震リフォームの費用は、どのような工事をどれくらいの規模で行うかによって大きく変わります。
壁を数カ所補強するような部分的な工事から、基礎や屋根まで含めた家全体の工事まで様々です。
これらを組み合わせた一般的な木造住宅の耐震リフォームでは、総額で120万円〜200万円程度になるケースが最も多く見られます。
この金額には、工事前の耐震診断費用、設計費、実際の工事費、そして諸経費などが含まれます。
もちろん、建物の劣化が進んでいたり、非常に大規模な補強が必要だったりする場合には200万円を超えることもありますが、多くの場合はこの範囲内で必要な耐震性能を確保することが可能です。
まずは専門家による耐震診断を受け、ご自宅の状態に合わせた正確な見積もりを取得することが重要です。
受け取れる補助金額の目安は30万円〜100万円
耐震リフォームの費用負担を大幅に軽減してくれるのが、国や自治体の補助金制度です。
受け取れる金額は制度の内容によって異なりますが、一つの目安として30万円〜100万円程度の補助が期待できます。
特に、多くの自治体では1981年5月31日以前の「旧耐震基準」で建てられた木造住宅を対象に、手厚い支援制度を設けています。
例えば、工事費用の半分や3分の2を補助(上限額あり)といった制度が一般的です。
国の制度と自治体の制度をうまく組み合わせることで、100万円以上の補助を受けられるケースも少なくありません。
これらの補助金を活用することで、先述した費用相場から自己負担額を大きく減らすことができるのです。
【2025年最新】耐震リフォームで利用できる補助金制度

耐震リフォームの補助金は、主に「国」と「お住まいの都道府県・市区町村」の2つが実施しています。
それぞれ特徴が異なるため、両方の制度をしっかり確認し、ご自身のケースで最大限活用できるものを見つけましょう。
国の代表的な補助金制度「長期優良住宅化リフォーム推進事業」
国の制度で耐震リフォームに関連が深いのが「長期優良住宅化リフォーム推進事業」です。
これは、単に耐震性を高めるだけでなく、省エネ性能の向上やバリアフリー化など、住宅全体の性能を総合的に高め、長く安心して暮らせる「長期優良住宅」へとリフォームする場合に支援を受けられる制度です。
耐震工事は必須項目の一つとなっており、断熱リフォームやバリアフリー改修など、他の性能向上リフォームと合わせて行うことで大きな補助が期待できます。
補助額の上限は、行う工事の種類や、リフォーム後に長期優良住宅の認定を取得するかどうかによって変動しますが、最大で160万円/戸と非常に高額な支援を受けられる可能性があります。
ただし、工事前に専門家による住宅診断(インスペクション)が必須であるなど、専門的な要件が多いため、この制度の利用を検討する場合は、実績の豊富なリフォーム会社と計画段階から連携することが不可欠です。
お住まいの市区町村の補助金制度の探し方
最も身近で利用しやすいのが、お住まいの自治体が独自に行っている補助金制度です。
制度の有無や内容は自治体によって大きく異なりますが、多くの自治体で旧耐震基準の木造住宅を対象とした支援を行っています。
ご自身の地域の制度を調べる最も確実な方法は、「(お住まいの市区町村名) 耐震 補助金」とインターネットで検索することです。
自治体の公式ウェブサイトに、制度の詳細や相談窓口の情報が掲載されています。
例えば、広島市では「木造住宅耐震化促進支援事業」という手厚い補助金制度が用意されています。
昭和56年5月31日以前に着工された木造住宅で、耐震診断の結果「倒壊する可能性が高い」とされた場合、耐震リフォームにかかった費用の80%(上限100万円)という非常に手厚い補助が受けられます。
このように、自治体によっては非常に大きな支援が受けられるため、耐震リフォームを検討する際は、まずご自身の自治体の制度を必ず確認しましょう。
補助金の対象となる工事とならない工事
補助金は、どのようなリフォームにも使えるわけではありません。
原則として、補助金の対象となるのは「建物の安全性を高めるための耐震補強工事」そのものです。
具体的には、壁に筋交いを入れる、基礎を補強する、重い屋根を軽いものに葺き替えるといった工事が該当します。一方で、耐震性に直接関係のない工事は対象外となることがほとんどです。
例えば、耐力壁を増設する際に一緒に壁紙(クロス)を張り替えたり、キッチンや浴室を新しくしたりといった内装リフォームや設備交換の費用は、補助金の対象にはなりません。
また、補助金を利用するには、事前に専門家による耐震診断を受け、「耐震補強が必要」と判断されていることが大前提となります。
どの工事が補助の対象となり、どこからが対象外なのか、計画段階でリフォーム会社や自治体の担当窓口にしっかりと確認することが重要です。
耐震リフォーム費用相場(工事内容別)
耐震リフォームの総額は、複数の工事の組み合わせで決まります。
ここでは、主な工事内容ごとの費用相場を解説します。ご自宅にどの工事が必要になるかイメージしながらご覧ください。
一般的な木造住宅全体の耐震補強費用
多くの耐震リフォームでは、単一の工事で終わることは稀で、建物の弱点を補うために複数の工事を組み合わせて行います。
例えば、「壁の補強」と「基礎の補修」を同時に行う、「屋根の軽量化」と「壁の増設」をセットで実施するといったケースです。
このように、複数の工事を組み合わせた一般的な木造住宅の耐震リフォーム費用は、総額で120万円〜200万円程度が最も多い価格帯です。
この金額には、耐震診断から設計、実際の工事費までが含まれます。
もちろん、建物の規模や劣化状況、目標とする耐震性能によって費用は変動しますが、一つの大きな目安としてこの価格帯を想定しておくと、資金計画が立てやすくなります。
正確な費用は、必ず専門家による現地調査と耐震診断の上で見積もりを出してもらうようにしましょう。
壁の補強・増設の費用
地震の横揺れに抵抗するためには、建物を支える壁の強度が不可欠です。
壁の補強や増設にかかる費用は、1箇所あたり9万円〜25万円、家全体で25万円〜200万円程度が相場です。
具体的な工事内容としては、既存の壁に「筋交い(すじかい)」と呼ばれる斜めの部材を追加したり、構造用合板という強度の高い板を設置したりして「耐力壁」を増やします。
どの壁を補強するかが非常に重要で、家全体のバランスを見ながら適切な場所に配置する必要があります。
工事の際は壁を一度解体するため、内装の復旧費用も含まれます。
補強する壁の数や場所、仕上げ材の種類によって費用が変動するため、設計段階でしっかりと確認することが大切です。
基礎の補強・修繕の費用
住宅の土台である基礎部分を強化する工事も、耐震リフォームでは非常に重要です。
基礎の補強・修繕費用は、25万円〜120万円程度が目安となります。
主な工事は、基礎のひび割れ(クラック)にエポキシ樹脂などを注入して埋める補修や、鉄筋が入っていない「無筋コンクリート」の基礎の横に、新たに鉄筋コンクリートの基礎を増設する「増し打ち」という工法です。
特に古い住宅では、基礎が現在の基準を満たしていないケースが多く見られます。
家の足元をがっちりと固めることで、建物全体の安定性が大きく向上します。
床下での作業となるため、床の解体や復旧が必要になる場合もあり、工事の範囲によって費用が変動します。
屋根の軽量化の費用
建物は、頭(屋根)が重いほど地震の際に大きく揺れてしまいます。
そのため、重い屋根材を軽いものに葺き替える「屋根の軽量化」は、耐震性を向上させる上で非常に効果的な方法です。
工事費用は、80万円〜150万円程度が相場です。
特に、昔ながらの重い和瓦やセメント瓦を、軽量な金属屋根(ガルバリウム鋼板など)やスレート屋根に葺き替えるのが一般的です。
屋根が軽くなることで建物の重心が下がり、地震の揺れを大幅に軽減できます。
費用には既存の屋根材の撤去・処分費、新しい屋根材の費用、施工費などが含まれます。
屋根の面積や形状、選ぶ屋根材の種類によって費用は変わります。
耐震診断の費用
現在の住まいがどれくらい地震に強いのかを専門家が調査するのが耐震診断です。
適切なリフォーム計画を立てるための第一歩であり、補助金申請の必須条件にもなっています。
耐震診断の費用は、10万円〜40万円程度が一般的です。
診断では、図面調査と現地調査を行い、建物の基礎や壁の配置、劣化状況などを細かくチェックし、専門の計算ソフトで耐震性を数値化(評点)します。
多くの自治体では、旧耐震基準(1981年5月31日以前)の木造住宅を対象に、無料の耐震診断や診断費用の補助を行っています。
耐震リフォームを考え始めたら、まずはお住まいの自治体でこの制度が利用できないかを確認してみることを強くお勧めします。
耐震リフォームの耐震補助金を受け取るまでの4ステップ
「補助金の申請は手続きが複雑で難しそう」と感じる方も多いかもしれませんが、大まかな流れを掴んでおけば心配ありません。
多くの場合、リフォーム会社が手続きをサポートしてくれますので、安心して進めることができます。
①自治体への事前相談と耐震診断の実施
まずは、お住まいの市区町村の建築指導課など、補助金の担当窓口に相談しましょう。
ご自宅が補助金の対象になるか、どのような手続きが必要かを確認します。
その後、自治体が指定する方法で専門家に耐震診断を依頼し、建物の現状を正確に把握します。
この診断結果が、後のリフォーム計画と補助金申請の基礎となります。
自治体によっては耐震診断士を派遣してくれる場合もありますので、最初に窓口で相談することがスムーズに進めるための鍵となります。
この段階で、ご自身の希望や予算なども伝えておくと良いでしょう。
②補助金の交付申請と業者選定
耐震診断の結果をもとに、リフォーム会社と具体的な工事内容と見積もりを詰めていきます。
この時、複数の会社から見積もりを取り、提案内容や費用を比較検討することが重要です。
計画が固まったら、工事の見積書や設計図などを添えて、自治体に補助金の「交付申請書」を提出します。
この申請が受理され、自治体から「交付決定通知」が届くのを待ちます。
この通知が届く前に、絶対にリフォーム会社と工事の契約を結んだり、工事を始めたりしないでください。
「事前着工」と見なされ、補助金が受けられなくなってしまうため、最も注意すべきポイントです。
③耐震リフォーム工事の契約と着工
自治体から「交付決定通知書」が郵送などで届いたら、いよいよ正式にリフォーム会社と工事契約を結び、工事を開始できます。
工事期間中は、計画通りに施工されているかを確認するため、自治体によっては中間検査が行われたり、重要な箇所の写真撮影が求められたりする場合があります。
これらは基本的にリフォーム会社が責任を持って対応してくれますが、ご自身でも進捗状況に関心を持ち、担当者とコミュニケーションを取ることが大切です。
不明な点があれば、遠慮なく質問し、納得しながら進めていきましょう。
④完了報告と補助金の受領
工事がすべて完了したら、まずは契約に従ってリフォーム会社に工事代金を全額支払います。
その後、工事完了報告書や費用の領収書の写し、工事中の写真などをまとめて自治体に提出します。
提出された書類に基づき、自治体の担当者が現地調査などを行い、計画通りに工事が行われたかを最終確認します。
すべての審査に問題がなければ、交付が確定し、後日、指定したご自身の銀行口座に補助金が振り込まれます。
このように、補助金は工事代金を支払った後に受け取る「後払い」である点を覚えておきましょう。
耐震リフォームの補助金以外で費用を抑える3つの方法
補助金は費用負担を軽減する最も大きな要素ですが、それ以外にも自己負担額を抑える方法があります。
税金の優遇制度や業者選びの工夫を組み合わせ、賢くリフォームを実現しましょう。
複数業者から相見積もりを取る
リフォーム会社を選ぶ際は、1社に絞らず、必ず2〜3社から見積もり(相見積もり)を取得しましょう。
複数の見積もりを比較することで、工事内容ごとの費用の相場感が分かり、不当に高い金額を提示されていないか判断できます。
また、各社の提案内容の違いも明確になります。
例えば、同じ耐震性能を確保するにも、A社は壁の補強を、B社は屋根の軽量化を提案するなど、アプローチが異なる場合があります。
単に金額の安さだけで決めるのではなく、「なぜこの工事が必要なのか」「どのような材料を使うのか」といった見積もりの内訳が詳細で、説明が丁寧な会社を選ぶことが、最終的なコストパフォーマンスと満足度の高いリフォームに繋がります。
住宅ローン減税・所得税の特別控除を活用する
一定の要件を満たす耐震リフォームを行った場合、所得税が控除される制度があります。
一つは「住宅ローン減税」で、返済期間10年以上のリフォームローンを利用した場合、年末のローン残高の0.7%が最大10年間、所得税から控除されます。
もう一つはローンを利用しない場合に使える「リフォーム促進税制」で、耐震工事にかかった標準的な工事費用相当額の10%(上限25万円)が、その年の所得税から直接控除されます。
どちらの制度も、1981年5月31日以前に建築された住宅で、工事により現行の耐震基準に適合することなどが条件です。
この優遇措置を受けるには確定申告が必要になるため、工事を担当した建築士などが発行する「増改築等工事証明書」を必ず受け取り、大切に保管しておきましょう。
固定資産税の減額措置を利用する
耐震リフォームを行うと、翌年度の家屋にかかる固定資産税が減額される、非常にメリットの大きい制度です。
リフォーム完了の翌年度分の固定資産税額(120㎡相当分まで)が2分の1減額されます。
1982年1月1日以前に建築された住宅で、耐震リフォームの工事費用が50万円を超えていることなどが主な条件です。
この制度を利用するには、工事完了後、原則3ヶ月以内にお住まいの市区町村の税務課などへ申告が必要です。
所得税の控除とは別に申請が必要で、申請期限が短いため、工事が完了したらすぐに手続きできるよう、事前に必要書類などを確認し、準備しておくことが大切です。
耐震リフォーム補助金のよくある質問
最後に、耐震リフォームや補助金に関して、お客様からよく寄せられる質問とその回答をご紹介します。
中古物件の購入と同時でも補助金は利用可能か
はい、多くの場合で利用可能です。中古住宅を購入して、入居する前に耐震リフォームを行う場合でも、自治体の補助金制度の対象となるケースは少なくありません。
ただし、補助金の申請者はその住宅の所有者であることが条件のため、物件の売買契約と所有権の移転を済ませてから申請手続きを開始する必要があります。
リフォームの計画と並行して、物件の引き渡しや登記のスケジュールを不動産会社としっかり調整することが重要です。
また、金融機関によっては、中古住宅の購入費用とリフォーム費用をまとめて借り入れできるローン商品もありますので、資金計画の際に相談してみると良いでしょう。
予算がない・ローンが組めない場合の対処法
自己資金に余裕がなく、費用を捻出するのが難しい場合でも、諦める必要はありません。
まずは、多くの金融機関が提供している「リフォームローン」の活用を検討しましょう。
担保が不要なものや、比較的低い金利で借り入れできる商品もあります。
また、住宅金融支援機構が提供する【フラット35】リノベのように、中古住宅の購入と合わせて耐震リフォームを行う場合に、一定期間の金利優遇が受けられる制度も有効です。
リフォーム会社によっては、提携している金融機関のローンを紹介してくれる場合もあります。
まずは「お金がないから」と諦めずに、信頼できるリフォーム会社や金融機関の窓口で、利用できる制度がないか遠慮なく相談してみることが大切です。
申請から補助金受領までの期間はどれくらいか
申請から補助金が実際に振り込まれるまでの期間は、工事の規模や自治体の手続き状況によって異なりますが、一般的には半年から1年程度を見込んでおくと良いでしょう。
内訳としては、まず自治体への事前相談から交付決定通知が届くまでが1〜2ヶ月、その後、工事期間が1〜3ヶ月、工事完了報告から審査を経て実際に振り込まれるまでが1〜2ヶ月程度かかります。
特に、補助金の申請は年度ごとに予算が決まっているため、申請が集中する時期は審査に時間がかかる傾向があります。
計画を立てる際は、これらの期間を考慮し、余裕を持ったスケジュールを組むことが重要です。
耐震リフォームは補助金や助成金を使って上手に実施しよう!
今回は、耐震リフォームの費用相場と、負担を軽減するための補助金・税優遇制度について詳しく解説しました。
- 費用と自己負担 一般的な木造住宅の耐震リフォームは総額120万円〜200万円が目安。
補助金活用で自己負担は50万円〜150万円に。 - 補助金 国や自治体の制度を活用すれば100万円以上の補助が受けられる可能性も。
まずはお住まいの自治体の制度確認から。 - 税優遇 所得税の控除(住宅ローン減税など)や固定資産税の減額も併用可能で、さらなる負担軽減に。
- 手続き 信頼できるリフォーム会社に相談すれば、複雑な申請もスムーズに進められる。
地震への備えは、先延ばしにせず、できるだけ早く取り組むことが大切です。
補助金制度が充実している今こそ、耐震リフォームを検討する絶好の機会と言えるでしょう。
まずは第一歩として、お住まいの自治体の補助金制度を調べ、「無料の耐震診断」が利用できないか問い合わせてみてはいかがでしょうか。
この記事が、あなたの家の安全と安心を守るための助けとなれば幸いです。
山根木材では「永く住み継がれる家づくり」を目指し、これまでに累積1万件を超える施工を手掛けてきました。
私たちはお客様の住まいと暮らしに寄り添うライフパートナーとして、ご家族の思いに耳を傾け、ライフステージの変化も見据えた、お客様の暮らしに寄り添ったリフォームプランをご提案します。
今なら「リフォームまるわかり大辞典」を無料進呈中です。お問い合わせ・資料請求は、下記お問合せフォームからお気軽にご連絡ください。
※弊社では、広島県内を施工エリアとさせていただいています。