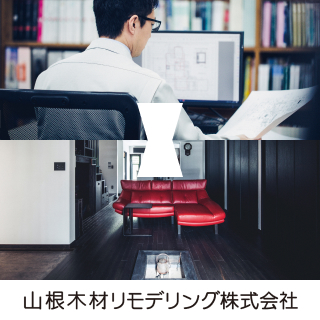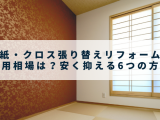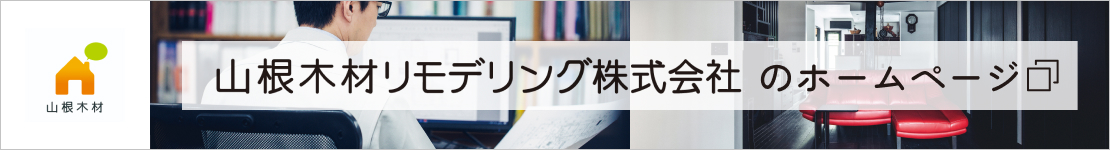地震大国の日本では、古い住宅の耐震補強は欠かせません。
特に築50年の住宅の多くは旧耐震基準で建てられており、大規模地震への備えが不十分な可能性があります。
この記事では、築50年の住宅における耐震工事の費用目安や注意点、さらに建て替えとの比較を詳しく解説します。
安全で安心な住まいづくりのヒントをお届けします。
築50年の住宅には耐震工事が必要?

住まいの耐震性が気になる場合、建築確認を受けた時期が一つの目安です。
特に築50年のお宅は旧耐震基準のことが多く、大きな地震に備えるには早めの耐震補強を検討する必要があります。
建築確認日による基準の違いと倒壊リスクは、以下の通りです。
旧耐震基準の家は要注意
築50年以上の住宅は、旧耐震基準で建てられている可能性が高く、震度6強から7クラスの大規模地震に耐える性能が備わっていないかもしれません。
1981年5月31日までの旧耐震基準は、震度5程度の地震での倒壊防止が目的でした。
一方、1981年6月1日以降の新耐震基準では震度6強から7の大地震に耐えうる設計が義務付けられ、さらに2000年6月1日以降の現行の耐震基準では木造住宅の細かな基準が義務化されています。
築50年の家は、基準の古さに加え、経年劣化も懸念されます。
木材の腐食やコンクリートのひび割れ、シロアリ被害などは住宅の強度を低下させ、耐震性を損なう要因です。
自宅と家族の安全のためにも、早めの対策を検討することが重要です。
気になる人はまず耐震診断を受けよう
地震から大切な命を守るため、住宅の耐震性能向上が推奨されています。
まずは、住まいが現在の地震にどの程度耐えられるのか、どの部分が弱いのかを把握するために耐震診断を受けましょう。
耐震診断は専門家による詳細な調査が基本ですが、手軽に始められるセルフチェック「誰でもできる我が家の耐震診断」もあります。
少しでも不安を感じたら、ぜひ活用して自宅の安全を確認してください。
築50年の住宅の耐震工事にかかる費用目安

築50年の住宅における耐震工事の費用は、住宅の状態により異なりますが、100万円から200万円が目安です。
日本木造住宅耐震補強事業者協同組合(木耐協)の調査では、旧耐震基準の住宅で実際にかかった耐震工事費として、100万~200万円が最も多い割合(36.9%)を占めています。
しかし、必要な工事内容は住宅ごとに異なるため、あくまで目安として捉え、詳細な費用は専門家による診断後に確認しましょう。
耐震工事と建て替えはどちらを選ぶべき?

築年数の古い住宅では、耐震工事か建て替えで悩む方も多いでしょう。
耐震補強工事のメリットは、費用を抑えられる、施工期間が短い、そして思い入れのある家を残せることです。
デメリットは、古い外観や設備が残る可能性があり、補強後も新たな修繕が必要になる場合がある点です。
一方、建て替えのメリットは、耐震性能だけでなく、断熱性や省エネなど最新の設備を導入でき、住宅の寿命がリセットされることです。
現行の耐震基準に完全に対応できるのも強みでしょう。
デメリットとしては、費用が高額になること、工事期間が長く仮住まいが必要になる点が挙げられます。
どちらを選ぶかは、費用、住み慣れた家への愛着、最新設備へのニーズ、そして将来的な住まいへの考え方によって異なります。
ご自身と家族にとって何が重要かどうかで検討しましょう。
耐震工事を安く抑えるには

耐震工事を安く抑えるコツは、以下の2点です。
・補助金や減税制度を利用する
・相見積もりをとる
特に補助金の情報は事前にしっかり確認しておくことが重要となります。その理由を以下で詳しく解説します。
補助金や減税制度を利用する
大地震や台風などの自然災害から住宅を守るために、多くの自治体が耐震診断や耐震工事に関する補助金制度を用意しています。
特に倒壊リスクが高い旧耐震基準の住宅は補助額が大きい傾向にあり、活用すれば費用負担を大幅に抑えられます。
また、減税制度も利用可能です。
所得税から一定額が控除される「リフォーム促進減税」や「住宅ローン減税(控除)」などがあり、これらも費用軽減に役立ちます。
ただし、これらの制度にはそれぞれ適用条件があります。
利用を検討する際は、事前に自治体のホームページなどで詳細を確認しましょう。
申請書類の準備や手続きは複雑な場合が多いため、慣れていない方は、専門知識を持つリフォーム業者などに相談しながら進めることをおすすめします。
相見積もりをとる
住宅に最適な耐震工事を予算内で実現するには、複数のリフォーム会社から見積もりを取り、比較検討することが大切です。
耐震工事は住宅の状態や構造、劣化具合によって必要な内容や規模が大きく異なるため、費用も一様ではありません。
また、会社ごとに補強のアプローチや工法が異なることもあります。
複数の見積もりを比較することで費用の相場を把握できるだけでなく、自宅に適した提案をしてくれる、住まいに適した工事を提案してくれるリフォーム会社を見極めることができるでしょう。
耐震工事の内容と費用内訳

耐震工事にかかる費用は以下の6つです。
・耐震診断:10万円~
・柱の改修:100万円~
・壁の耐震補強:5〜200万円
・基礎の補修工事(費用は内容による)
・屋根の葺き替え:70万円~
・シロアリ駆除・予防:3,800~10,000円/坪
それぞれを詳しく解説していきます。
耐震診断:10万円~
耐震診断にかかる費用は、一般診断で約10万円、精密診断で約20万円、耐震設計で約30万円が目安です。
全て行うと合計60万円前後になることもありますが、旧耐震基準の住宅の場合、多くの自治体が補助金を支給しており、要件を満たせば費用負担を軽減できます。
耐震診断では、間取り、壁の材質、筋かいの有無、屋根の重さ、劣化状況など多角的に調査し、住宅の耐震性能を詳細に評価します。
診断結果は総合評価(評点)で示され、1.5以上で「倒壊しない」、1.0〜1.5未満で「一応倒壊しない」、0.7〜1.0未満で「倒壊する可能性あり」、0.7未満で「倒壊する可能性が高い」と判断されます。
柱の改修:100万円~
築50年の住宅は旧耐震基準のため、柱の強度が低く本数も少ないことが多いです。
耐震性向上には柱の増設も有効ですが、基礎からの改修が必要で費用は100万円〜と高額になりがちです。
そのため、既存の柱に金物を取り付ける方法が多く採用されます。
これは費用を抑えつつ、工期も短縮できるメリットがあります。
また、朽ちた部分の補修も同時に行うことで、効率的に耐震性能を高められます。
壁の耐震補強:5〜200万円
築50年の住宅では、壁の量不足や配置の偏りにより、家全体の安定性が不十分なケースが少なくありません。
耐震性を高めるために多く採用されるのが、耐力壁による補強です。
具体的には、柱と柱の間に筋交いを入れたり(5〜20万円/箇所)、必要な箇所に耐力面材を追加したり(9〜15万円/箇所)します。
これにより、家の揺れへの抵抗力を向上させます。
住宅全体の補強となると150〜200万円程度かかる場合もあります。
基礎の補修工事(費用は内容による)
大地震に備える上で、土台となる基礎部分の耐震性は非常に重要です。
築50年を超える住宅では基礎がもろくなっていたり、腐食、ひび割れ、シロアリ被害を受けていることがよくあります。
このような場合、基礎の補強や補修が不可欠です。
主な工事として、基礎の増し打ち(40~60万円)、ひび割れの補修(樹脂注入1~2万円/m、シール貼り付け4,000~6,000円/m、繊維シート貼り付け2万円前後/m)などがあり、費用は内容によって異なります。
屋根の葺き替え:70万円~
築50年の住宅によく見られる重い和瓦などは、耐震上不利に働くことがあります。
地震に強い家にするためには、軽量な屋根材への葺き替えを検討するのがおすすめです。
費用相場(30坪の場合)は、スレートが70〜200万円、ガルバリウム鋼板が100〜200万円、アスファルトシングルが90〜190万円です。
屋根を軽量化することで、建物全体の重心が下がり、地震時の揺れを軽減し、倒壊リスクを減らせるでしょう。
シロアリ駆除・予防:3,800~10,000円/坪
築年数が経過した住宅では、シロアリ被害や木材の腐朽によって、建物の強度が著しく低下していることがあります。
この状態で耐震補強工事を行っても根本的な問題が解決されず、新しい木材が再び被害に遭う可能性があります。
シロアリ被害が確認された場合は、駆除と防除対策を同時に行うことが極めて重要です。
駆除・予防にかかる費用は、1坪あたり3,800〜10,000円が目安となります。
住宅耐震工事の実例
山根木材が手掛けた耐震工事の実例をご紹介します。
適切な耐震工事を行い、大切な住まいを長く安心して暮らせる場所に生まれ変わらせましょう。
築30年超の二世帯住宅を安心・快適な住まいに

二世帯住宅の2階に住んでいたI様は、1階に住んでいたご両親が他界されたことを機に、空いた空間を有効活用するため1階への生活移動を計画しました。
築30年を超え、耐震性や断熱性に不安があったため、建築士の診断に基づき、1階を中心に性能を強化するリフォームを実施。
これにより、家族が安心して快適に暮らせる住まいへと生まれ変わりました。
築150年の蔵を住まいにリフォーム

築150年の蔵を住まいへと改装したM様ご家族は、まず耐震性や断熱性といった住居性能を懸念していました。
そこで、設計士による詳細な診断を行い、快適な暮らしを実現するためのプランを策定。蔵の持つ独特の雰囲気を壊したくないという要望を尊重し、元々あった水屋箪笥や階段箪笥をリフォームして再活用。
家族共通の趣味であるカメラや小物を飾る空間としても、新たな命が吹き込まれました。
親世帯から譲り受けた家を子どもが安心して暮らせる家に

ご両親から築38年の家を引き継いだY様は、長く安心して暮らすためのリノベーションを計画。
ご主人が生まれ育った思い出深い家ですが、一番の懸念は耐震性でした。
お子様が成長する中で、安心して暮らせる拠点にするため、耐震性と断熱性を強化。
さらに、二間続きの和室を広々としたLDKに、既存のキッチンを大容量のクローゼットへと変更し、快適で機能的な住まいを実現しました。
築50年の住まいに耐震工事をする際の注意点

築50年の住宅に耐震工事を施す際、知っておきたい注意点があります。
耐震性だけでなく、より長く快適に暮らすためには、以下の点も考慮してリフォームを計画しましょう。
水回りや電気系統もリフォームが必要な可能性がある
築50年の住宅では、耐震工事と並行して水回りや電気系統の劣化にも注意が必要です。
特に給排水管の寿命は約20年とされており、未交換の場合は水漏れや詰まりのリスクが高まります。
安全で快適な暮らしのため、新しい配管への交換をおすすめします。
また、現代の生活では、築年数の古い住宅のコンセント数や容量は不足しがちです。
電化製品の増加に伴い、不便なだけでなく、無理な使用は漏電や火災のリスクにもつながります。
耐震リフォームの際にコンセントの増設や回路の見直しを行うことで、安全性と利便性を同時に高められます。
これらの設備の刷新は単なる見た目の改善だけでなく、機能面での安心にも繋がります。
断熱性や気密性が低い可能性がある
築50年の住宅は断熱性や気密性が低い場合が多く、夏は暑く冬は寒いといった室内の不快感につながります。
さらに、気密性の低さは隙間風や結露の原因となり、カビやダニの発生リスクを高める可能性もあります。
これらの問題を解決して快適な室内環境を保つためには、断熱性や気密性を向上させるリフォームが効果的です。
具体的には、窓を二重サッシにする、壁や床に断熱材を厚く敷き詰めるなどの対策がおすすめです。
予算が厳しい場合は建物の一部だけ補強することもできる
予算の都合で耐震工事を諦める必要はありません。
住宅全体の大規模な補強が難しい場合でも、建物の一部だけ耐震補強を行うことは十分に可能です。
例えば、特に倒壊リスクが高いと考えられる箇所や、生活の中心となるスペースのみを優先的に補強するといった選択肢があります。
費用と耐震効果のバランスを考慮しながら、専門家と相談し、最適なプランニングを進めることで、予算内で効果的な耐震対策を実現できるでしょう。
築50年の住宅の耐震工事にかかる費用を抑えて検討しよう
築50年の住宅における耐震工事の費用は、ご紹介した通り一様ではありません。
また、住宅の状態によって内容は大きく変動します。
まずは耐震診断を受け、ご自身の予算内で最適な工事プランを住宅会社と相談することが大切です。
山根木材では、100年以上の経験と知識を活かし、適正な費用で安全な住まいへのリフォームをご提案いたします。
耐震診断から工事まで、お客様のお悩みをトータルで解決いたします。
自宅の耐震工事を検討中の方はぜひお気軽にご相談ください。
※弊社では、広島県内を施工エリアとさせていただいています。