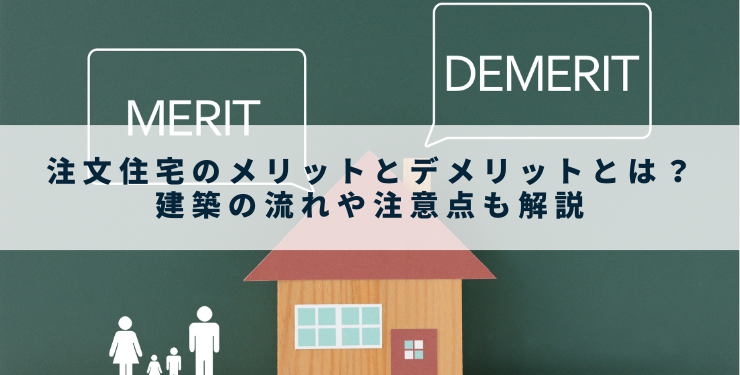憧れのマイホームを建てたいと考えていても、自己資金が少なかったり、住宅ローンを返済する余裕があまりなかったりして、できるだけ安く建てたいと考えている方も少なくないのではないでしょうか。
しかし、初めての家づくりだと「安かろう悪かろうの家にならないか」という不安や、どこにコストをかけるべきで、どのようなコストを削減できるのか知りたいというケースは多いでしょう。
この記事では、マイホームを限られた予算内で叶えたいと考えている方に向けて、「安くて良い家」を建てるための具体的な方法や、価格の仕組み、そして絶対に妥協してはいけないポイントまで、専門家の視点で徹底解説します。
家を安く建てるための具体的な方法12選

家づくりのコストダウンは、計画段階の工夫で大きく変わります。
ここでは、建築費用を抑えるための特に効果的な7つの方法を具体的に見ていきましょう。
方法1:凹凸のないシンプルな形状・間取りにする
家の形状は、建築費用に最も大きく影響する要素の一つです。
家の形を正方形や長方形といったシンプルな「箱型」(総二階)にすることが、コストダウンの基本です。
凹凸の多い複雑な形状の家は、壁の面積が増えるだけでなく、角の部分(コーナー)が増えることで材料のロスや施工の手間が増加します。
シンプルな箱型にすることで、外壁や基礎、屋根の面積を最小限に抑えられ、材料費と施工費の両方を削減できるのです。
方法2:不要な廊下をなくす
廊下のスペースを最小限にすれば、全体の床面積を節減することができてコストダウンを図れます。
居住スペースとしての機能のない廊下が増えるほど、面積効率が悪くなり、居住スペースの広さに対して建築費が割高になってしまうでしょう。
例えば、リビングダイニングから寝室や水回りに直接アクセスできる間取りにすれば、部屋間をつなぐ廊下を省略できるので、居住スペースの広さを維持しながら建築費の削減が可能です。
方法3:オープンプランを採用する
部屋を細かく仕切るほど、壁やドアを多く設置しなければならなくなり、コストが高くなる傾向にあります。
部屋の仕切りが少ない、広々とオープンな間取りにすることでこうした費用を削減可能です。
特に、LDKを一体化する設計は無駄な仕切りを減らせるだけでなく、開放感の演出にもつながります。
オープンプランを採用すると部屋ごとに用途を限定する必要がなくなるため、1つの空間を多目的に使えるようになります。
そのため、わざわざ部屋を細かく仕切らなくても快適な暮らしを送れるでしょう。
方法4:延床面積を小さくする(コンパクトな家)
当然のことながら、家の延床面積が大きくなるほど、それに比例して建築費用は高くなります。
本当に必要な広さを見極め、無駄のないコンパクトな家を設計することも、重要なコストダウンの方法です。
「家は広ければ広いほどいい」という考え方もありますが、家族構成やライフスタイルに合わせて最適なサイズにすることで、建築費用だけでなく、住み始めてからの光熱費や固定資産税、将来のメンテナンス費用も抑えることができます。
最近では、無駄なスペースを徹底的に省いた25坪程度のコンパクトな家でも、間取りの工夫次第で3~4人家族が快適に暮らすことが可能です。
方法5:水回りを1箇所にまとめる
キッチン、お風呂、洗面所、トイレといった水回りの設備は、できるだけ1箇所に集中させるのがコストダウンの鉄則です。
水回り設備には給水管や排水管、給湯管の配管工事が必要ですが、これらの設備が家のあちこちに分散していると、配管が長くなり、工事が複雑になって費用が高くなります。
例えば、1階にキッチンと洗面所・お風呂を隣接させ、2階建ての場合はその真上にトイレを配置するなど、上下階で位置をそろえることで配管のルートを最短にし、工事費を大幅に圧縮できます。
この工夫は、将来のメンテナンスのしやすさにも繋がる、非常に効果的な方法です。
方法6:平屋にするか、2階建てにするかを検討する
ある程度の広さがある土地を確保できるなら、平屋は有効な選択肢になります。
平屋は階段が不要で、2階を支えるための構造補強もいらないため、設計がシンプルになりコストを抑えやすいメリットがあります。
ただし、2階建てと同じ延床面積を確保しようとすると、平屋の方が基礎や屋根の面積が大きくなるため、かえって建築費用が高くなるケースもあります。
敷地が狭い場合や、基礎工事の面積を減らしたい場合には、2階建て(総二階)を選んだほうが建築費用を抑えられる可能性が高いでしょう。
土地の広さや形状に合わせて、適切な階数を選ぶ必要があります。
方法7:建材や住宅設備のグレードを調整する
床材や壁材、窓、そしてキッチンやお風呂といった住宅設備は、グレードによって価格が大きく異なります。
すべての仕様を最高グレードにするのではなく、「こだわりたい部分」と「コストを抑える部分」のメリハリをつけることが、賢いコストダウンの鍵です。
例えば、「キッチンは毎日使うからハイグレードなものにしたいけれど、トイレや洗面台は標準仕様で十分」といったように、家族のライフスタイルに合わせて優先順位を決めましょう。
住宅会社が標準仕様として大量に仕入れている建材や設備の中から選ぶことで、品質を保ちながら費用を抑えることができます。
方法8:多目的な収納スペースを作る
家づくりにおいて収納の確保は重要な課題です。
しかし、収納量を確保するために大型のウォークインクローゼットを設置したり、収納専用の部屋を設けたりすると、床面積が増えて建築コストが上がってしまいます。
コストを抑えながら収納力を確保するには、廊下やデッドスペースを有効活用するのがおすすめです。
階段下や天井裏、小上がりの下など、スペースが余る場所を収納に充てることで、無駄な床面積を増やさずに十分な量の収納スペースを確保できます。
生活動線上の余剰スペースに設置しておけば、多目的かつ使い勝手の良い収納スペースになるでしょう。
収納が多い家のメリット・デメリットについては、こちらをご覧ください。
方法9:将来の増築・リフォームを見越した設計にする
長く住み続けていると、家族構成やライフステージに変化が生じます。
家族の状況が変化すれば、将来的に増築したりリフォームしたりする必要が出てくるかもしれません。
変化に応じてフレキシブルに対応できる設計にすれば、長期的なコストを抑えられます。
具体的には、2階部分を増築できるような構造にしておく、リフォームで個室間の壁を取り払ったり、後から壁で仕切れるようにしたりしておく、二世帯住宅にも対応できるようにしておくなどの例が挙げられます。
可変性のある設計を心がければ、長い間安心して住み続けることができるでしょう。
増築リフォームの費用相場については、こちらをご覧ください。
方法10:外構工事はシンプルにする
いくら建物本体の建築費用を抑えられたとしても、外構工事に費用をかけ過ぎてしまっては意味がありません。
周辺環境やライフスタイルに応じて、庭や駐車スペース、塀やフェンスなどを設けることは大切ですが、デザインや素材にこだわると費用が膨らんでしまいます。
シンプルなデザインにしたり、外構の整備を後回しにしたりして、外構工事を最小限にすれば初期コストを抑えられる可能性があります。
後回しにした外構工事はDIYで行うのもよいかもしれません。
外構工事の費用相場については、こちらをご覧ください。
方法11:ローコスト住宅が得意なハウスメーカー・工務店を選ぶ
家を安く建てるためには、パートナーとなる住宅会社選びが最も重要です。
ローコスト住宅を専門にしているハウスメーカーや、地域の特性を活かした提案が得意な地元の工務店を選ぶことで、費用を抑えやすくなります。
ローコスト住宅専門のハウスメーカーは、建材の一括仕入れや設計・工法の規格化によって、安定した品質の家を効率良く建てるノウハウを持っています。
プレハブ工法や2×4(ツーバイフォー)工法など、短い工期で効率的に施工できる工法を採用することで、人件費を抑えているのが特徴です。
方法12:自分でできる部分はDIYで行う
専門知識や高い技術を必要とする箇所はプロに任せるべきですが、特別な知識や技術が不要な箇所であれば、DIYで仕上げるというのもコスト削減につながります。
建物の構造や強度にかかわる部分はリスクを伴うため、外構周りのフェンス設置や植栽、内装の壁の塗装など、万が一失敗してもやり直しの効く部分を自分たちで施工するのもよいでしょう。
費用削減だけでなく、自分たちの手で作り上げたマイホームへの愛着を深める効果も期待できます。
「500万円の家」は本当に建てられる?価格の仕組みと注意点

インターネットなどで見かける「500万円の家」という広告は非常に魅力的ですが、その価格だけで住める家が完成するわけではありません。
後悔しないために、価格の仕組みと、その裏に隠れた注意点を正しく理解しましょう。
広告価格は「本体工事費」のみ。総額との違いを理解する
注文住宅を建てる際の費用は、大きく「本体工事費」「付帯工事費」「諸費用」の3つに分けられます。
広告に表示されている「500万円」といった価格のほとんどは、このうちの「本体工事費」のみを指しています。
| 費用 | 内容 |
| 本体工事費 | ・建物そのものの建築にかかる費用(構造、内外装、設備など)。 ・家づくりの総費用の約70~80%。 |
| 付帯工事費 | ・外構、地盤改良、インフラ整備(給排水・ガス)などにかかる費用。 ・総費用の約15~20%。 |
| 諸費用 | ・設計料、登記費用、住宅ローン手数料、税金など。 ・総費用の約5~10%。 |
つまり、「本体工事費500万円」の家を建てるための総額は、実際には付帯工事費と諸費用が加わり、800万円~1000万円程度になるのが一般的です。
「500万円で家が建つ」のではなく、「500万円の家に住むためには、総額で800万円以上が必要」と理解しておくことが大切です。
土地の状態が付帯工事費に大きく影響する
土地の選び方も、最終的な建築コストに大きく影響します。
特に注意が必要なのが、付帯工事費に含まれる「地盤改良費」と「インフラ整備費」です。
土地の状態が悪い(軟弱地盤である)場合、家を安全に建てるために地盤改良工事が必要となり、数十万~百万円以上の追加費用がかかることがあります。
また、ガスや水道、電気などのインフラが敷地に引き込まれていない土地を選ぶと、その引き込み工事にも多額の費用がかかります。
土地を探す際は、これらの付帯工事費を抑えられる、地盤の良い造成済みの土地を選ぶのがおすすめです。
安くても「良い家」にするために削ってはいけない費用3選

コストダウンを追求するあまり、家の基本的な性能を犠牲にしては本末転倒です。
「安かろう悪かろう」の家を建てて後悔しないために、絶対に削ってはいけない重要な費用を3つ解説します。
家の強度に関わる構造・基礎費用
建物の骨格となる構造(柱や梁など)と、家全体を支える基礎は、家族の安全を守る上で最も重要な部分です。
この部分の費用を削ると、耐震性が著しく低下し、地震などの災害時に命を危険に晒すことになります。
建築基準法で定められた最低限の基準はありますが、長く安心して暮らすためには、基準以上の強度を確保することが望ましいです。
特に地盤が弱い土地の場合は、地盤改良工事の費用を絶対に削ってはいけません。
完成後は見えなくなる部分だからこそ、しっかりとお金をかけるべき最優先ポイントです。
快適性と健康に関わる断熱・換気費用
夏の暑さや冬の寒さを直接左右するのが、壁や窓の断熱性能です。
断熱材のグレードを下げたり、性能の低い窓を採用したりして初期費用を抑えると、冷暖房効率が悪くなり、月々の光熱費が高くなってしまいます。
結果として、長期的なランニングコストで損をすることになりかねません。
また、不十分な断熱や換気は結露を招き、カビやダニの発生原因となります。
シックハウス症候群やアレルギーといった健康被害を防ぐためにも、断熱性能と計画的な換気システムの導入費用は、快適で健康な暮らしのための必要不可欠な投資と考えましょう。
家の寿命に関わる防水工事費用
屋根や外壁、ベランダなどから雨水が浸入するのを防ぐ防水工事も、絶対に妥協してはいけないポイントです。
防水処理が不十分だと、雨漏りの原因となります。
一度雨漏りが発生すると、修理費用が高額になるだけでなく、建物の構造体を腐らせ、シロアリを呼び寄せるなど、家の寿命を著しく縮めてしまいます。
目先のコストダウンのために防水工事のグレードを下げると、数年後に何倍もの修繕費用がかかるリスクを背負うことになります。
家の資産価値を長く維持するためにも、防水工事にはしっかりと費用をかけるべきです。
【住宅タイプ別】建物の建築費用を安く抑えるポイント

注文住宅や建売住宅など、取得する住宅のタイプによってコストダウンのポイントが異なります。
ここでは、5つの住宅タイプ別に建築費用を安く抑えるポイントを紹介します。
なお、設計をシンプルにする、できるだけ住宅会社の標準仕様を活用する、工法を工夫する、設備のグレードを適度なレベルに抑えるなどは、どの住宅タイプにも共通して有効なコストダウンの方法といえるでしょう。
注文住宅
注文住宅は、間取りやデザインを自由に選べるのが魅力ですが、自由度が高い分だけ厳密なコスト管理が求められます。
こだわりを取り入れつつ、無駄な要素を排除することで費用を抑えられるでしょう。
注文住宅で費用を抑えるには、シンプルな間取りにするのが有効です。
複雑な間取りやデザインはコスト増につながります。
長方形や正方形のシンプルな形状で無駄のない間取りにすれば、材料費や施工費を削減できます。
仕様や設備もこだわればこだわるほどコストがかかるもの。
住宅会社の標準仕様や標準設備を選択すれば、カスタマイズにかかる追加費用を抑えることができます。
キッチンやバスルームなどはグレードによる価格差が大きいため、標準的な仕様のものを選ぶだけでも大きな節約効果が期待できます。
先ほど紹介したように、プレハブ工法や2×4工法といった効率的な工法を採用し、施工を効率化するのも効果的です。
なお、施工会社によっては打ち合わせ回数に上限や期限を設けている場合もあります。
打ち合わせ回数をなるべく減らすことで、コストダウンにつながるかもしれません。
注文住宅の費用相場については、こちらをご覧ください。
建売住宅
建売住宅は注文住宅に比べて自由度が低い反面、完成済み(あるいはプラン決定済み)の家を購入するため、取得にかかるコストが明確です。
購入後、すぐに住み始められるというのも建売住宅ならではの魅力といえます。
取得費用を抑えるためのポイントは大きく2つです。
1つ目は完成物件を選ぶこと。
建売住宅は完成から時間がたつと値下げされる傾向にあります。
長期間売れ残っている物件など、掘り出し物が見つかる可能性もあります。
2つ目のポイントは、複数の物件を比較検討することです。
建売住宅は、地域や販売業者、販売のタイミングなどによって価格が変わります。
複数の物件を比較することでコストダウンできる可能性があるでしょう。
建売住宅の賢い選び方については、こちらをご覧ください。
規格住宅(企画住宅)
規格住宅(企画住宅)とは、注文住宅と建売住宅の中間的な性格を持った住宅のことです。
住宅会社によってあらかじめ決められた設計やプランの中から、好きなものを選んで建てるため、建売住宅に比べると自由度は高めです。
注文住宅ほどの自由度はないものの、建材や施工を効率化できるので、比較的安価に建てられます。
規格住宅でも、標準仕様から外れた設計や設備を採用するとコストが上がります。
費用を少しでも抑えたいなら、できるだけ既存プランを活用しましょう。
加えて、不要なオプションをつけないことも無駄な費用の削減につながります。
ローコスト住宅
建築費を抑えることを重視した住宅を「ローコスト住宅」と呼びます。
もともと低価格で提供されるものですが、設計や施工方法に問題がないかは事前にチェックが必要です。
費用を抑えやすいローコスト住宅で、さらにコストを節約するには、建材や設備をローコストなものにするのが有効です。
高級な建材やハイスペックな設備を選ばず、機能的でコストパフォーマンスの良いものを選べば、費用を低くできます。
また、建築費用は坪単価で計算されます。
そのため、余分な部屋やスペースを削減して必要最低限の面積に収めることも、トータルコストの削減につながるでしょう。
ローコスト住宅では、構造がシンプルな平屋にすることで基礎工事にかかる費用を削減できる可能性があります。
間取りを効率化できるなら、平屋のマイホームを検討するのもおすすめです。
二世帯住宅
2つの家族が一緒に住める二世帯住宅は、通常の住宅に比べて面積が大きく、コストが高くなりがちです。
しかし、二世帯住宅もプランニング次第でコストを抑えることはできます。
二世帯住宅の費用が高くなる大きな要因として、2世帯分の水回りやLDKを用意しなくてはならない点が挙げられます。
トイレや浴室、キッチンなどを共用スペースにすることで、設備費や施工費を大きく削減できるでしょう。
水回りを2つ設置する場合でも、上下階で同じ位置に配置して配管工事を減らすなど、構造をシンプルにすれば費用を削減できる可能性があります。
二世帯住宅を建てるには広い土地が必要なため、土地代が高くなりやすいのもネックです。
ただ、土地代を2つの世帯で分担すれば費用を抑えられます。
そうすれば土地にかける予算を高くできるので、地価が高いエリアでも少ない負担でマイホームを実現できるかもしれません。
完全分離型の二世帯住宅のメリット・デメリットについては、こちらをご覧ください。
家を安く建てるためのハウスメーカーや工務店の選び方

家づくりのコストを安く抑えつつ、満足度の高い住まいを実現するには、次のポイントを押さえて信頼できる住宅会社を選びましょう。
ハウスメーカーと工務店の違いを理解する
大手ハウスメーカーと地元密着型の工務店では強みや弱みが異なります。
大手ハウスメーカーは設計や施工が標準化されており、設備や建材の大量生産・調達が可能なため、安定的な品質で効率良く家づくりが可能です。
一方、広告費などが価格に反映されやすいという弱みがあります。
対する工務店は、対応の柔軟性や地域の特性を理解した提案を受けられるのが魅力。
ハウスメーカーに比べて安価に家を建てられることもありますが、小規模な工務店は会社によって技術力や施工品質に差があるので慎重に選びましょう。
ハウスメーカーと工務店の詳しい違いについては、こちらをご覧ください。
ローコスト住宅を専門にしている業者を探す
ローコスト住宅を専門にするハウスメーカーを選ぶというのも、費用を抑えるのに有効な方法です。
こうした業者は、規格化された設計や工法を用いて、ローコストに特化したプランを提供しています。
また、工務店でも地元の資材業者と提携して材料費を抑えるなど、コストダウンに強いところもあります。
ただし、ローコストな反面、設計の自由度が低かったり、耐久性や断熱性などの住宅性能が低かったりするケースも。
長期的には、むしろコストが高くなる可能性もあるので十分注意しましょう。
見積もりを複数から取る
業者によって見積もり額に差が出るケースも多いため、必ず複数のハウスメーカーや工務店に見積もりを依頼し、価格と内容を比較検討することが大切です。
見積もりには細かな項目があるので、項目ごとの内訳を確認し、どの項目に費用が多くかかるのかを把握しましょう。
工務店の場合、価格交渉にも柔軟に対応してくれることがあるため、見積もり取得後にあらためて相談するのがおすすめです。
保証内容を確認する
これから長い期間住み続けるマイホームなので、新築時の保証内容やアフターサポートの内容も十分に確認しましょう。
価格の安い業者を選んでも、保証が不十分だとメンテナンス費用がかさんでしまう恐れがあります。
定期的な点検やメンテナンスを無料保証している業者もあるので、初期コストの削減だけでなく、将来の経済性も考慮して業者を選ぶようにしましょう。
業者の評判や実績を確認する
業者選びの際は、インターネットで口コミを検索したり、知人に良い業者を紹介してもらったりして、品質や信頼性に定評のあるところを選ぶようにしましょう。
併せて、施工実績や過去に手がけた住宅の事例を確認しておくことも大切。
できれば、その業者が実際に建てた住宅を見学しておくと安心です。
家を安く建てるために活用したい税制や補助金制度

家づくりにかかる費用を抑えるには、国や自治体による税制や補助金制度を積極的に活用したいところです。
ここでは、住宅新築時に使える代表的な税制や補助金制度を紹介します。
住宅ローン控除(住宅ローン減税)
住宅ローン控除は、返済期間10年以上の住宅ローンを使って一定の条件を満たす住宅を新築する場合、13年間にわたって所得税や住民税が控除される制度です。
具体的には、年末の住宅ローン残高×0.7%が所得税から控除され、控除しきれなかった分が翌年の住民税から控除されます。
当制度によりローン返済期間中の納税額が大きく軽減されるため、実質的にマイホーム取得の費用負担を軽減できるのがメリットです。
ZEH(ゼロエネルギーハウス)補助金
ZEH(ゼッチ)とは、断熱性能を高めたり高機能な省エネ設備を導入したりすることで、年間のエネルギー収支を実質ゼロにする住宅をいいます。
環境に優しいZEHは、普及を推進する目的で手厚い補助金制度が設けられています。
「戸建ZEH」補助金であれば、1戸あたり55万円の定額補助に加え、特定の設備やシステム導入にも追加の補助メニューが適用されるので、大きな費用削減が可能です。
また、電気代やガス代の削減により、ランニングコストの抑制につながる点も見逃せません。
ZEH住宅を建てる時に活用できる補助金については、こちらをご覧ください。
長期優良住宅認定制度
長期優良住宅に認定されると、先ほどの住宅ローン控除をはじめ、税制の優遇措置が数多く適用されます。
長期優良住宅とは、優れた耐久性や省エネ性能を有していて、長期にわたって良好な状態で住み続けられると認められた住宅のこと。
言い換えれば、長く住めるとお墨付きをもらった住宅であるため、資産価値の向上や維持も期待できます。
将来住み替える必要が生じたときでも、高値で売却しやすくなるでしょう。
固定資産税の減額制度
戸建て住宅を新築する場合、一定の条件のもとで、固定資産税が3年間にわたって半分に減額されます。
長期優良住宅に認定されれば、減額の期間が5年間に延長されるのもポイントです。
毎年納めなければならない固定資産税が当初3年間、あるいは5年間減額されるので、新居で暮らし始めてからの負担を軽減できるでしょう。
新築住宅の固定資産税の計算方法や減税措置については、こちらをご覧ください。
地方自治体による補助金や助成金
地方自治体によっては、国の制度とは別に、独自の住宅購入や新築支援を目的とした補助金制度を設けているケースがあります。
場合によっては、国の制度よりも手厚い支援が受けられることもあるでしょう。
また、国費で運用されている制度でなければ、国の補助金制度と併用できるというメリットもあります。
地方自治体のWebサイトや役所の窓口などで確認するとよいでしょう。
家を安く建てる際の注意点

家は長く住み続けるものなので、安く建てることばかりを意識するのはよくありません。
以下のポイントを踏まえ、予算とニーズのバランスが合った家づくりを進めるのが大切です。
長期的なランニングコストも考慮する
たとえ初期費用を抑えたとしても、住宅性能や設備グレードを下げるとメンテナンスコストが高くつく可能性があります。
さらに低価格を売りにする業者の場合、アフターサポートが十分でない場合があり、結果として点検や修繕にかかる費用が高くなることもあるでしょう。
家づくりでは、当初の建築費用だけでなく、将来的なランニングコストにも配慮する必要があります。
坪単価だけ「安い、高い」を判断しない
建築費用は「坪単価」で表現されるケースが多いものの、ここには建物の「本体価格」しか含まれていないケースが大半です。
先述の3種類の費用のうち、付帯工事費や諸費用は含まれていません。
また、坪単価は使用する建材や設備のグレードによっても大きく変わる可能性があります。
坪単価が低く見えても追加費用がかかり、最終的には高コストになる恐れもあるので注意しましょう。
ハウスメーカーの選び方に注意する
ローコスト住宅を提供するハウスメーカーを選ぶ際は、価格だけなく、十分な品質やサービスを提供しているかどうかも重要な判断基準です。
安価だからといって、設計の自由度が低かったり、収納スペースが十分にできなかったりして「安かろう悪かろう」では、理想の住まいを実現するのは難しいでしょう。
満足度の高い住まいにするためにも、家族の希望やライフスタイルに沿った設計ができるハウスメーカーを選ぶことが大切です。
家を安く建てるためには計画段階でのコスト管理と優先順位の明確化がポイント!
家を安く建てるためには、希望条件の優先順位を明確化することと、計画段階でしっかりとコスト管理することが大切です。
優先順位の低い部分はコストカットし、本当に必要な部分にお金をかければ、予算内でも満足度の高い家づくりを実現できるでしょう。
また、信頼できる業者を選定し、補助金制度を活用するというのも、費用を抑えた家づくりを成功させるためのポイントです。
家づくりにおいて初期コストを抑えることはもちろん大切ですが、長く住み続けることを考えると、長期的な目線で経済性を考える必要があります。
山根木材ホームは「永く住み継がれる家づくり」を目指し、長期優良住宅を標準仕様としています。
住宅ローン減税、各種税金の軽減など、初期費用を抑えることができるだけでなく、将来的なメンテナンスコストの軽減にもつながるのが魅力です。
加えて、基礎・柱・梁・屋根などの構造躯体、防水に関しては30年の初期保証で対応。耐久性の高さとアフターメンテナンスの充実により、100年後も価値の残る住まいを実現します。
広島・東広島・福山エリアで、長期的なコストパフォーマンスを重視した家づくりをするなら、実績豊富な山根木材ホームにぜひお任せください。
お問い合わせ・資料請求は、下記お問い合わせフォームからお気軽にご連絡ください。