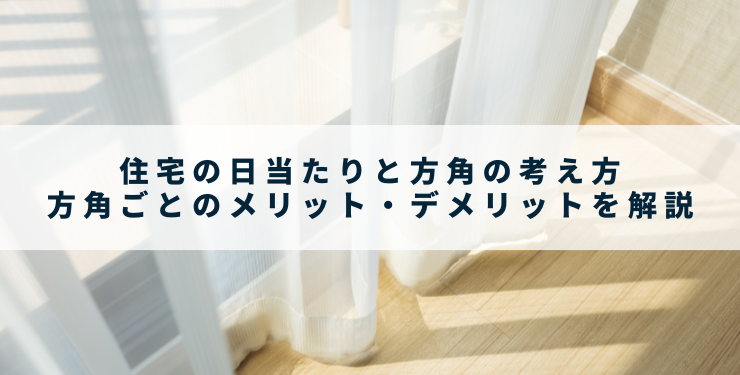新築の家づくりでは、間取りや内装、キッチン設備など建物の内部に意識が向きがちです。
しかし、理想のマイホームを実現するには、建物の外、つまり「外構(がいこう)」の計画が同じように重要になります。
素敵な外構は住まい全体のデザイン性を高め、日々の暮らしやすさや安全性、防犯性にも直結する大切な部分です。
この記事では、外構工事の基礎知識から、新築で失敗しないための計画の進め方、費用の考え方までを詳しく解説します。
外構工事とは?

外構工事とは、一言でいえば「住宅の敷地内にある、建物以外の工事全般」を指します。
具体的には、毎日通る門や玄関アプローチ、駐車場、お庭の植栽、お隣との境界にあるフェンスなどが含まれます。
外構計画を後回しにすると、「駐車場が狭い」「玄関が道路から丸見え」「雨が降ると水浸しになる」といった後悔につながりかねません。
外構は、住まいの第一印象を決める「顔」の役割を果たすと同時に、日々の暮らしやすさや安全性、防犯性にも直結する非常に大切な部分です。
例えば、しっかり計画されたアプローチや駐車場は、雨の日の移動や荷物の出し入れを快適にしてくれます。
また、防犯性を高めるための照明や、小さなお子様の飛び出しを防ぐ門扉の設置など、家族の安全を守る上でも不可欠な要素です。
外構工事は、ただ単に敷地を区切るだけでなく、生活の質を向上させ、住まいの価値を高めるための大切なステップです。
建物のデザインと調和させ、機能的かつ美しい空間を作り上げることで、より満足度の高いマイホームが実現します。
外構とエクステリアの具体的な違い

家づくりの打ち合わせや情報収集をしていると、「外構」と「エクステリア」という2つの言葉を耳にすることがあります。
この2つはしばしば同じような意味で使われますが、実は少しだけニュアンスが異なります。
この違いを知っておくと、業者との打ち合わせなどがスムーズに進みます。
外構は、門や塀、フェンス、駐車場のコンクリートといった「構造物」そのものや、それらを作る「工事」を指すことが多く、どちらかというと機能的な側面が強い言葉です。
敷地と道路を分ける、車を停める場所を確保するといった、実用的な役割を持つ設備や工事と捉えると分かりやすいでしょう。
一方で、エクステリアは、そうした構造物だけでなく、庭の植栽や芝生、ウッドデッキ、照明、デザイン性の高い水栓などを含めた「空間全体のデザインや雰囲気」といった、より広い意味合いで使われる傾向があります。
例えるなら、外構が「家の外にある設備や構造物」で、エクステリアが「家の外の空間デザイン全体」というイメージです。
近年では、暮らしを豊かにするために庭のデザイン性や空間としての活用を重視する傾向が強まっているため、「エクステリア」という言葉が使われる場面が増えています。
ただし、工事業者との打ち合わせなど実務的な場面では、今でも「外構工事」という言葉が一般的に使われますので、まずは「外構は機能的な工事、エクステリアはデザインを含めた空間全体」と覚えておきましょう。
外構工事の範囲と代表的な6つの工事種類
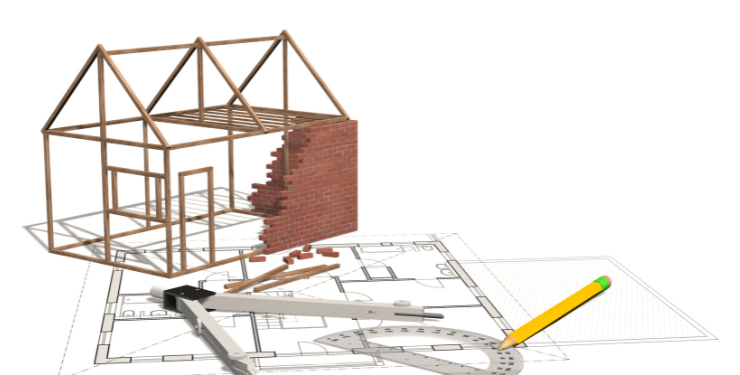
外構工事と一言でいっても、その範囲は非常に広く、様々な種類があります。
ここでは、代表的な外構工事の種類と、それぞれにかかる費用の目安をご紹介します。
自分たちの理想の暮らしには、どの工事が必要になるかイメージしながら見ていきましょう。
門まわり(門扉・門柱・表札・ポスト)
門まわりは、住まいの「顔」とも呼ばれる最も象徴的な場所です。
訪問者が最初に目にする部分であり、そのデザイン次第で家全体の印象が大きく変わります。
門まわりを構成する主な要素は、道路と敷地の境界に設ける門扉(もんぴ)、表札やインターホンを取り付ける門柱(もんちゅう)、そして郵便物を受け取るポストです。
最近では、開放的な空間を演出するために門扉を設けない「オープン外構」も人気ですが、小さなお子様の飛び出し防止や、防犯性、プライバシーを重視する場合は、しっかりと門扉を設置することをおすすめします。
素材やデザインも豊富で、軽やかで錆びにくいアルミ製、温かみのある木目調、重厚感のあるアイアン調など、住宅の雰囲気に合わせて選ぶことができます。
| 門の素材 | タイプ | 費用相場 |
| アルミ材 | 片開き | 8万円程度 |
| アルミ材 | 両開き | 12万円程度 |
| ステンレス材 | 片開き | 17万円程度 |
| ステンレス材 | 両開き | 27万円程度 |
アプローチ
アプローチとは、門から玄関までをつなぐ通路のことです。
毎日家族が通り、お客様を迎える大切な動線となります。
デザイン性はもちろんですが、歩きやすさと安全性への配慮が欠かせません。
素材には、高級感のある天然石やタイル、温かみのあるレンガ、コストを抑えられるコンクリートや砂利、デザイン性の高いインターロッキングブロックなどが使われます。
雨の日でも滑りにくく、水はけの良い素材を選ぶことが大切です。
また、夜間の安全のために足元を照らす照明を設置したり、将来のために車椅子でも通りやすいようにスロープを設けたりすることも検討しましょう。
施工面積によって費用は変わりますが、一般的には10万円〜30万円程度が相場です。
フェンス・塀
フェンスや塀は、隣地や道路との境界を明確にし、プライバシーの確保や防犯性を高めるという重要な役割を担っています。
また、住まいの外観デザインを構成する要素としても存在感を発揮します。
素材は、見通しが良くコストも手頃なスチールメッシュフェンス、デザインが豊富で耐久性も高いアルミ形材フェンス、木のような質感が美しい木目調の樹脂フェンス、自然な風合いで人気のウッドフェンス(天然木)などがあります。
どこからの視線を遮りたいのか、風通しや日当たりをどうしたいのかによって、設置する高さや、すき間のない「目隠しタイプ」か、すき間のある「ルーバータイプ」かなどを選び分けることがポイントです。
| フェンスの種類 | 費用相場(1メートルあたり) |
| スチールメッシュフェンス | 5,000円〜10,000円 |
| アルミ素材フェンス | 10,000円〜60,000円 |
| 木目調フェンス | 10,000円〜30,000円 |
| ウッドフェンス | 30,000円〜40,000円 |
駐車場・カーポート
駐車場(カースペース)は、大切な愛車を保管するためのスペースです。
地面の仕上げ方には、コストを抑えられる砂利敷き、丈夫で手入れが楽なコンクリート舗装、水はけが良くデザイン性も高いインターロッキングなどがあります。
所有する車の台数や車種、将来の買い替えの可能性も考慮して、十分な広さを確保することが重要です。
さらに、雨や紫外線、鳥のフンなどから車を守るためにカーポートを設置するのも一般的です。
1台用であれば16万円〜70万円程度で設置可能で、積雪や強風に強いタイプ、デザイン性の高いタイプなど、様々な製品があります。駐車場の計画では、道路への出入りのしやすさや、玄関までの動線も考慮すると、日々の使い勝手が格段に向上します。
庭・植栽(ウッドデッキ・テラス)
庭は、家族の憩いの場や趣味を楽しむ空間として、暮らしに彩りを与えてくれます。
芝生を敷いて子どもが走り回れるスペースにしたり、家庭菜園やガーデニングを楽しんだり、その可能性は無限大です。
リビングから直接出られるウッドデッキや、タイル敷きのテラスを設ければ、屋外のリビングとしてバーベキューを楽しんだり、カフェタイムを過ごしたりと、活用の幅がさらに広がります。
シンボルツリーとなる木を1本植えるだけでも、住まいの外観はぐっと豊かになります。
庭の工事は、砂利や芝生を敷く程度であれば50万円未満で可能ですが、ウッドデッキの設置や広範囲のタイル敷きなど、内容によっては100万円以上になることもあります。
| 外構工事の内容 | 費用相場 |
| テラスの設置 | 15万円〜25万円程度 |
| 屋根付きのテラスの設置 | 20万円〜35万円程度 |
| サンルームの設置 | 50万円〜80万円程度 |
その他設備(照明・物置・立水栓)
上記の主要な工事以外にも、外構には暮らしを便利で豊かにする様々な設備があります。
照明は、夜間の安全確保や防犯対策に役立つだけでなく、ライトアップによって幻想的な雰囲気を演出することもできます。玄関まわりや駐車場、アプローチに設置するのが一般的です。
また、タイヤやアウトドア用品、園芸用品などを収納するための物置も非常に便利です。
サイズやデザインも様々で、本体価格は3万円〜40万円程度が目安です。
さらに、庭での水やりや洗車、バーベキューの後片付けなどに重宝するのが立水栓(りっすいせん)です。
デザイン性の高いおしゃれな製品も多く、庭のアクセントにもなります。
これらの設備を適切に配置することで、外構の機能性と快適性は大きく向上します。
【計画の前に】失敗しないために押さえるべき3つのポイント
具体的な計画を始める前に、まずは理想の外構づくりで失敗しないために押さえておくべき3つの重要なポイントをご紹介します。
「デザイン」「実用性」「安全性」の観点から、家族で何を大切にしたいのか、あらかじめ話し合っておくことが後悔しないための第一歩です。
外構工事を失敗しないためのコツ
理想の外構づくりを成功させるためには、漠然としたイメージだけでなく、いくつかの重要なポイントを押さえておく必要があります。
ここでは、「デザイン性」「実用性」「安全性」という3つの観点から、計画段階で必ず検討すべきポイントをご紹介します。
家族で話し合いながら、後悔のない外構を実現しましょう。
1. 優先順位を決めてメリハリをつける
外構工事は、こだわればこだわるほど費用がかかります。
限られた予算の中で理想を形にするためには、「どこにお金をかけたいか(重点ポイント)」と「どこでコストを抑えるか(節約ポイント)」を明確にすることが重要です。
例えば、「お客様を迎える玄関アプローチのタイルは高級感のあるものにしたいけど、普段あまり使わない庭の奥は砂利敷きでコストを抑えよう」といったように、家族が譲れないポイントに予算を集中させましょう。
すべての希望を一度に叶えようとせず、優先順位をつけて計画にメリハリをつけることが、満足度の高い外構づくりのコツです。
2. 使い勝手や手入れのしやすさを考える
おしゃれなデザインに惹かれて採用したものの、実際に暮らしてみると「手入れが大変…」となっては本末転倒です。
外構は常に雨風や砂埃に晒されるため、日々のメンテナンス性は非常に重要です。
例えば、天然木のウッドデッキは定期的な塗装が必要ですが、樹脂製の人工木デッキならメンテナンスはほとんど不要です。
また、美しい天然芝の庭は憧れますが、芝刈りや雑草取りといった手入れが継続的にできるか、ライフスタイルと照らし合わせて考える必要があります。
デザイン性だけでなく、長期的な視点で使い勝手や手入れのしやすさを考慮して素材や設備を選びましょう。
3. 防犯面やプライバシー確保を意識する
外構は、家族の安全とプライバシーを守るための「第一の砦」でもあります。
例えば、開放感のあるオープン外構は明るい印象を与えますが、道路から室内が丸見えになったり、誰でも敷地に入りやすかったりといったデメリットも考えられます。
一方で、高い塀で囲ってしまうと、侵入者が一度敷地内に入ると外から見えにくくなるというリスクもあります。
人感センサー付きの照明を設置して防犯効果を高めたり、リビングの前だけは視線を遮る高さのフェンスを設けたりと、見た目のデザインと機能面のバランスを考えることが大切です。
周辺の環境や人通りなども考慮しながら、安心して暮らせる外構計画を立てましょう。
新築住宅における外構工事の進め方と最適なタイミング

新築の家づくりにおいて、外構工事をいつ、どのように進めればよいのかは非常に悩ましいポイントです。
建物の計画に集中するあまり、外構は後回しにされがちですが、スムーズに進めるためには建物と並行して計画することが成功のカギとなります。
ここでは、理想の外構を実現するための具体的な進め方を5つのステップで解説します。
【ステップ1】情報収集とイメージの具体化
まずは、自分たちがどんな外構にしたいのか、理想のイメージを具体化することから始めましょう。
スマートフォンのアプリInstagram(インスタグラム)やPinterest(ピンタレスト)で「外構 デザイン」「新築 エクステリア」などと検索すると、たくさんの素敵な施工事例を見つけることができます。
気に入った写真があれば、スクリーンショットを撮って専用のフォルダにまとめておくと、後で家族とイメージを共有したり、業者に希望を伝えたりする際に非常に役立ちます。
また、住宅雑誌やエクステリア専門誌を眺めるのも良いでしょう。
様々な事例を見る中で、「こんな雰囲気の門柱がいい」「ウッドデッキでバーベキューがしたい」「家庭菜園のスペースが欲しい」といった具体的な要望が明確になっていきます。
【ステップ2】業者探しと相談の開始時期
理想の外構イメージが固まってきたら、次はそれを形にしてくれるパートナー、つまり施工業者を探します。
外構工事を相談するタイミングとして最も理想的なのは、建物の間取りや配置が具体的に決まった段階です。
このタイミングであれば、リビングの大きな窓の前に視線を遮る植栽を計画したり、玄関ドアの色と門扉のデザインを合わせたりと、建物と一体感のある美しいデザインを実現しやすくなります。
また、給排水管やガス管などの配管ルートも考慮しながら計画できるため、「ここにカーポートの柱を立てたかったのに、水道管が通っていて掘れない」といった後々のトラブルを防ぐことにも繋がります。
遅くとも、建物の着工までには相談を開始することを強くおすすめします。
【ステップ3】現地調査とプランニング
相談する業者がある程度決まったら、担当者に実際に現地を見てもらう「現地調査」を依頼します。
プロの視点で、敷地の正確な寸法や高低差、日当たりの状況、隣家の窓の位置、電柱やマンホールの位置などを細かくチェックしてもらい、プランニングの基礎情報としてもらいます。
現地調査が終わると、いよいよ具体的なプランニングの打ち合わせです。
ステップ1で集めた写真などを見せながら、自分たちの理想のイメージやライフスタイル(「子どもが小さいので庭で安全に遊ばせたい」「将来は車がもう一台増える予定」など)、予算感をできるだけ詳しく伝えましょう。
優れた業者は、こちらの要望を汲み取り、さらにプロならではの視点を加えた魅力的なプランを提案してくれます。
【ステップ4】見積もり確認と契約
プランが固まったら、業者から図面と見積書が提出されます。
この時、1社だけでなく2〜3社から相見積もりを取ると、費用の相場感が分かり、各社の提案内容を比較検討できるためおすすめです。
見積書を確認する際は、総額だけでなく、「〇〇工事一式」のように項目が大雑把になっていないか、単価や数量が明記された詳細な内訳になっているかを必ずチェックしましょう。
内容に不明な点があれば、遠慮なく質問して全て納得した上で契約に進むことが大切です。
工事の期間や支払い条件、保証内容などもしっかりと書面で確認し、契約書にサインします。
【ステップ5】着工から完成・引き渡し
契約が完了すると、いよいよ外構工事の着工です。
工事が始まる前には、業者が近隣の方々へ挨拶回りをしてくれるのが一般的ですが、施主としても一言挨拶をしておくと、その後のご近所付き合いがよりスムーズになります。
工事期間中は、可能であれば時々現場に顔を出し、進捗状況を確認したり、職人さんとコミュニケーションを取ったりすると良いでしょう。
そして工事が完了したら、すぐに引き渡しを受けるのではなく、必ず担当者と一緒に最終チェックを行います。
図面通りにできているか、フェンスにぐらつきはないか、タイルに傷やひび割れはないかなど、隅々まで細かく確認し、もし修正が必要な点があれば、きちんと対応してもらってから引き渡しを受けましょう。
外構工事の費用相場と主な内訳

外構工事を計画する上で、最も気になるのが「一体いくらかかるのか」という費用についてではないでしょうか。
ここでは、新築外構の全体的な費用相場と、価格を上手にコントロールするためのコツについて解説します。
新築の費用総額は建築費の10%(100万円〜300万円)が目安
外構工事の費用は、土地の広さや高低差、工事の内容、使用する素材のグレードによって大きく変動しますが、一般的に新築住宅の場合、建物の建築費の10%程度が目安とされています。
例えば、建築費が2,500万円の住宅であれば、250万円程度を外構予算として考えておくとよいでしょう。
実際の価格帯としては、100万円〜300万円の範囲に収まるケースが多く見られます。
シンプルな駐車場と最低限のアプローチ、砂利敷きといった内容であれば100万円以下に抑えることも可能ですし、カーポートを2台分設置したり、こだわりのタイルや天然木を使ったりすれば300万円以上になることもあります。
まずはこの「建築費の10%」を目安として大まかな予算を確保し、その中でどこに費用をかけ、どこを節約するのかを考えていくことが、賢い資金計画の第一歩です。
工事の種類別費用と価格を抑えるコツ
外構全体の費用は、個々の工事費用の積み重ねで決まります。
費用を上手にコントロールするためには、価格を抑えるためのいくつかのコツを知っておくことが有効です。
まず一つ目は、DIY(自分で行うこと)を取り入れることです。
例えば、簡単な花壇づくりや、広範囲の砂利敷き、芝生張りなどは、比較的DIYに挑戦しやすい部分です。
専門的な技術が必要なコンクリート工事やブロック積みはプロに任せ、自分たちでできる範囲の作業を行うことで、人件費を節約できます。
二つ目は、素材のグレードを見直すことです。
例えば、アプローチの素材を全面天然石にするのではなく、人の目につきやすい部分だけ天然石にし、他はコンクリート洗い出し仕上げにするなど、素材を使い分けることでコストダウンが図れます。
三つ目は、複数の業者から相見積もりを取ることです。
同じ工事内容でも業者によって見積もり金額は異なります。
適正な価格で信頼できる業者を選ぶためにも、比較検討は非常に重要です。
失敗しない業者選び2つの依頼先とメリット・デメリット

外構工事の依頼先は、大きく分けて「ハウスメーカー・工務店」と「外構・エクステリア専門業者」の2つがあります。
それぞれにメリットとデメリットがあるため、両者の特徴をよく理解した上で、自分たちの希望や状況に合った依頼先を選ぶことが、後悔しないための重要なポイントです。
ハウスメーカー・工務店
新築住宅を建てる際、その住宅を建設するハウスメーカーや工務店に外構工事もまとめて依頼する方法です。
最大のメリットは、打ち合わせの窓口が一本化されるため、手間が少ないことです。
建物と外構の担当者が同じ社内、あるいは提携会社であるため、情報の連携がスムーズで、建物と調和の取れたデザインを提案してもらいやすいでしょう。
また、外構工事費を住宅ローンに含めて借り入れしやすい点も大きな魅力です。
一方で、デメリットとしては、ハウスメーカーが下請けの外構業者に工事を発注するため、中間マージンが発生し、専門業者に直接依頼するよりも費用が割高になる傾向があります。
また、提携している業者が限られている場合、デザインの選択肢が少なくなる可能性も考えられます。
外構・エクステリア専門業者
自分でインターネットや紹介などを通じて、外構・エクステリア工事を専門に行っている業者を探して直接依頼する方法です。
こちらのメリットは、専門的な知識や経験が豊富なことです。
デザインの提案力が高く、様々な素材や工法に詳しいため、こだわりのある外構を実現したい場合に適しています。
また、ハウスメーカーなどを介さないため中間マージンが発生せず、同じ内容の工事であればコストを抑えられる可能性が高いです。
デメリットとしては、数多くの業者の中から、信頼できる一社を自分で探さなければならないという手間がかかる点です。
また、業者によってデザインの得意分野や技術力に差があるため、施工事例などをよく確認し、慎重に選ぶ必要があります。
外構工事に関するよくある質問

ここまで外構工事の全体像について解説してきましたが、ほかにも細かな疑問点がいくつかあるかと思います。
そこで、家づくりを始めたばかりの方が抱きがちな、外構工事に関するよくある質問をQ&A形式でまとめました。
Q.「外構」と「外溝」の違いは?
A. この2つの言葉は読み方が同じ「がいこう」であるため、非常によく混同されますが、意味は全く異なります。
「外構」は、これまで説明してきた通り、家の外周りの構造物や設備全般を指す言葉です。
一方で「外溝」は、道路の脇などにある水の流れる「みぞ(溝)」を指します。
パソコンやスマートフォンで「がいこう」と入力すると、両方の漢字が変換候補に出てくるため間違えやすいのですが、住宅の工事について話す場合は「外構」が正解です。
見積書や契約書などの正式な書類では必ず「外構」が使われますので、覚えておきましょう。
もしインターネットで情報を検索する際に間違えて「外溝工事」と入力しても、検索エンジンが意図を汲み取って「外構工事」の結果を表示してくれることがほとんどです。
Q.工事期間の目安はどれくらい?
A. 外構工事にかかる期間は、工事の規模や内容、天候によって大きく変わりますが、一般的な新築戸建て住宅の場合、おおよそ2週間から1ヶ月程度を見ておくとよいでしょう。
例えば、駐車場をコンクリートで舗装し、門柱とアプローチ、最低限のフェンスを設置するようなシンプルな工事であれば、2週間程度で完了することが多いです。
ここにウッドデッキの設置や広範囲の植栽などが加わると、3週間から1ヶ月以上かかることもあります。
特にコンクリートは、打設した後に固まるまで養生期間が必要なため、その日の作業が早く終わっても次の工程に進めない日があります。
また、雨が降ると作業ができない工事も多いため、梅雨の時期などは工期が延びやすくなります。
正確な工期については、必ず事前に業者に確認しておきましょう。
Q.建物完成後からでも工事は可能?
A. はい、もちろん可能です。
建物の引き渡しを受けて、実際に住み始めてから外構工事を行うことも全く問題ありません。
予算の都合で、最初は最低限の工事だけ行い、数年後にお金を貯めてからウッドデッキを追加するといった計画も立てられます。
ただし、建物完成後に工事を行う場合、いくつかの注意点があります。
まず、住みながらの工事となるため、工事車両の出入りや作業音、職人さんの出入りがあることを理解しておく必要があります。
また、重機を使うような大掛かりな工事の場合、すでに完成している建物の基礎や壁、給排水管などを傷つけないよう、より慎重な作業が求められるため、工事費用が若干割高になる可能性もあります。
可能であれば、建物の工事と並行して計画を進めるのが最も効率的でおすすめです。
外構工事について知り、理想のマイホームを叶えよう
今回は、「外構工事とは何か」という基本的な知識から、具体的な工事の種類と費用、新築での計画の進め方、そして業者選びのポイントまで、網羅的に解説しました。
外構は、単なる「家の外側」ではなく、住まいの価値を高め、家族の毎日を豊かにしてくれる大切な空間です。
後回しにせず、建物の計画と同じくらい真剣に向き合うことで、きっと「この家を建ててよかった」と思える満足度の高いマイホームが完成するはずです。
この記事が、あなたの理想の家づくりへの第一歩となれば幸いです。
まずはご家族でどんな暮らしがしたいかを話し合い、楽しみながらイメージを膨らませてみてください。
お問い合わせ・資料請求は、下記お問い合わせフォームからお気軽にご連絡ください。