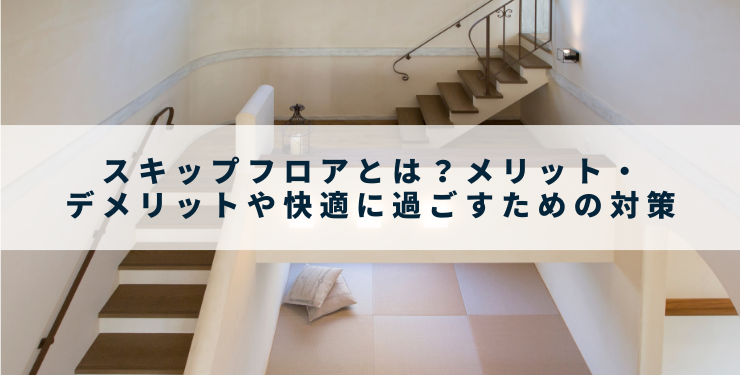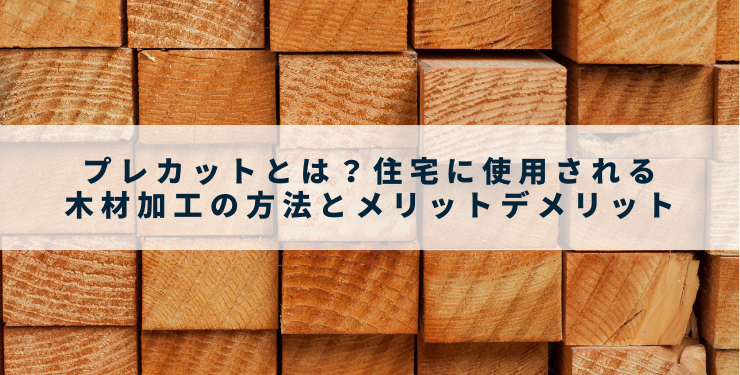中古の木造住宅を探していると、「法定耐用年数は22年です」という言葉を耳にすることがあります。
「え、じゃあ築25年のこの家は価値がないの?」「あと数年しか住めないってこと?」 そんな大きな不安を感じて、購入をためらってしまう方も少なくありません。
しかし、ご安心ください。
その「耐用年数22年」という数字は、家が実際に住める期間、つまり「寿命」とは全く関係ありません。
この記事では、多くの方が誤解しがちな木造住宅の「法定耐用年数」と「本当の寿命」の違いを徹底的に解説します。
さらに、耐用年数が税金や不動産売買、住宅ローンにどう影響するのかまで、専門家の視点で分かりやすくお伝えします。
結論 木造住宅の耐用年数は「法定22年」と「実際の寿命」の2種類

中古の木造住宅を検討する上で最も重要な知識は、「法定耐用年数」と、実際に住み続けられる「寿命」が全く異なる指標であるということです。
この2つの違いを理解することが、不安解消の第一歩です。
税金の計算で使う「法定耐用年数」
法定耐用年数とは、国税庁が定めた、税金の計算(減価償却)のために使われる“帳簿上の年数”のことです。
木造の居住用建物の場合、構造や用途を問わず一律で「22年」と定められています。
これは、不動産オーナーなどが確定申告をする際に、建物の取得費用を22年かけて少しずつ経費として計上していくための会計上のルールに過ぎません。
あくまで税務上の基準であり、建物の物理的な強度や、「あと何年住めるか」という実際の寿命とは一切関係ありません。
「法定耐用年数が22年だから、築22年で建物の市場価値がゼロになる」というのは大きな誤解なのです。
実際に住める期間を示す「物理的耐用年数(寿命)
木造住宅が実際に住める期間、つまり「本当の寿命(物理的耐用年数)」は、適切なメンテナンスを行えば50年、80年、さらには100年以上にもなります。
事実、早稲田大学の研究によると、日本の木造住宅の平均寿命は年々延びており、2011年時点の調査では65年に達しています。
(参考 https://rea-osaka.or.jp/kantei/46.pdf)
これは、建築技術の向上や、良質な住宅を長く維持しようという意識の高まりによるものです。
特に、国が定める基準をクリアした「長期優良住宅」は、100年以上の耐久性を持つことを前提に設計されています。
法定耐用年数という数字に惑わされず、その家がどのように建てられ、どのように維持管理されてきたか、という「品質」を見ることが、中古住宅選びでは最も重要です。
一目でわかる 法定耐用年数と物理的耐用年数の違い
| 項目 | 法定耐用年数(税法上の年数) | 物理的耐用年数(本当の寿命) |
| 意味 | 税金計算のための、帳簿上の価値がゼロになるまでの期間 | 建物が物理的に住居として使用できる、実際の期間 |
| 年数 | 木造住宅は一律22年 | 30年~80年以上(メンテナンス次第) |
| 主な目的 | 減価償却費の計算(確定申告)、固定資産税評価の算出 | 居住、資産としての長期保有 |
| 定めている機関 | 国税庁 | (定めはない) |
| 寿命を延ばす方法 | 延長はできない | 定期的なメンテナンス、適切なリフォーム |
法定耐用年数22年が関わる税金と減価償却

法定耐用年数は「寿命とは違う」と理解しても、具体的に何に使われるのか、私たちの生活にどう関わるのかが気になるところです。
ここでは、特に重要な「税金」との関係について詳しく解説します。
不動産所得の計算に必須の減価償却
不動産投資などで家賃収入がある場合、確定申告で経費を計上します。
この際に建物の取得費用を法定耐用年数に分割して毎年経費として計上することを減価償却といいます。
木造住宅の法定耐用年数は22年なので、22年間にわたって費用を分割計上していくことになります。
計算は主に「定額法」が用いられ、毎年同じ額を経費にしていきます。
具体的な計算式は「建物取得価額 × 償却率」です。
木造住宅の償却率は0.046であり、例えば3000万円で取得した建物の場合は「3000万円 × 0.046 = 138万円」を年間の減価償却費として計上できます。
このルールは国税庁によって定められており、不動産の収支計算において非常に重要な要素です。
この減価償却があることで、帳簿上の利益を圧縮し、所得税や住民税を抑える効果が期待できます。
(参考 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2100.htm)
固定資産税の評価額への影響
固定資産税は、毎年1月1日時点の土地や家屋の所有者に対して課される税金です。
家屋の評価額は、年数の経過によって価値が減少することを考慮して計算されます。
この価値の減少を示す「経年減点補正率」は、法定耐用年数をもとに設定されています。
木造の居住用家屋の場合、法務局の基準では建築翌年から評価額が下がり始め、25年経過すると下限である20%まで評価額が下がった状態で固定されます。
つまり、法定耐用年数である22年を過ぎて、さらに築25年を超えても、固定資産税がゼロになるわけではありません。
あくまで評価額がそれ以上は下がらなくなるという仕組みです。
このように、法定耐用年数は固定資産税の計算においても基準の一つとして利用されています。
実際の評価額は自治体によって異なるため、詳細は市町村役場の資産税課などで確認することをおすすめします。
住宅ローン控除と耐用年数の関係
中古住宅を購入して住宅ローン控除(住宅ローン減税)を利用する場合、一定の耐震基準を満たしている必要があります。
法定耐用年数が直接の要件ではありませんが、築年数に関する要件が存在します。
具体的には、1982年(昭和57年)1月1日以降に建築された新耐震基準適合住宅であることが一つの要件です。
したがって、法定耐用年数(22年)を超えている木造住宅であっても、この新耐震基準を満たしていれば住宅ローン控除の対象となります。
もし1981年以前の旧耐震基準の建物の場合は、「耐震基準適合証明書」の取得や「既存住宅売買瑕疵保険への加入」など、現行の耐震基準に適合していることを証明できれば控除を受けられる可能性があります。
法定耐用年数という言葉に惑わされず、購入を検討している物件がいつ建てられたものか、新耐震基準を満たしているかを確認することが非常に重要です。
築22年超え中古木造住宅の資産価値と売買

法定耐用年数が不動産取引、特に中古住宅の資産価値や住宅ローンに与える影響について具体的に解説します。
法定耐用年数を超えた物件の評価
不動産の査定において、築年数が評価の一つの指標になることは事実です。
しかし、「法定耐用年数超え=資産価値ゼロ」ということには絶対になりません。
金融機関や不動産会社が査定を行う際、法定耐用年数はあくまで参考指標の一つです。
それ以上に重視されるのが、建物の現在の状態、過去のメンテナンスやリフォームの履歴、そして立地条件です。
例えば、築30年でも定期的に外壁や屋根のメンテナンスが行われ、水回りがリフォームされている家は、メンテナンスされていない築15年の家よりも高く評価されることがあります。法定耐用年数という数字だけで判断せず、その家がどれだけ大切にされてきたかという「品質」で価値を見ることが重要です。
中古住宅購入時の住宅ローン利用の可否
「法定耐用年数を超えた物件は、住宅ローンを組めないのでは?」というのも、よくある不安の一つです。
結論から言うと、法定耐用年数を超えていても住宅ローンを組むことは十分に可能です。
確かに、一部の金融機関では法定耐用年数を融資期間の上限の目安にすることがあります。
しかし、多くの金融機関は、申込者の返済能力(年収、勤続年数、信用情報など)と、物件の現在の状態や担保価値を総合的に判断して融資を決定します。
特に、しっかりとしたホームインスペクション(住宅診断)で建物の状態が良好であることが証明できれば、融資の可能性はさらに高まります。
諦めずに複数の金融機関に相談したり、中古住宅に詳しい不動産会社に相談したりすることが大切です。
売却査定で重要視される建物の状態
ご自身の家を売却する場合、査定ではどのような点が評価されるのでしょうか。
法定耐用年数を超えた木造住宅であっても、高く評価されるポイントは存在します。
最も重要なのは、建物の維持管理状態が良いことです。
特に、「メンテナンス履歴(修繕記録)」は客観的な証拠として非常に有効です。
いつ頃、外壁塗装や屋根の補修、シロアリの防蟻処理を行ったかといった記録がしっかり残っていると、査定額にプラスに働く可能性が高まります。
また、キッチンや浴室、トイレなどの水回りの設備が新しいことや、内装が清潔に保たれていることも重要です。
買主が購入後にリフォーム費用をあまりかけずに住める状態であれば、それが物件の付加価値となり、査定評価の向上に繋がります。
木造住宅の実際の寿命を60年以上に延ばすメンテナンス

木造住宅の本当の寿命は、日頃のメンテナンスによって大きく左右されます。
大切な自宅に長く快適に住み続けるためには、計画的なメンテナンスが欠かせません。
10〜15年周期の外壁・屋根の塗装と修繕
屋根や外壁は、常に紫外線や雨風に晒され、家全体を外部環境から守っている最も重要な部分です。
塗装の防水効果が切れたり、ひび割れ(クラック)が生じたりすると、そこから雨水が壁の内部に浸入し、柱や土台といった構造体を腐らせる原因となります。
一般的に10年~15年に一度のペースで、専門家による点検と再塗装を行うことが、家の寿命を延ばす上で非常に重要です。
費用はかかりますが、構造体が傷んでからの大規模な修繕に比べれば、はるかに安く済みます。
5〜10年ごとのシロアリ対策(防蟻処理)
木造住宅の大敵であるシロアリの被害を防ぐことも、寿命を延ばすためには不可欠です。
新築時に行われる防蟻処理の効果は、薬剤の種類にもよりますが一般的に5年程度で切れてしまいます。
効果が切れた状態を放置すると、湿気の多い床下や水回りからシロアリが侵入し、土台や柱を食べて内部をスカスカにしてしまう恐れがあります。
一度被害にあうと、耐震性が著しく低下してしまいます。
少なくとも5年に一度は専門業者による床下点検を行い、必要に応じて防蟻処理を再施工することが、家を長持ちさせるための重要な投資です。
給排水管や住宅設備の定期的な点検と交換
木材にとって湿気は劣化の大きな原因です。特に、キッチンやお風呂、トイレといった水回りは、小さな水漏れが起こりやすい場所です。
床下や壁の内部で水漏れが長期間続くと、木材が腐ってしまいます。
定期的に水回りの配管周辺を点検し、異常があれば早めに修繕することが、家の寿命を守ることに繋がります。
また、給湯器や換気扇などの住宅設備も10年~15年で寿命を迎えることが多いため、計画的に交換していくことが快適な暮らしの維持に繋がります。
普段から室内の換気を心がけ、湿気を溜めない工夫も大切です。
木造住宅の耐用年数に関するよくある質問

最後に、木造住宅の耐用年数に関して多くの方が抱く疑問について、Q&A形式でお答えします。
Q.法定耐用年数を過ぎたら住めなくなる?
いいえ、全くそんなことはありません。
前述の通り、法定耐用年数22年はあくまで税金の計算上で使われる帳簿上の数字です。
この年数を過ぎたからといって、建物の安全性がなくなったり、居住できなくなったりするわけではありません。
実際に、日本では築22年を超える木造住宅が数多く存在し、人々が快適に暮らしています。
大切なのは法定耐用年数という数字ではなく、その建物が適切にメンテナンスされ、安全な状態が保たれているかどうかです。
定期的な点検や補修を行っていれば、築50年、60年と長く安心して住み続けることが可能です。
Q.リフォームで耐用年数は延びる?
これはよくある質問ですが、答えは「目的によって変わる」となります。
まず、税金計算で使われる法定耐用年数は、大規模なリフォームやリノベーションを行っても延長されたりリセットされたりすることはありません。
あくまで建物の構造と用途で定められた固定の年数です。
一方で、家が実際に住める期間である物理的耐用年数(寿命)は、適切なリフォームによって大幅に延ばすことが可能です。
例えば、屋根の葺き替えや外壁の張り替え、耐震補強などを行えば、建物の耐久性は大きく向上します。
また、リフォームは不動産としての資産価値の維持・向上にも直結します。
法定耐用年数は変わりませんが、家の寿命と価値はリフォームによって大きく伸ばせるのです。
Q.築30年の木造住宅は購入しても大丈夫?
はい、建物の状態が良ければ全く問題ありません。
築30年という築年数だけで判断するのではなく、購入後に後悔しないために以下の3つのポイントを必ずチェックしましょう。
- ホームインスペクション(住宅診断)を実施する
住宅診断の専門家が、屋根裏や床下など普段見えない部分まで劣化状況や欠陥の有無を診断してくれます。
購入前に建物の健康状態を正確に把握できるため、安心して取引を進めるための必要不可欠な投資です。 - メンテナンス・リフォーム履歴を確認する
これまでの修繕記録を取り寄せましょう。
「10年ごとに外壁塗装を実施」「5年前に給湯器を交換」といった記録があれば、その家が大切にされてきた証拠です。
特に外壁・屋根とシロアリ対策の履歴は必ず確認しましょう。 - 新耐震基準(1981年6月以降)に適合しているか確認する
1981年6月1日以降に建築確認を受けた建物は、震度6強~7程度の地震でも倒壊しない「新耐震基準」で建てられています。
この基準を満たしていれば、耐震性について一定の安心感があり、住宅ローン控除も利用しやすくなります。
まとめ
木造住宅の「法定耐用年数」と「本当の寿命」の違いについて解説しました。
最後に、この記事の最も重要なポイントをまとめます。
- 法定耐用年数(22年)は税金計算のための数字であり、家の寿命とは全く関係ありません。
- 木造住宅の本当の寿命はメンテナンス次第で、50年、80年と長く住み続けることが可能です。
- 中古住宅を検討する際は、築年数という数字だけでなく、メンテナンス履歴や建物の状態をしっかり確認することが重要です。
法定耐用年数という言葉の本当の意味を正しく理解し、数字に惑わされることなく、質の良い住まいを見極める目を養うことが、賢い家選びの第一歩です。
山根木材が手がける木造の注文住宅は、強度や耐久性に優れる広島県産のヒノキを土台に標準採用。
長期優良住宅とZEHを標準仕様とし、耐震等級3を実現するなど、長く安心して暮らせる家づくりを追求しています。
中古住宅のリフォームに関するご相談も承っておりますので、お気軽にご相談ください。
お問い合わせ・資料請求は、下記お問い合わせフォームからお気軽にご連絡ください。