「親の近くで子育てしたい」「高齢になった親のサポートをしたい」「建築費用を協力して負担を減らしたい」など、さまざまな理由から三世帯住宅を検討する方が増えています。
三世帯住宅は、家族みんなが助け合いながら暮らせる魅力的な選択肢ですが、同時に「建築費用はどれくらいかかるの?」「世帯間のプライバシーは確保できる?」といった不安も大きいのではないでしょうか。
この記事では、三世帯住宅の建築を検討し始めたばかりの方に向けて、以下の内容を分かりやすく解説します。
- 後悔しないために知っておきたいメリット・デメリットと対策
- 3つの同居タイプとそれぞれの特徴
- タイプ別のリアルな費用相場とコストを抑える方法
- プライバシーを守るための具体的な間取り実例
- 2025年に活用できる補助金制度
この記事を読めば、あなたの家族にとって最適な三世帯住宅の形が見えてくるはずです。
ぜひ、理想の家づくりの参考にしてください。
三世帯住宅のメリット・デメリット徹底比較

三世帯住宅には多くの魅力がありますが、もちろんデメリットも存在します。
両方を正しく理解し、事前に対策を講じることが、後悔しない家づくりのためには不可欠です。
経済的・精神的な5つのメリット
- 子育てや介護で助け合える 共働き夫婦にとって、急な残業や子どもの発熱時に親が近くにいる安心感は計り知れません。
逆に、親世帯が高齢になった際には、日常的な見守りやサポートがしやすくなります。 - 建築費や生活費を節約できる 土地代や建築費を協力して負担することで、一世帯あたりの経済的負担を軽減できます。
同居タイプによっては光熱費や通信費の基本料金も一本化でき、日々の生活コスト削減につながります。 - 住宅ローンが組みやすい 親世帯と子世帯の収入を合算して申し込む「親子リレーローン」などを利用すれば、借入可能額を増やせる場合があります。
- 相続税が大幅に軽減される 親が住んでいた土地に同居する場合、一定の条件を満たせば「小規模宅地等の特例」が適用され、土地の相続税評価額が最大80%も減額されます。
これは非常に大きなメリットです。 - 住宅建築時に支援制度を受けられる 国や自治体は、三世帯同居を促進するための補助金や税金の優遇制度を用意しており、これらを活用することで初期費用を抑えられます。
同居ストレスを招く3つのデメリットと対策
- プライバシーを確保しにくい どんなに仲の良い家族でも、四六時中一緒では息が詰まってしまいます。
特に子世帯は、親からの干渉がストレスに感じることもあるでしょう。
【対策】 間取りを工夫することが最も有効です。
完全分離型や部分共有型を選び、各世帯が気兼ねなく過ごせるプライベート空間を必ず確保しましょう。 - 価値観やライフスタイルの違いが表面化する 世代が違えば、子育ての方針、金銭感覚、衛生観念、食事の好みなど、あらゆる面で価値観が異なります。
また、就寝時間や起床時間といった生活リズムの違いも、騒音トラブルの原因になりかねません。
【対策】 家を建てる前に、必ず家族全員で徹底的に話し合いましょう。
「生活費の分担方法」「家事の役割分担」「お互いの友人や来客のルール」「子育てや介護への関わり方」など、具体的なルールを決め、書面に残しておくことを強くおすすめします。 - 相続でトラブルになる可能性がある 三世帯住宅は、不動産の所有権が複雑になりがちです。
例えば、土地は親名義、建物は親と子の共有名義といった場合、将来どちらかの親が亡くなった際に、同居していない兄弟姉妹との間で遺産分割トラブルに発展する可能性があります。
【対策】 建築前に、誰がどのようにお金を出し、不動産の登記(名義)をどうするか、専門家である司法書士や税理士に相談しながら決めましょう。
将来の相続まで見据えた計画を立てておくことが重要です。
三世帯住宅の3つの同居タイプと特徴

三世帯住宅には、世帯間の距離感やライフスタイルによって大きく3つのタイプがあります。
それぞれの特徴を理解し、ご自身の家族に最適な形を見つけることが成功の第一歩です。
プライバシーを重視する完全分離型
完全分離型は、玄関、キッチン、浴室、トイレといった生活に必要な設備を各世帯で完全に独立させるスタイルです。
建物内部で世帯間の行き来ができない設計も多く、まるで同じ建物に2つ(または3つ)の家が隣接しているようなイメージです。
このタイプの最大のメリットは、お互いのプライバシーを最大限に尊重できる点です。
生活音や来客などを気にする必要が少なく、各世帯が独立したライフスタイルを維持できます。
一方で、すべての設備を複数設置するため、建築コストが最も高額になり、広い敷地面積が必要になる点がデメリットです。
スープの冷めない距離で、必要な時には助け合いながらも、普段はそれぞれの生活を大切にしたい家族におすすめです。
生活費を抑える部分共有型
部分共有型は、玄関や浴室、LDK(リビング・ダイニング・キッチン)など、住まいの一部を共有し、寝室などのプライベート空間は各世帯で分けるスタイルです。
どこを共有スペースにするかによって、プライバシーの度合いや建築コストを柔軟に調整できるのが大きな特徴です。
例えば、「玄関と浴室だけ共有する」「2階に共有のセカンドリビングを設ける」など、家族のコミュニケーションの取り方に合わせて設計できます。
完全分離型よりも建築コストを抑えられるメリットがありますが、共有スペースの使い方や光熱費の分担について、事前に家族間でルールを決めておくことがトラブルを避ける鍵となります。
適度な距離感を保ちつつ、家族のふれあいも大切にしたい家族にぴったりのスタイルです。
建築費が最も安い完全共有型
完全共有型は、寝室以外のほとんどの空間(玄関、LDK、浴室、トイレなど)を全世帯で共有するスタイルです。昔ながらの大家族の暮らしをイメージすると分かりやすいでしょう。
このタイプの最大のメリットは、設備の重複が少ないため、3つのタイプの中で最も建築コストを抑えられる点です。
水道光熱費の基本料金も一本化できるため、ランニングコストの節約にもつながります。
ただし、常に家族の気配を感じながら生活するため、プライバシーの確保が難しくなるのが最大のデメリットです。
生活時間帯や価値観の違いがストレスの原因になる可能性もあるため、常に助け合い、賑やかに暮らしたいという、非常に良好な関係性が築けている家族向けのスタイルと言えます。
三世帯住宅のタイプ別費用相場

三世帯住宅を建てる上で最も気になるのが費用です。
ここでは、住宅のタイプ別に具体的な建築費用の相場を見ていきましょう。
完全分離型の費用相場4,000万円~8,000万円
設備がほぼ2軒分必要になる完全分離型は、建築費用も高額になる傾向があります。
延床面積や設備のグレードにもよりますが、一般的な木造住宅の場合、総額で4,000万円から8,000万円程度が一つの目安となります。
元記事で示されている坪単価の相場(80万円~140万円)も参考にすると、例えば60坪の家なら4,800万円~8,400万円となり、総額のイメージと大きくは違いません。
土地の状況や導入する設備の仕様によっては、さらに高額になる可能性もあります。
部分共有型の費用相場3,500万円~7,000万円
設備の一部を共有する部分共有型は、完全分離型に比べてコストを抑えることができます。
共有する範囲によって費用は大きく変動しますが、総額で3,500万円から7,000万円程度が相場です。
例えば、キッチンや浴室といった高額な水回り設備を共有するだけで、数百万円のコストダウンにつながることもあります。
どこまでをプライベート空間とし、どこからを共有スペースとするか、家族の希望と予算のバランスを考えながら計画を進めることが重要です。
建築費用を抑える3つのポイント
高額になりがちな三世帯住宅ですが、工夫次第で費用を抑えることは可能です。
ここでは代表的な3つのポイントをご紹介します。
- 建物の形状をシンプルにする 住宅は、凹凸が多い複雑な形よりも、総二階建てのようなシンプルな四角い形の方が建築コストを抑えられます。
シンプルな形状は、耐震性を高める上でも有利に働きます。 - 設備の共有範囲を広げる キッチンや浴室、トイレなどの水回り設備は、住宅設備の中でも特に高額です。
これらの共有範囲を広げることで、設備費用だけでなく、配管工事などの費用も削減できます。 - 補助金や税制優遇を最大限活用する 国や自治体は、三世帯同居を支援するための補助金制度や税制優遇措置を用意しています。
後ほど詳しく解説しますが、これらの制度を漏れなく活用することで、負担を数十万円から数百万円単位で軽減できる可能性があります。
三世帯住宅のプライバシーを守る間取り

ここからは、より具体的な生活をイメージするために、タイプ別の間取りをご紹介します。
プライバシーとコミュニケーションのバランスをどう取るかが、間取りづくりの鍵です。
玄関から分離する完全分離型2階建ての間取り
完全分離型で最も一般的なのが、1階を親世帯、2階を子世帯(またはその逆)に完全に分ける間取りです。
このプランの最大のポイントは、玄関を世帯ごとに別に設けることです。
これにより、お互いの来客に気を使う必要がなくなり、郵便物や宅配便の受け取りもスムーズになります。
1階の親世帯は、庭へのアクセスがしやすく、階段の上り下りがないため老後も安心です。
2階の子世帯は、日当たりや眺望が良い空間を確保できます。
各フロアにLDKと水回りを完備することで、生活動線が完全に分離され、気兼ねなく暮らせます。
ただし、2階の足音が1階に響かないよう、床の防音対策は必須です。
この間取りは、プライバシーを最優先に考え、お互いの生活リズムを尊重したい家族に最適な実例と言えるでしょう。
水回りだけを共有する部分共有型の間取り
部分共有型は、「どこを共有するか」で暮らし方が大きく変わります。
例えば、玄関と浴室・洗面所は共有し、各世帯にミニキッチン付きのLDKと寝室を設ける間取りはいかがでしょうか。
朝の忙しい時間帯はそれぞれのLDKで過ごし、夜は広い共有の浴室で一日の疲れを癒す、といった暮らしが可能です。
この間取りのメリットは、生活の中心となるLDKが各世帯にあるため、プライベートな時間を確保しやすい点です。
一方で、浴室や玄関では顔を合わせる機会が自然に生まれるため、コミュニケーションが途絶えることもありません。
コスト面でも、高額な浴室設備を一つにまとめることで大きな節約効果が期待できます。
共有スペースの掃除当番や光熱費の分担など、事前にルールを決めておけば、快適な同居生活が実現できるでしょう。
都市部で人気の3階建ての間取り
敷地が限られる都市部で三世帯住宅を建てる場合、3階建ては非常に有効な選択肢です。
縦の空間を活かすことで、各世帯の独立性を確保しやすくなります。
間取りの実例として、1階を親世帯の居住スペースとビルトインガレージ、2階を家族全員が集まるLDKと水回り、3階を子世帯のプライベートフロアとするプランが人気です。
このプランでは、2階が共有のリビングとなるため、家族のコミュニケーションの中心になります。
食事の時間などを共にすることで、自然な交流が生まれるでしょう。そして、1階と3階は完全にプライベートな空間として使えるため、オンとオフの切り替えがしやすいのがメリットです。
ただし、毎日の階段移動が負担にならないか、将来を見据えてホームエレベーターの設置スペースを確保しておくなど、バリアフリーへの配慮も重要なポイントとなります。
2025年に使える国と自治体の補助金制度
三世帯住宅の建築は、国や自治体の補助金制度の対象となる場合があります。
費用負担を軽減するために、活用できる制度は漏れなくチェックしましょう。
国土交通省の子育てグリーン住宅支援事業(2025年度)
子育てグリーン住宅支援事業は、2050年カーボンニュートラルの実現に向け、省エネ性能の高い住宅の取得を支援する2025年度の国の事業です。
「子育て」という名称ですが、新設された「GX志向型住宅」※という最高ランクの省エネ住宅については、世帯を問わず最大160万円の補助対象となるのが大きな特徴です。
もちろん、三世帯住宅を検討している方の多くが含まれる子育て世帯(18歳未満の子を有する世帯)または若者夫婦世帯(夫婦のいずれかが39歳以下の世帯)への支援も手厚く、長期優良住宅で最大80万円、ZEH水準住宅で最大40万円の補助金を受け取ることができます。
住宅の省エネ性能に対する要求水準は年々高まっていますが、こうした補助金を賢く活用することで、初期費用を抑えながら、光熱費も安く、快適で健康的な住まいを実現できます。
(参考: 国土交通省 住宅省エネ2025キャンペーン 公式ウェブサイト)
※GX志向型住宅とは、高い断熱性能に加え、太陽光発電などの再生可能エネルギーを導入することで、家庭で消費するエネルギー量をおおむねゼロ以下にする住宅のことです。
各自治体が実施する多世代同居支援制度
国とは別に、自治体独自で三世代同居や近居を支援する補助金制度を設けている場合があります。
例えば、元記事でも紹介されている広島市の「三世代同居・近居支援事業」は、市外から転入して親と同居または近居を始める子育て世帯に対し、引越し費用などを助成する制度です。
このように、自治体によって制度の有無や内容、補助額、条件は大きく異なります。
「(お住まいの市区町村名) 三世代同居 補助金」などのキーワードで検索し、ご自身の自治体にどのような制度があるか、必ず事前に確認しましょう。
三世帯住宅の計画から完成までの5ステップ
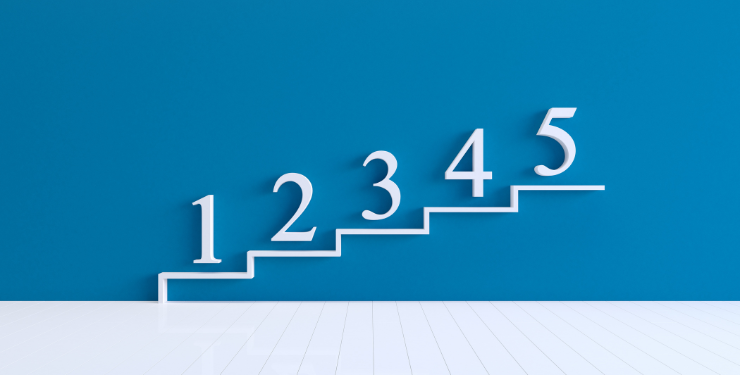
最後に、三世帯住宅の計画を始めてから、実際に新しい家での生活がスタートするまでの基本的な流れを5つのステップでご紹介します。
- ステップ1 家族会議と理想の共有 全ての始まりは家族の話し合いです。
なぜ同居したいのか、どんな暮らしがしたいのか、お金の計画はどうするか、お互いの希望と不安をすべてテーブルの上に出して、理想の暮らしのイメージを共有しましょう。 - ステップ2 情報収集とハウスメーカー選び 住宅展示場を見学したり、インターネットで資料請求をしたりして情報を集めます。
特に三世帯住宅の建築実績が豊富なハウスメーカーや工務店を選ぶと、経験に基づいた的確なアドバイスがもらえるため安心です。 - ステップ3 間取りと資金計画の具体化 建築会社の担当者と打ち合わせを重ね、家族の希望を反映した具体的な間取りプランを作成してもらいます。
同時に、詳細な見積もりを取り、住宅ローンを含めた最終的な資金計画を固めます。 - ステップ4 契約・着工 プランと見積もりに納得したら、工事請負契約を結びます。
その後、土地のお清めをする地鎮祭などを経て、いよいよ家の建築工事が始まります。 - ステップ5 完成・引き渡し 工事が無事に完了し、建物の最終チェックが終わると、家の鍵が引き渡されます。
ここから、待ちに待った新しい家での三世帯同居生活がスタートします。
三世帯住宅のメリット・デメリットを把握して理想の暮らしを実現しよう!
三世帯住宅は、3つの世帯が共に支え合いながら暮らすための住まいの形です。
光熱費の節約や子育て・介護の協力といった多くのメリットがある一方で、プライバシーの確保や価値観の違いといった乗り越えるべき課題も存在します。
後悔しない三世帯住宅を実現するためには、家を建てる前の徹底した家族間の話し合いが何よりも重要です。
そして、話し合った内容を形にするためには、完全分離型、部分共有型、3階建てなど、家族に合った間取りを慎重に検討する必要があります。
広島・東広島・福山エリアで理想の注文住宅をご検討なら、広島で長年の実績を持つ私たち山根木材にご相談ください。
お客様一人ひとりの家族の形に寄り添い、ライフステージの変化も見据えた最適なプランをご提案します。まずはお気軽にお問い合わせください。
お問い合わせ・資料請求は、下記お問い合わせフォームからお気軽にご連絡ください。















