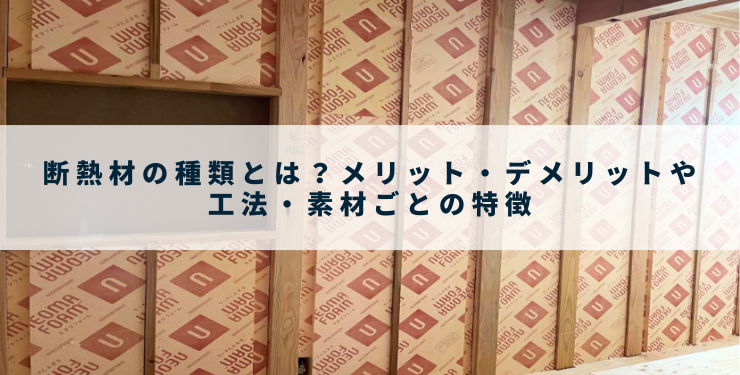「夏は涼しく、冬は暖かい家にしたい」 これからマイホームを建てる多くの方が、そう願っているのではないでしょうか。
その快適な暮らしを実現する上で、心臓部とも言えるのが「断熱材」です。
しかし、断熱材にはグラスウールやウレタンフォームなど多くの種類があり、「ハウスメーカーから標準仕様を提案されたけど、これで本当に良いのかな?」「もっと性能が良いものがあるのでは?」と悩んでしまう方も少なくありません。
断熱材は、一度施工すると簡単には交換できない重要な部分。
だからこそ、後悔しないように、その種類と特徴をしっかり理解して選ぶことが大切です。
この記事では、注文住宅を検討している方が知っておくべき断熱材の基本的な知識から、主要な断熱材の性能・価格を徹底比較し、あなたの理想の家づくりに最適な断熱材を見つけるための「選び方のポイント」まで、専門用語を避けながら分かりやすく解説します。
この記事を読めば、専門家と対等に話せるだけの知識が身につき、自信を持ってご自身の家に最適な断熱材を選択できるようになるはずです。
断熱材の性能・価格・特徴が一目でわかる比較一覧表

まずは「結局、どの断熱材がどう違うの?」という疑問に答えるため、現在日本の住宅でよく使われる代表的な断熱材8種類の特徴を一覧表にまとめました。
それぞれの性能(熱伝導率)や価格の目安、メリット・デメリットを比較して、全体像を掴んでみてください。
| 断熱材の種類 | 素材の分類 | 熱伝導率(W/m・K)の目安※ | 施工費込み価格(円/㎡)の目安 | メリット | デメリット |
| グラスウール | 無機繊維系 | 0.033~0.050 | 4,000~8,000 | ・価格が安く経済的 ・吸音性が高い ・燃えにくい |
・湿気に弱い ・施工精度で性能差が出やすい |
| ロックウール | 無機繊維系 | 0.035~0.045 | 5,000~9,000 | ・耐熱性、耐火性が高い ・撥水性が高い ・吸音性が高い |
・価格がやや割高 ・繊維が飛散しやすい |
| 硬質ウレタンフォーム | 発泡プラスチック系 | 0.020~0.036 | 6,000~12,000 | ・断熱性が非常に高い ・自己接着性で気密性が高い ・ボード/吹付が選べる |
・火災時に有毒ガス発生の恐れ ・紫外線で劣化しやすい |
| フェノールフォーム | 発泡プラスチック系 | 0.019~0.021 | 12,000~20,000 | ・トップクラスの断熱性能 ・燃えにくく有毒ガスが少ない ・経年劣化が少ない |
・価格が非常に高い ・衝撃に弱く割れやすい |
| 押出法ポリスチレンフォーム | 発泡プラスチック系 | 0.022~0.036 | 5,000~10,000 | ・水や湿気に非常に強い ・軽量で加工しやすい ・基礎断熱にも使える |
・熱に弱い ・有機溶剤に弱い |
| ビーズ法ポリスチレンフォーム | 発泡プラスチック系 | 0.034~0.040 | 4,500~9,000 | ・軽量で衝撃吸収性が高い ・水や湿気に強い ・比較的安価 |
・熱に弱い ・紫外線で劣化しやすい |
| セルロースファイバー | 天然素材系 | 0.038~0.040 | 8,000~15,000 | ・高い調湿性を持つ ・防音、吸音性に優れる ・防虫、防カビ効果がある |
・施工コストが割高 ・専門の施工業者が必要 |
| 羊毛(ウールブレス) | 天然素材系 | 0.037~0.045 | 10,000~18,000 | ・非常に高い調湿性 ・空気を浄化する効果 ・防虫効果がある |
・価格が非常に高い ・取り扱い業者が少ない |
※熱伝導率は数値が小さいほど断熱性能が高いことを示します。製品の密度やグレードによって数値は変動します。
後悔しない断熱材の選び方3つの重要ポイント

一覧表で全体像を掴んだら、次にご自身の家づくりに当てはめて、どの断熱材が最適かを見極めるための「選び方のポイント」を3つのステップで見ていきましょう。
ポイント1 断熱性能を示す熱伝導率で選ぶ
断熱材選びで最も基本的な指標が「熱伝導率」です。
これは「熱の伝わりやすさ」を示す数値で、数値が小さいほど熱が伝わりにくく、断熱性能が高いことになります。
この熱伝導率が低い素材を選ぶことが、断熱材選びの第一歩です。
では、どのくらいの性能を目指すべきでしょうか。
近年では、国が定める省エネ基準を満たす「ZEH(ゼッチ)基準」や、さらに高い断熱性を目指す「HEAT20」という基準が注目されています。
特にHEAT20にはG1・G2・G3という3つのグレードがあり、G2グレード以上を達成すると「冬でも暖房に頼りすぎず快適に過ごせる」レベルの断熱性が確保できると言われています。
例えば、広島市(省エネ基準地域区分6)でHEAT20のG2を目指す場合、壁の断熱材には熱伝導率が0.03W/m・K台のグラスウールなら約105mmの厚みが、0.02W/m・Kのフェノールフォームなら約70mmの厚みが必要、といった計算ができます。
ハウスメーカーや工務店に希望の断熱レベルを伝え、どの断熱材で、どのくらいの厚みが必要になるのかを確認することが重要です。
(参考: 一般社団法人 20年先を見据えた日本の高断熱住宅研究会 HEAT20)
ポイント2 初期費用と光熱費の総額コストで選ぶ
断熱性能と密接に関わるのが「価格」です。
一覧表の通り、一般的に高性能な断熱材ほど初期費用は高くなる傾向にあります。
しかし、ここで注意したいのが「初期費用だけで判断しない」ということです。
例えば、初期費用が50万円高い高性能な断熱材を選んだとします。
この投資によって家の断熱性が向上し、年間の冷暖房費が5万円安くなった場合、10年で元が取れる計算になります。
それ以降は、年間5万円ずつお得になるわけです。
これは「ライフサイクルコスト(LCC)」という考え方で、建築時にかかる費用(イニシャルコスト)と、住み始めてからかかる費用(ランニングコスト)を合計して考える視点です。
断熱材は、まさにこのライフサイクルコストに直結する建材です。
目先の価格だけでなく、30年、50年と住み続ける中で、トータルでどれくらいの費用がかかるのか、という長期的な視点でコストパフォーマンスを判断しましょう。
ポイント3 家の施工場所(壁・天井・床・基礎)で選ぶ
家は、場所によって求められる断熱材の特性が少しずつ異なります。
どこにどの断熱材を使うか、適材適所で考えることも大切です。
- 壁・天井
柱と柱の間や、屋根裏に施工する部分です。
最も面積が広く、多くの種類の断熱材が使われます。
グラスウールのような繊維系を隙間なく充填する方法や、硬質ウレタンフォームを吹き付ける方法が一般的です。 - 床下
地面からの冷気や湿気の影響を受けやすい場所です。
特に湿気対策が重要になるため、水や湿気に強い押出法ポリスチレンフォームや硬質ウレタンフォームなどの発泡プラスチック系断熱材がよく採用されます。 - 基礎
建物の土台となるコンクリート部分の断熱です。床下断熱と異なり、基礎自体を断熱材で覆う「基礎断熱」という工法で使われます。
地面と接し、シロアリのリスクもあるため、水に強く、防蟻処理が施された押出法ポリスチレンフォームが選ばれることがほとんどです。
【素材別】主要な断熱材8種類のメリット・デメリット

ここからは、比較表でご紹介した8種類の断熱材について、それぞれの特徴をさらに詳しく解説していきます。
メリットだけでなく、注意すべきデメリットや欠点も理解することが、最適な選択に繋がります。
グラスウール
リサイクルガラスを主原料とする、綿状の断熱材です。
現在、日本の木造住宅で最も広く使われており、コストパフォーマンスの高さが最大の魅力です。
価格は施工費込みで1㎡あたり4,000円~8,000円が目安で、比較的安価に導入できます。
また、繊維の間に空気を含む構造から吸音性にも優れており、生活音の軽減にも貢献します。
不燃材料であるため火災に強い点も安心です。
一方で、最大のデメリットは湿気に弱いことです。
壁の中で結露を起こしたり、雨漏りなどで濡れたりすると、水分を含んで断熱性能が大きく低下してしまいます。
そのため、防湿フィルムを隙間なく丁寧に施工するなど、施工会社の高い技術力が性能を維持する上で不可欠となります。
ロックウール
玄武岩などの天然岩石を高温で溶かして作る、グラスウールと似た綿状の断熱材です。
グラスウールよりも価格はやや高くなりますが、水を弾く撥水性が高いという特徴があります。
これにより、万が一水分に触れても性能が低下しにくいのがメリットです。
また、耐熱性もグラスウールより高く、1000℃以上まで耐えられるほどの防火性能を誇ります。
吸音性も高いため、空港周辺の住宅などで採用されることもあります。
デメリットとしては、素材自体が重く、施工中に繊維が脱落しやすい点が挙げられます。
また、価格がグラスウールより割高になるため、予算とのバランスを考える必要があります。
防火性や撥水性を重視する場合に有力な選択肢となるでしょう。
硬質ウレタンフォーム
ポリウレタン樹脂に発泡剤を加えて作る断熱材で、非常に高い断熱性能を誇ります。
工場で作られるボード状のものと、現場で液体を吹き付けて発泡させる吹付タイプがあります。
特に吹付タイプ(日本アクア社の「アクアフォーム」などが有名)は、細かい部分にも隙間なく充填でき、自己接着性によって気密性を高めやすいのが大きなメリットです。
耐久性や吸音効果もあります。
ただし、注意すべきデメリットとして、火災時に燃えるとシアン系の有毒ガスが発生する可能性があること、そしてシロアリに弱いことが挙げられます。
そのため、防火対策や防蟻処理が重要になります。
価格は比較的高めですが、その高い断熱性と気密性から、近年人気が高まっています。
フェノールフォーム(ネオマフォーム)
フェノール樹脂を主原料とする断熱材で、旭化成建材の「ネオマフォーム」が代表的な製品です。
現行の住宅用断熱材の中ではトップクラスの断熱性能を誇ります。
熱伝導率が極めて低いため、他の断熱材より薄い厚みで同等以上の性能を発揮でき、壁の厚みを抑えたい都市部の住宅などにも適しています。
また、耐熱性が高く、燃えにくい上に火災時の有毒ガス発生も少ないのが大きなメリットです。経年による性能劣化も少ないとされています。
最大のデメリットは、価格が非常に高いことです。
初期費用はかかりますが、最高の断熱性能を追求したい場合には最適な選択肢と言えるでしょう。
ただし、素材が硬くてもろいため、衝撃で割れやすい点には施工時の注意が必要です。
押出法ポリスチレンフォーム(スタイロフォーム)
ポリスチレンを主原料とし、発泡させながら押し出してボード状に成形する断熱材です。
デュポン・スタイロ社の「スタイロフォーム」が有名で、製品名で呼ばれることも多くあります。
最大の特徴は、水や湿気に非常に強いことです。
独立した気泡構造のため吸水率が極めて低く、水中や土中など湿度の高い場所でも断熱性能がほとんど低下しません。
そのため、住宅の基礎断熱に最もよく使われる断熱材です。
軽量でカッターでも簡単に切断できるため、加工・施工がしやすいのもメリットです。
一方で、デメリットは熱に弱いことです。70~80℃程度で変形が始まるため、高温になる場所での使用には適していません。
また、多くのプラスチック系断熱材と同様に、シロアリ対策も考慮する必要があります。
ビーズ法ポリスチレンフォーム(EPS)
一般的に「発泡スチロール」として知られている素材です。
ポリスチレンの小さなビーズを発泡させて金型の中で成形します。押出法ポリスチレンフォームと同じ原料ですが、製法が異なります。
こちらも軽量で水に強く、比較的安価なのがメリットです。
衝撃を吸収する能力が高く、加工もしやすいです。
断熱性能は押出法ポリスチレンフォームに比べるとやや劣りますが、コストを抑えたい場合の外張り断熱などで採用されることがあります。
デメリットは、押出法と同様に熱に弱い点です。
また、ビーズの集合体であるため、製品によってはビーズ間にわずかな隙間が生じ、吸水することがあります。
製造メーカーによって品質の差が出やすいとも言われており、信頼できる製品を選ぶことが大切です。
セルロースファイバー
古新聞などの古紙をリサイクルして作られる、綿状の断熱材です。
専門の機械を使い、壁の中や屋根裏に隙間なく吹き込んで施工します。
木質繊維である紙が持つ特性から、湿気を吸ったり吐いたりする高い調湿性を備えているのが最大の特徴です。
これにより、壁の内部結露を防ぎ、建物の耐久性を高める効果が期待できます。
また、高密度に充填するため、防音・吸音性能が非常に高く、静かな室内環境を作りたい場合に最適です。
ホウ酸が添加されているため、防虫(ゴキブリやシロアリ対策)や防カビ効果、難燃性も備えています。
デメリットは、専門の吹込み工法が必要なため施工コストが割高になることと、対応できる施工業者が限られる点です。
羊毛(ウールブレス)
その名の通り、羊の毛を原料とした断熱材です。
衣類にも使われるウールが持つ優れた機能性を住宅にも活かしています。
セルロースファイバーを上回るほどの非常に高い調湿性を持ち、室内の湿度を快適に保ちます。
また、化学物質を吸着・分解して空気を浄化する作用があるとも言われています。
もちろん、冬は暖かく夏は涼しい断熱効果も期待でき、防虫処理が施されているため害虫の心配も少ないです。
まさに「呼吸する断熱材」と言えるでしょう。
最大のデメリットは、価格が非常に高いことです。
天然素材であることや加工の手間から、他の断熱材と比べて高価になります。
また、取り扱っている工務店がまだ少ないため、採用したくてもできないケースがあります。
【目的別】新築・注文住宅におすすめの断熱材
ここまで解説した特徴を踏まえ、「結局、自分の場合はどれを選べばいいの?」という疑問に答えます。
ここでは代表的な3つの目的別に、おすすめの断熱材をご紹介します。
性能を最重視するなら「フェノールフォーム」
「初期費用はかかっても、とにかく暖かく涼しい、最高性能の家に住みたい」という方には、フェノールフォーム(ネオマフォーム)が最適です。
業界トップクラスの断熱性能は、冬の寒さが厳しい地域や、将来にわたって高い住宅性能を維持したいと考える方に大きな満足感をもたらしてくれるでしょう。
薄くても高い性能を発揮できるため、デザイン性の高い住宅にも適しています。
価格と性能のバランスなら「グラスウール」
「予算は抑えたいけれど、断熱性能で後悔はしたくない」という、コストパフォーマンスを重視する方にはグラスウールが最も有力な選択肢です。
圧倒的な普及率と安価な材料費は、住宅建築の総コストを抑える上で大きなメリットになります。
ただし、その性能は施工品質に大きく左右されるため、必ず信頼できる高い技術力を持った施工会社を選ぶことが絶対条件となります。
防音・調湿性も求めるなら「セルロースファイバー」
「断熱性能はもちろん、室内の空気環境や静かさにもこだわりたい」という方にはセルロースファイバーをおすすめします。
その高い調湿性は、梅雨時期のジメジメや冬の過乾燥を和らげ、一年を通して快適な湿度環境を保ちます。
また、優れた防音性能は、幹線道路沿いの家や、シアタールームを作りたいといった要望にも応えてくれます。
健康や快適性を多角的に追求したい方にぴったりの断熱材です。
知っておきたい断熱材の基礎知識
最後に、断熱材を選ぶ上で知っておくと役立つ基礎知識を2つご紹介します。
断熱材の役割と住宅への効果
そもそも、なぜ断熱材が重要なのでしょうか。
その役割は、単に「家を暖かくする」だけではありません。
優れた断熱は、私たちの暮らしに主に3つの良い効果をもたらします。
- 快適性の向上
外の暑さや寒さが室内に伝わりにくくなるため、「夏は涼しく、冬は暖かい」室内環境を保てます。
部屋ごとの温度差も少なくなり、どこにいても快適に過ごせます。 - 省エネ(光熱費の節約)
断熱性が高いと、冷暖房の効率が格段にアップします。
エアコンがすぐに効き、一度快適な温度になればそれを維持しやすくなるため、無駄なエネルギー消費を削減。
結果として月々の光熱費を大きく節約できます。 - 健康の維持
冬場の暖かいリビングと寒い脱衣所・浴室との急激な温度差は、体に大きな負担をかけ「ヒートショック」を引き起こす原因となります。
家全体の温度差を小さくする高断熱住宅は、ヒートショックのリスクを低減し、家族の健康を守ることに繋がります。
断熱工法の種類 充填断熱・外張り断熱・付加断熱
断熱材の性能を最大限に引き出すには、その取り付け方である「断熱工法」も重要です。
元記事でも詳しく解説されている通り、主に3つの種類があります。
- 充填断熱(内断熱)
柱と柱の間など、構造躯体の内側に断熱材を充填する工法です。
壁の厚みの中に断熱材が収まるため、設計の自由度が高いのが特徴です。
グラスウールやセルロースファイバー、吹付硬質ウレタンフォームなどがこの工法で施工されます。
コストを抑えやすく、日本の木造住宅で最も広く採用されていますが、柱や梁の部分が断熱されないため、熱が逃げる「熱橋(ヒートブリッジ)」ができやすい点には注意が必要です。 - 外張り断熱
柱などの構造躯体の外側から、家全体をボード状の断熱材ですっぽりと覆う工法です。
構造躯体が熱橋になりにくく、家全体の気密性を高めやすいのがメリットです。
フェノールフォームや押出法ポリスチレンフォームなど、硬いボード状の断熱材が使われます。
ただし、壁が厚くなる、コストが割高になる、使用できる外壁材が限られるといったデメリットもあります。 - 付加断熱
充填断熱と外張り断熱の両方を組み合わせた、最も断熱性能が高い工法です。
それぞれのデメリットを補い合うことで、非常に高い断熱性を実現します。
HEAT20のG3グレードなど、最高レベルの断熱性を目指す高性能住宅で採用されますが、その分コストは最も高くなります。
断熱材の種類に関するよくある質問
ここでは、断熱材選びで多くの方が抱く素朴な疑問にお答えします。
Q. 結局、最強の断熱材はどれですか?
- もし「断熱性能」という一点だけで判断するなら、フェノールフォームが現状で最強の断熱材と言えるでしょう。
しかし、価格、耐火性、調湿性、防音性など、何を重視するかによって「最強」の定義は変わります。例えば、コストパフォーマンスではグラスウールが、調湿性や防音性ではセルロースファイバーが非常に優れています。
ご自身の家づくりで何を一番大切にしたいかを考えることが、あなたにとっての「最強の断熱材」を見つける近道です。
Q. 主要な断熱材メーカーと製品の違いはありますか?
- はい、あります。
例えば同じグラスウールでも、旭ファイバーグラス社の「アクリア」シリーズや、マグ・イゾベール社の「イゾベール」シリーズなど、メーカーごとに様々な製品ブランドが存在します。
特に近年は、従来のグラスウールよりも繊維を細くして断熱性能を高めた「高性能グラスウール」が主流になっています。
同じ種類の断熱材でも、密度や製品グレードによって熱伝導率が異なりますので、工務店から提案された際には、どのメーカーのどの製品(グレード)が使われるのかまで確認することをおすすめします。
Q. リフォームで断熱材を追加・交換できますか?
- はい、可能です。
ただし、施工できる範囲や方法は、家の構造や状態によって大きく異なります。
壁の断熱リフォームは、一度壁を剥がす必要があるため大規模な工事になりがちですが、床下や天井裏(屋根裏)は比較的簡単に断熱材を追加・交換できる場合があります。
特に天井裏に断熱材を敷き込むリフォームは、夏の暑さ対策に高い効果を発揮し、コストパフォーマンスも良いため人気があります。
まずはリフォーム専門の会社や工務店に自宅の状態を診断してもらうことから始めましょう。
まとめ
今回は、住宅に使われる断熱材の種類について、それぞれのメリット・デメリットから、後悔しないための選び方のポイントまでを詳しく解説しました。
- 断熱材を選ぶ際は、まず比較一覧表で全体像を把握する
- 「性能」「コスト」「場所」の3つのポイントで自分に合うものを絞り込む
- 各断熱材のメリットだけでなく、デメリットも正しく理解することが重要
- 断熱性能は、断熱材の種類だけでなく「工法」や「施工技術」も大きく影響する
断熱材は、快適で健康的、そして経済的な暮らしを末永く支える、家づくりの縁の下の力持ちです。
この記事で得た知識をもとに、ご自身の家づくりで何を優先したいのかを整理し、建築を依頼するハウスメーカーや工務店の担当者としっかり話し合ってみてください。
もし、広島・東広島・福山エリアで、断熱性能にこだわった理想の注文住宅を建てたいとお考えなら、ぜひ私たち山根木材にご相談ください。 累積1万棟を超える家づくりの実績を元に、お客様一人ひとりのライフスタイルとご希望に寄り添い、最適な断熱材と工法をご提案いたします。プロの視点から、あなたの家づくりを全力でサポートしますので、下記のお問い合わせフォームからお気軽にご連絡ください。
お問い合わせ・資料請求は、下記お問い合わせフォームからお気軽にご連絡ください。