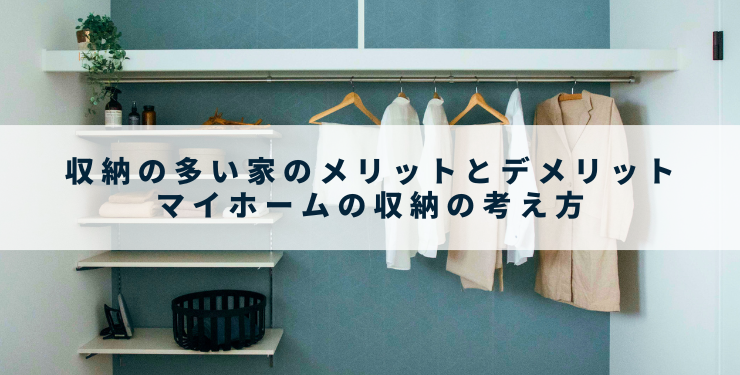木造と鉄骨のメリット・デメリット早わかり比較表

マイホームを考え始めたけれど、木造と鉄骨、どちらが良いのか分からない…そんなお悩みを解決するため、まずは両者の違いを一覧表で見ていきましょう。
コストや性能、設計の自由度など、家づくりで重要となる7つのポイントでメリット・デメリットを比較しました。
この表はあくまで一般的な傾向です。
それぞれの項目について、なぜこのような違いが生まれるのか、ここから詳しく解説していきます。
ご自身の家づくりで何を優先したいかを考えながら、読み進めてみてください。
そもそも木造・鉄骨造とは?構造の基本を解説

木造住宅の基本と主な工法
木造住宅とは、その名の通り、建物の主な構造部分(柱、梁、土台など)に木材を使用した家のことです。
日本の気候や風土に適していることから古くから採用されており、現在でも一戸建て住宅の主流となっています。木の持つ温かみや調湿性の高さが大きな魅力です。
木造住宅の工法で代表的なものに「木造軸組工法(在来工法)」と「木造枠組壁工法(ツーバイフォー工法)」があります。
木造軸組工法は、柱と梁を組み合わせて骨格を作る日本の伝統的な工法です。
柱の位置や長さを比較的自由に決められるため、間取りの自由度が高く、将来的なリフォームや増改築がしやすいという特長があります。
一方、ツーバイフォー工法は、2×4インチなどの規格化された木材で枠組みを作り、そこに構造用合板を張ってできた「面(パネル)」で家を支える工法です。
地震の揺れを6つの面全体で受け止めて分散させるため、耐震性が高いと言われています。
鉄骨住宅の基本と主な工法
鉄骨住宅とは、柱や梁などの骨組みに鉄や鋼の部材(スチール)を使用した家のことです。
S造(Steel)とも呼ばれます。
工場で生産された品質の安定した部材を使うため、職人の技術力に左右されにくく、均一な品質を保ちやすいのが特長です。
鉄骨住宅は、使用する鋼材の厚みによって主に2種類に分けられます。
一つは「軽量鉄骨造」です。厚さ6mm未満の鋼材を使い、個人の一戸建てやアパートなどで広く採用されています。
大手ハウスメーカーの多くがこの工法を得意としており、システム化された生産方式によって短い工期で建てられるのがメリットです。
もう一つは「重量鉄骨造」です。
厚さ6mm以上の頑丈な鋼材を使用し、高層マンションや商業ビルなどの大規模な建築物に用いられます。柱の本数を少なくできるため、広々とした空間や大きな窓を実現しやすいのが特長です。
【費用】木造と鉄骨のコストの違い

建築費用(坪単価)の目安は木造のほうが安い傾向
家づくりにおいて最も気になるのが建築費用です。
一般的に、建築費用(坪単価)は木造のほうが鉄骨造よりも安い傾向にあります。
木材は鉄骨に比べて材料そのものの価格が安く、また軽量で加工がしやすいため、現場での人件費や輸送コストも抑えることができます。
具体的な坪単価の目安としては、木造が50万円~、軽量鉄骨造が70万円~と言われることが多いですが、これはあくまで目安であり、仕様や設備、依頼する会社によって大きく変動します。
一方、鉄骨造は材料費が高いことに加え、部材が重いため基礎工事が大掛かりになりがちです。
特に、地盤が軟弱な土地に鉄骨住宅を建てる場合は、木造住宅以上に大規模な地盤改良工事が必要となり、100万円以上の追加費用がかかる可能性も考慮しておく必要があります。
ただし、木造であっても檜や欅といった高級な無垢材をふんだんに使ったり、複雑な設計にしたりすると、鉄骨造の費用を上回ることもあります。
将来のメンテナンス・リフォーム費用
家は建てて終わりではなく、長く快適に住み続けるためには定期的なメンテナンスが欠かせません。
このメンテナンス費用にも、構造による違いが現れます。
木造住宅で特に重要なのがシロアリ対策です。
木材を栄養源とするシロアリの被害を防ぐため、新築時に薬剤による防蟻処理を行いますが、その効果は永久ではありません。
一般的に5年~10年周期で再処理が必要となり、その都度費用が発生します。
一方、鉄骨住宅は主要な構造体が鉄骨なのでシロアリの直接的な被害は受けにくいですが、メンテナンスが不要というわけではありません。
鉄の最大の敵は「錆び」であり、定期的な防錆塗装のメンテナンスが重要です。
また、外壁に使われるパネルのつなぎ目を埋めるシーリング材は、木造・鉄骨を問わず経年劣化するため、10年~15年を目安に打ち替えが必要です。
さらに、固定資産税は一般的に資産価値が高いと評価される鉄骨住宅のほうが高くなる傾向があります。
長期的な視点でコストを考える際には、こうしたランニングコストも考慮に入れることが大切です。
【性能】耐震性・耐火性・断熱性の違い

地震や台風への強さ「耐震性」
地震大国である日本において、家の耐震性は最も重要な性能の一つです。
木造と鉄骨造、どちらが地震に強いのかは一概には言えませんが、揺れに対するアプローチが異なります。
木造住宅は、柱や梁などの接合部がある程度動くことで、建物全体がしなって地震のエネルギーを逃がす(いなす)という特性を持っています。
特に日本の伝統的な木造軸組工法は、この柔軟性を活かして倒壊を防いできました。
一方、鉄骨住宅は、鋼材の持つ高い強度と粘り強さ(靭性)によって、大きな揺れに力で抵抗し、建物の変形や倒壊を防ぐ(耐える)という考え方です。
頑丈な骨組みが、地震のエネルギーをしっかりと受け止めます。
ただし、現在の建築基準法では、どちらの構造であっても震度6強~7程度の大地震でも倒壊しないような厳しい基準が定められています。
そのため、構造の違いそのものよりも、国が定めた住宅性能表示制度の「耐震等級」がいくつであるかのほうが重要です。
耐震等級は1から3まであり、数字が大きいほど耐震性が高くなります。
家を建てる際は、構造の種類だけでなく、耐震等級を確認することが最も確実な方法です。
火災への強さと保険料に関わる「耐火性」
「木は燃えやすく、鉄は燃えにくい」というイメージから、耐火性は鉄骨住宅のほうが優れていると思われがちですが、実はそう単純ではありません。
鉄骨は確かに燃えませんが、熱に弱いという弱点があります。
火災時の高温(約550℃以上)にさらされると、鋼材は急激に柔らかくなり、強度を失ってぐにゃりと曲がってしまいます。
これにより、建物が一気に倒壊する危険性があります。
一方、木材は表面が燃えると炭化層を作ります。
この炭化層が内部への酸素の供給を妨げるため、木の中心部まで燃え進むのには時間がかかります。
太い柱や梁であれば、表面が燃えても構造体としての強度をしばらく保つことができるため、鉄骨造に比べて倒壊までの時間を稼ぎやすく、避難する時間を確保できるという側面があります。
また、住宅の耐火性能は、火災保険料にも大きく影響します。
木造住宅であっても、壁や天井の内部に石膏ボードを入れるなどの対策を施した「省令準耐火構造」の認定を受けることで、鉄骨造と同等の耐火性能があると見なされ、火災保険料を大幅に安く抑えることが可能です。
夏冬の快適さを左右する「断熱性・気密性」
一年を通して快適な室温を保つためには、断熱性と気密性が重要です。
この点においては、一般的に木造住宅のほうが有利と言われています。
木材は、鉄に比べて熱伝導率が非常に低いという特性があります。
熱伝導率が低いということは、外の暑さや寒さが室内に伝わりにくく、また室内の快適な温度が外に逃げにくいということです。
さらに、木は湿気を吸ったり吐いたりする「調湿性」も持っているため、日本の多湿な夏や乾燥する冬において、室内環境を快適に保つ手助けをしてくれます。
一方、鉄骨住宅で注意が必要なのが「ヒートブリッジ(熱橋)」という現象です。
これは、熱を伝えやすい鉄骨の骨組みが、外の熱気や冷気を室内まで運んでしまう現象のことです。
ヒートブリッジが起こると、断熱材の効果が十分に発揮されず、夏は暑く冬は寒く感じたり、壁内結露の原因になったりすることがあります。
そのため、鉄骨住宅では、外側から建物全体を断熱材ですっぽりと覆う「外張り断熱」を採用するなど、ヒートブリッジ対策をしっかりと行うことが快適な住環境の鍵となります。
【設計】間取り・デザインの自由度の違い

デザインやリフォームの自由度が高い木造
こだわりの詰まった注文住宅を建てたいと考える方にとって、設計の自由度は非常に重要なポイントです。
この点では、木造、特に木造軸組工法が優れていると言えます。
柱や梁で構造を支えるため、壁の配置に制約が少なく、斜めの壁や曲線の壁など、個性的なデザインにも柔軟に対応できます。
開口部も比較的自由に設けられるため、窓の大きさや形状にもこだわりを反映させやすいでしょう。
また、将来的なリフォームや増改築のしやすさも木造住宅の大きなメリットです。
家族構成の変化に合わせて間取りを変更したり、壁を抜いて部屋を広くしたりといった工事が、鉄骨造に比べて容易に行えます。
ただし、木造の中でもツーバイフォー工法は、壁(面)で建物を支える構造上、壁の撤去や大きな窓の設置には制限が出てくる場合があります。
工法によって自由度が異なる点は覚えておきましょう。
柱が少ない大空間を実現できる鉄骨造
鉄骨住宅の設計における最大の魅力は、柱の少ない広々とした大空間を実現できることです。
鉄骨は木材に比べて一本一本の部材が非常に高い強度を持っているため、少ない柱と梁で広いスペースを支えることができます。
特に、柱と梁を強固に接合する「ラーメン構造」を採用できる重量鉄骨造では、壁を取り払ったワンフロアのリビング・ダイニングや、壁一面の大きな窓、吹き抜け、ビルトインガレージなど、開放感あふれるダイナミックな空間設計が可能です。
軽量鉄骨造の場合は、木造のツーバイフォー工法のようにパネル化した部材を使うことが多く、設計の自由度はある程度規格化されています。
しかし、それでも木造軸組工法よりは柱の間隔(スパン)を広く取れるため、比較的すっきりとした空間を作りやすいのが特長です。
モダンで開放的な空間デザインを好む方にとっては、鉄骨造が有力な選択肢となるでしょう。
【結論】あなたにはどっち?木造・鉄骨住宅の選び方
コストを抑え、温かみのある家に住みたい人は木造
ここまで見てきたように、木造住宅には多くのメリットがあります。
もしあなたが以下の項目に当てはまるなら、木造住宅が向いている可能性が高いでしょう。
一つ目は、建築コストをできるだけ抑えたいと考えている人です。
一般的に木造は鉄骨造よりも坪単価が安く、初期費用を抑えることができます。
その分、内装や設備にお金をかけたり、将来のための貯蓄に回したりと、資金計画に余裕が生まれます。
二つ目は、木の香りやぬくもりなど、自然素材の持つ温かみのある空間が好きな人です。
木材が持つ調湿性や断熱性は、日本の気候に適しており、一年を通して快適な暮らしをサポートしてくれます。
経年変化によって風合いが増していくのも、木造住宅ならではの楽しみです。
三つ目は、設計士や工務店と相談しながら、こだわりのデザインや間取りを実現したい人です。
特に木造軸組工法は設計の自由度が高く、将来の家族構成の変化に合わせてリフォームしやすいのも大きな魅力です。
自分たちらしい、世界に一つだけの家を造りたいという想いを叶えやすい構造と言えるでしょう。
品質の安定した頑丈な家に住みたい人は鉄骨造
一方、鉄骨住宅にも木造にはない独自の魅力があります。
以下のような考えを持つ方には、鉄骨住宅がフィットするかもしれません。
一つ目は、品質の安定性と安心感を重視する人です。
鉄骨住宅の部材は、国が認定した工場で厳格な管理のもと生産されるため、品質にばらつきがありません。
職人の腕に左右されにくい工業化された工法は、安定した性能を求める方にとって大きな安心材料となります。
大手ハウスメーカーが提供する長期保証などの手厚いサポートを重視する方にもおすすめです。
二つ目は、柱の少ない、広々としたリビングや大開口の窓がある開放的な空間に憧れる人です。
鉄骨の強度を活かせば、木造では難しいダイナミックな空間設計が可能です。
モダンでスタイリッシュなデザインや、光と風をふんだんに取り入れる暮らしを理想としている方に最適です。
三つ目は、土地の資産価値をできるだけ長く維持したいと考えている人です。
鉄骨住宅は法定耐用年数が木造よりも長く設定されており、金融機関からの融資評価においても有利になる場合があります。
将来的に売却や賃貸に出す可能性を視野に入れている場合、資産価値が下がりにくい鉄骨住宅は合理的な選択と言えるでしょう。
【補足】混同しやすい鉄骨造・鉄筋コンクリート造との違い
戸建てに多い「軽量鉄骨造」とビルに使われる「重量鉄骨造」
家づくりを検討する中で「鉄骨造」という言葉が出てきたら、それが「軽量鉄骨造」なのか「重量鉄骨造」なのかを意識することが大切です。
この2つは、使われる鋼材の厚みが異なり、特徴や用途も大きく変わってきます。
軽量鉄骨造は、厚さ6mm未満の鋼材を使用して建てられます。
部材は工場で大量生産され、現場ではそれらをボルトで組み立てていくプレハブ工法が主流です。
そのため、品質が安定しており、工期が比較的短いというメリットがあります。
多くの大手ハウスメーカーが戸建て住宅で採用しているのがこの軽量鉄骨造であり、注文住宅における「鉄骨の家」は、ほとんどの場合こちらを指します。
一方、重量鉄骨造は、厚さ6mm以上の頑丈な鋼材を使用します。
柱と梁を溶接などで強固に接合する「ラーメン構造」により、骨組み自体が非常に強靭になるため、柱の本数を減らして巨大な空間を作ることが可能です。
その強度から、高層マンションや商業ビル、体育館といった大規模な建築物に採用されます。
戸建てで採用されることは稀ですが、災害に非常に強い堅牢な家や、店舗併用住宅などで用いられることがあります。
マンションに多い「鉄筋コンクリート(RC)造」との違い
鉄骨造(S造)と、家探しでよく耳にするもう一つの構造が鉄筋コンクリート造(RC造)です。
この二つの構造の違いを理解することは、特にマンションや賃貸物件を探す際に役立ちます。
両者は名前が似ていますが、全く異なる仕組みでできています。
鉄骨造は、これまで説明してきたように、鉄の柱と梁で「骨組み」を作る構造です。
それに対して鉄筋コンクリート造は、まず型枠の中に網目状に組んだ鉄筋を配置し、そこにドロドロのコンクリートを流し込んで固めて作ります。
「引っぱる力に強い鉄筋」と「圧縮される力に強いコンクリート」という、二つの材料の長所を一体化させることで、圧倒的な強度と耐久性を生み出します。
この特性から、分譲マンションや公共施設など、頑丈さが求められる建物に広く採用されています。
耐震性、耐火性、そして遮音性のいずれにおいても非常に高い性能を誇りますが、建物自体が極めて重くなるため、強固な地盤が必要となり、建築コストも木造や鉄骨造に比べて格段に高くなります。
まとめ
今回は、家づくりの第一歩として知っておきたい「木造」と「鉄骨造」の違いについて、費用、性能、設計など様々な角度から比較解説しました。
木造住宅は、コストを抑えやすく、木のぬくもりや高い設計自由度が魅力です。
一方の鉄骨住宅は、品質が安定しており、広々とした開放的な空間づくりが得意です。
どちらか一方が絶対的に優れているというわけではなく、それぞれに素晴らしい長所があります。
大切なのは、ご自身のライフスタイルや価値観、予算と照らし合わせ、「何を優先したいのか」を明確にすることです。
この記事が、あなたの理想のマイホームを実現するための、最適な構造選びの一助となれば幸いです。
お問い合わせ・資料請求は、下記お問い合わせフォームからお気軽にご連絡ください。