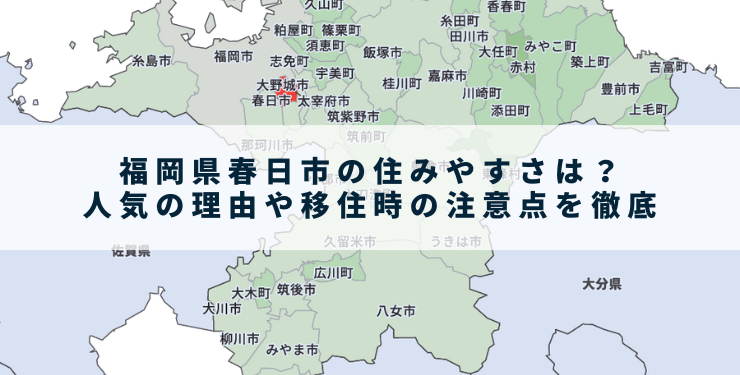これからマイホームを建てるなら、多くの方が「できるだけ長く、快適に、そして安全に暮らしたい」と願うはずです。
そんな思いに応える選択肢の一つが「長期優良住宅」です。
長期優良住宅とは、その名の通り、国が定めた厳しい基準をクリアし「長期にわたって良好な状態で住み続けられる」と認定された高品質な住宅のこと。
認定を受けると、税金の優遇や補助金といった金銭的なメリットが得られるため、ハウスメーカーから勧められている方も多いのではないでしょうか。
しかし、「メリットは聞くけど、具体的にいくらお得になるの?」「追加でかかる費用を考えると、本当に元が取れるの?」「デメリットはないの?」といった疑問や不安も尽きないはずです。
この記事では、そんなあなたの疑問を解消するために、長期優良住宅のメリット・デメリットから、誰もが気になる費用対効果まで、専門家の視点で徹底的に解説します。
この記事を読めば、長期優良住宅が「あなたの家族にとって本当に必要な選択なのか」が明確になり、自信を持って家づくりを進められるようになります。
長期優良住宅のメリット・デメリットは?採用すべきか一目でわかる比較表

まずは、長期優良住宅のメリットとデメリットの全体像を掴みましょう。
採用すべきか判断するために、重要なポイントを一覧表にまとめました。
このように、長期優良住宅は初期費用や手間がかかる一方で、それを上回るほどの金銭的・性能的なメリットを長期的に享受できる可能性があります。
では、このメリットとデメリットを天秤にかけたとき、本当に「お得」なのでしょうか。次の章で、具体的な金額をもとに詳しく検証していきましょう。
【結論】長期優良住宅にして本当にお得?費用対効果をシミュレーション

「結局、追加費用を払ってまで長期優良住宅にする価値はあるの?」これは、誰もが抱く最大の疑問です。
ここでは、具体的な金額をもとに、その費用対効果をシミュレーションしてみましょう。
追加費用30万円~は元が取れるか?損益分岐点を検証
長期優良住宅の認定を取得するためには、一般的な住宅に比べて追加で費用がかかります。
この追加費用は、主に「建築コストの増加分」と「認定申請費用」の2つです。
- 建築コストの増加分 高い性能基準を満たすための断熱材や構造材のグレードアップにより、建築コストが3%~5%程度上がると言われています。仮に2,000万円の建築費なら、60万円~100万円の上乗せです。
- 認定申請費用 設計事務所やハウスメーカーに支払う申請手続きの代行費用で、20万円~30万円程度が相場です。
これらを合計すると、総額で50万円~130万円程度の初期投資が必要になると考えられます。
では、この初期投資は回収できるのでしょうか。
結論から言うと、多くの場合、約10年~15年で元が取れる可能性が高いです。
例えば、住宅ローン控除の優遇額の増加分、固定資産税の減税期間延長による節税額、そして補助金(100万円)を合計すると、一般的な住宅に比べて10数年で150万円以上の経済的メリットが生まれるケースも少なくありません。
この時点で初期投資を上回り、それ以降は住めば住むほどお得になっていきます。
もちろん、これはあくまで一例であり、ご自身の年収や住宅の価格、利用する制度によって変動しますが、「長期的に見れば損はしない」というのが一つの結論と言えるでしょう。
【診断】長期優良住宅で得する人・損する人の特徴
シミュレーションの結果を踏まえ、あなたが長期優良住宅に向いているか診断してみましょう。
「得する人」と、場合によっては「必要ない・損する可能性のある人」のそれぞれの特徴をまとめました。
こんなあなたは「得する人」
- 一つの家に長く住み続けたいファミリー 長期優良住宅のメリットは、長く住むほど大きくなります。
20年、30年と世代を超えて住み続けることを考えているなら、税制優遇や光熱費の削減効果、メンテナンスのしやすさといった恩恵を最大限に享受でき、コストパフォーマンスは非常に高くなります。 - 住宅の性能や資産価値を重視する人 「とにかく安ければ良い」ではなく、耐震性や省エネ性といった住宅の基本的な性能を重視し、安心して暮らしたい方には最適です。
また、国のお墨付きがあることで、将来もし家を売却することになっても、一般住宅より有利な条件で売れる可能性が高く、資産として価値が落ちにくい点も大きな魅力です。 - 補助金や税金の優遇を最大限活用したい人 子育て世帯や若者夫婦向けの補助金制度の対象になっている場合、初期費用増の大部分を補助金でカバーできる可能性があります。
また、住宅ローン控除などの税制優遇をフル活用することで、手元に残るお金を増やしたいと考えている堅実な方にもおすすめです。
こんなあなたは「必要ない・損するかも」
- 数年での転勤や住み替えの可能性がある人 前述の通り、長期優良住宅の初期費用を回収するには10年以上の期間が必要です。
短期間で家を手放す可能性がある場合、メリットを十分に享受できず、単に「割高な家」になってしまう可能性があります。 - 初期費用を1円でも安く抑えたい人 何よりも初期費用を最優先に考え、予算に全く余裕がない場合は、長期優良住宅のコストアップが大きな負担になるかもしれません。
ただし、将来の光熱費や税金を考えると、目先のコストだけで判断するのは慎重になるべきです。 - 家のメンテナンスに手間やお金をかけたくない人 長期優良住宅は、定期的な点検とメンテナンス計画の報告が義務付けられています。
これを「面倒」「余計な出費」と感じる方には不向きかもしれません。
ただ、どんな家でも長く安全に住むためにはメンテナンスが不可欠であり、計画的に行うことで結果的に修繕費を抑えられるという側面もあります。
知らないと損!長期優良住宅の5つの金銭的メリット

長期優良住宅の最大の魅力は、なんといっても金銭的なメリットの多さです。
ここでは、特に重要な5つのメリットを具体的に解説します。
メリット1. 住宅ローン控除の優遇(最大455万円の控除)
住宅ローン控除(減税)は、年末の住宅ローン残高の0.7%が最大13年間、所得税や住民税から控除される制度です。
長期優良住宅は、この控除を受けられる借入限度額が一般住宅よりも高く設定されています。
2024年・2025年に入居する場合、一般住宅の限度額が原則3,000万円(2023年までに建築確認を受けた場合は4,000万円)であるのに対し、長期優良住宅の場合は5,000万円(子育て世帯・若者夫婦世帯の場合)となります。
仮に5,000万円のローンを組んだ場合、最大控除額は5,000万円 × 0.7% × 13年 = 455万円にもなります。一般住宅(3,000万円で計算)の最大控除額は約273万円なので、その差は歴然です。
高額な住宅を建てる方ほど、このメリットは大きくなります。
(参考: 国土交通省 住宅ローン減税)
メリット2. 固定資産税などの税金が減税される
マイホームを持つと毎年かかる「固定資産税」にも優遇があります。
新築住宅は本来、税額が2分の1に減額される期間が戸建てで3年間、マンションで5年間ですが、長期優良住宅の場合はこの期間が戸建てで5年間に、マンションで7年間に延長されます。
2年間の延長は、数十万円単位の節税につながる大きなメリットです。
さらに、家を購入した時に一度だけかかる税金にも優遇があります。
- 不動産取得税 課税標準からの控除額が、一般住宅の1,200万円から1,300万円に引き上げられます。
- 登録免許税 所有権保存登記や移転登記の税率が、一般住宅よりも引き下げられます。
これらの細かな優遇が積み重なり、家計の負担を軽くしてくれます。
メリット3. 【2025年最新】子育てグリーン住宅支援事業で最大100万円の補助金
省エネ性能の高い住宅の取得を支援する国の補助金制度も、大きなメリットです。
2025年度は「子育てグリーン住宅支援事業」が予定されており、長期優良住宅の認定を受けると、1戸あたり最大100万円の補助金が交付される見込みです。(2024年度の「子育てエコホーム支援事業」と同等水準の場合)
この補助金は、主にエネルギー価格高騰の影響を受けやすい子育て世帯・若者夫婦世帯を支援することを目的としています。
100万円という大きな金額は、認定取得のために増えた建築コストや申請費用を十分にカバーできる可能性があり、使わない手はありません。
補助金には予算があり、申請期間も限られているため、利用を検討する場合は早めにハウスメーカーや工務店に相談することが重要です。
(参考: 国土交通省 子育てグリーン住宅支援事業)
メリット4. 地震保険料が最大50%割引される
地震大国の日本において、地震保険への加入は必須とも言えます。
長期優良住宅は、その高い耐震性能に応じて、地震保険料が大幅に割り引かれます。
割引率は耐震性能によって異なり、以下のようになっています。
長期優良住宅は耐震等級3(消防署や警察署など防災の拠点となる建物と同レベル)を満たすことが多いため、保険料が半額になるケースがほとんどです。
地震保険は家を持つ限り継続して支払うものなので、長期的に見れば非常に大きな節約効果が期待できます。
メリット5. 住宅ローンの金利が引き下げられる(フラット35S)
住宅金融支援機構が提供する全期間固定金利の住宅ローン「フラット35」にも、長期優良住宅向けの優遇プランがあります。
「フラット35S(金利Aプラン)」を利用すると、当初10年間のローン金利が年0.25%引き下げられます。毎月の返済額が数千円変わるだけでも、総返済額で見れば数十万円の差になります。
低金利が続く現在でも、さらなる金利引き下げは家計にとって大きな助けとなるでしょう。
この優遇を受けるためにも、長期優良住宅の認定は強力な武器となります。
デメリットは費用だけじゃない!後悔しないための4つの注意点
多くのメリットがある一方で、長期優良住宅には無視できないデメリットや注意点も存在します。
契約してから「こんなはずじゃなかった」と後悔しないために、しっかりと確認しておきましょう。
デメリット1. 建築費用・申請費用が高くなる
最も大きなデメリットは、やはりコスト面です。
元記事にもあるように、高い品質基準を満たすために高性能な建材や設備が必要となり、一般的な住宅に比べて建築コストが3%~5%程度アップします。
さらに、認定を受けるための申請手続きにも費用がかかります。
各種図面の作成や計算、行政への申請代行などをハウスメーカーや設計事務所に依頼する必要があり、その費用は20万円~30万円程度が相場です。
この「申請費用が高い」と感じるかもしれませんが、専門的な書類作成の手間を考えると妥当な価格とも言えます。
これらを合わせると、初期費用が数十万円単位で増加することは覚悟しておく必要があります。
デメリット2. 建築期間が長くなる傾向
長期優良住宅は、設計段階からクリアすべき基準が多く、構造計算なども複雑になります。
また、行政への認定申請とその審査にも時間がかかるため、一般的な住宅よりも建築期間が数週間から1ヶ月程度長くなる傾向があります。
特に、お子様の入学や転勤など、入居時期が決まっている場合は注意が必要です。
家づくりの計画を立てる際は、この認定にかかる期間も考慮し、余裕を持ったスケジュールを組むことが大切です。
事前にハウスメーカーや工務店と、全体のスケジュール感をしっかり共有しておきましょう。
デメリット3. 定期的な点検・メンテナンスの義務と費用が発生する
長期優良住宅の認定を維持するためには、「維持保全計画」に基づき、定期的な点検と修繕を行い、その記録を保管する義務があります。
これは「建てて終わり」ではなく、きちんと手入れをしながら長く大切に住み続ける、という制度の趣旨に基づいています。
点検は少なくとも10年ごとに実施する必要があり、専門家(建築士など)に依頼した場合の費用は、1回あたり5万円~10万円が相場です。
このメンテナンスコストを負担に感じる方もいるかもしれません。
しかし、元記事の優れた指摘通り、これは「どのような住宅を建築しても発生する必要経費」と考えるべきです。
計画的な点検は、問題が小さいうちに発見し、将来の大規模な修繕を防ぐことにもつながり、結果的にトータルの維持費を抑える賢い選択と言えるでしょう。
デメリット4. 将来のリフォームに制約がかかる場合がある
長く住んでいると、家族構成の変化などでリフォームや増改築を考えたくなることもあるでしょう。
しかし、長期優良住宅の場合、認定を受けた際の計画から大幅に変更するようなリフォームは簡単にはできません。
例えば、耐震性に影響する柱や壁を撤去したり、大規模な増築を行ったりする場合は、再度、所管行政庁の変更認定を受ける必要があります。
もし無断でリフォームを行い、認定基準を満たさなくなると、最悪の場合、認定が取り消され、補助金や税金の優遇分を返還しなければならない可能性もあります。
将来的にリフォームの可能性がある場合は、どのような制約があるのか、事前に設計士やハウスメーカーに確認しておくことが重要です。
長期優良住宅の認定を受けるための条件とは?2025年の新基準も解説
長期優良住宅として認定されるには、国が定める複数の厳しい基準(性能要件)をすべてクリアする必要があります。
ここでは主要な条件を「なぜその基準が必要なのか」という目的とともに分かりやすく解説します。
耐震性(地震に強い家)
大規模な地震が発生しても、倒壊しにくいだけでなく、損傷を最小限に抑え、修復して住み続けられるレベルの強さが求められます。
具体的には、建築基準法で定められた耐震性の1.25倍の強さを持つ「耐震等級2」以上、または最高ランクの「耐震等級3」であることが基本的な条件です。
家族の命と財産を守るための、最も重要な基準の一つです。
省エネルギー性(夏涼しく冬暖かい家)
断熱性能を高め、冷暖房に頼りすぎなくても快適に過ごせる「省エネ性能」が求められます。
具体的には「断熱等性能等級5」かつ「一次エネルギー消費量等級6」という高いレベルが必要です。
これにより、月々の光熱費を抑えられるだけでなく、部屋ごとの温度差が少ない健康的な暮らしを実現できます。
ちなみに、2025年4月からは原則全ての新築住宅に省エネ基準への適合が義務化されます。
長期優良住宅はこれを先取りする高い基準であり、将来の資産価値維持においても有利に働くと言えるでしょう。
(参考: 国土交通省 建築物省エネ法のページ)
劣化対策(長持ちする家)
構造躯体(柱や梁など)が、数世代(75年~90年程度)にわたって大規模な改修工事を必要としないような対策が求められます。
木造住宅であれば、シロアリ対策や木材の腐食対策などがこれにあたります。
住宅が長持ちするための、縁の下の力持ちとも言える基準です。
維持管理・更新の容易性(メンテナンスしやすい家)
水道管やガス管、排水管といった設備は、建物の構造部分よりも寿命が短いものです。
そのため、これらの配管の点検や清掃、交換が簡単にできるように設計されている必要があります。
点検口が適切に設けられているか、配管がコンクリートに埋め込まれていないか、などが評価されます。将来のメンテナンス費用を抑えるための重要な基準です。
その他の基準(住戸面積・居住環境・維持保全計画)
上記の他に、良好な居住環境を確保するための住戸面積の基準(戸建ての場合75㎡以上など)や、地域の景観と調和を図る居住環境への配慮、そして前述した維持保全計画が適切に策定されていることも認定の条件となります。
これらすべてを満たして初めて、長期優良住宅として認められるのです。
長期優良住宅の申請プロセスと費用相場
「実際に長期優良住宅を建てたい!」と思ったら、どのような手続きが必要なのでしょうか。
ここでは申請の流れと費用について解説します。
申請のタイミングと流れ【あとからの申請は不可】
長期優良住宅の認定申請で最も重要な注意点は、必ず「住宅の着工前」に申請を完了させなければならないということです。
建て始めてから「やっぱり長期優良住宅にしたい」と思っても、あとからの申請は原則として認められません。
一般的な申請の流れは以下の4ステップです。
- ハウスメーカー・工務店へ相談 家づくりの計画段階で、長期優良住宅を希望する旨をはっきりと伝えます。
- 設計・認定申請書類の作成 工務店や設計事務所が、認定基準を満たす設計を行い、膨大な申請書類を作成します。
- 所管行政庁へ申請 建築主(あなた)が、所管行政庁(市区町村など)に認定を申請します。実際の手続きはハウスメーカー等が代行してくれることがほとんどです。
- 認定通知書の交付 審査を経て基準に適合していると認められれば、「認定通知書」が交付されます。これを受け取ってから、住宅の工事がスタートします。
申請費用の内訳と相場
前述の通り、認定申請にかかる費用は総額で20万円~30万円程度が相場です。
この費用の内訳は、主に以下の2つで構成されています。
- 登録住宅性能評価機関への申請費用 設計内容が基準に適合しているか、事前に専門機関に技術的な審査を依頼するための費用です。10万円前後かかることが多いです。
- ハウスメーカー・工務店への代行手数料 申請書類の作成や行政とのやり取りを代行してもらうための手数料です。これも10万円前後が一般的です。
費用は依頼する会社や住宅の規模によって異なります。
契約前に、申請費用の総額と内訳について、しっかりと見積もりを確認しておくことが大切です。
長期優良住宅に関するよくある質問(Q&A)
最後に、長期優良住宅について多くの方が抱く細かな疑問にお答えします。
Q1. 自分の家が長期優良住宅か確認する方法は?
ご自宅や購入を検討している中古物件が長期優良住宅かどうかを確認するには、いくつかの方法があります。
まずは、売主や不動産会社に「長期優良住宅建築等計画」の認定通知書があるか尋ねてみましょう。
この書類が、認定を受けている最も確実な証拠です。もし見当たらない場合は、建築したハウスメーカーに問い合わせたり、法務局で「住宅性能評価書」の有無を調べることでも確認できる場合があります。
中古物件の場合は、認定の有無が資産価値に大きく関わるため、必ず契約前に確認することが重要です。
Q2. ZEH(ゼッチ)住宅との違いは?
ZEH(ゼッチ)住宅も省エネ性能の高い住宅として注目されていますが、目的が少し異なります。
簡単に言うと、ZEHが「使うエネルギーと創るエネルギーの収支をゼロ以下にする」という省エネ性能に特化した住宅であるのに対し、長期優良住宅は省エネ性に加え、耐震性や耐久性、メンテナンス性など「住宅全体の品質を総合的に高め、長持ちさせる」ことを目的としています。
どちらも優れた住宅ですが、重視するポイントが異なります。
もちろん、両方の基準を満たす、さらに高性能な住宅を建てることも可能です。
Q3. 中古や建売、マンションでも認定されますか?
はい、認定されます。建売住宅や分譲マンションでも、新築時に長期優良住宅の認定を受けている物件は数多くあります。
購入を検討する際は、広告やパンフレットに「長期優良住宅認定」の記載があるかチェックしてみてください。 一方、中古住宅の場合は、注意が必要です。購入した人が、後から新たに認定を取得することはできません。
ただし、元々認定を受けていた物件であれば、売主から買主へその「地位」を引き継ぐことができます。その際は、維持保全計画などを引き継ぐための変更認定手続きが必要になるため、不動産会社や専門家によく相談しましょう。
まとめ
今回は、長期優良住宅のメリット・デメリットから、気になる費用対効果までを詳しく解説しました。
長期優良住宅は、初期費用として数十万円のコストがかかるものの、税制優遇や補助金、将来の光熱費削減などを考慮すると、10年~15年という期間で十分に元が取れる可能性が高い、非常に賢い選択肢です。
特に、
- これから一つの家に長く住み続けたい
- 目先のコストだけでなく、住宅の性能や資産価値も大切にしたい
- 地震や災害に備え、安心して暮らせる家が欲しい
このように考えている方にとって、長期優良住宅はまさに理想の住まいと言えるでしょう。
もちろん、最終的に採用するかどうかは、あなたのライフプランや価値観、そして予算次第です。この記事で得た知識をもとに、ご家族でじっくりと話し合い、ハウスメーカーや工務店の担当者にも相談しながら、後悔のない家づくりを進めてください。
広島・東広島・福山エリアで長期優良住宅をご検討なら、私たち山根木材にぜひご相談ください。お客様の暮らしに長く寄り添うライフパートナーとして、ご家族の思いを形にする最適なプランをご提案します。
お問い合わせ・資料請求は、下記お問い合わせフォームからお気軽にご連絡ください。