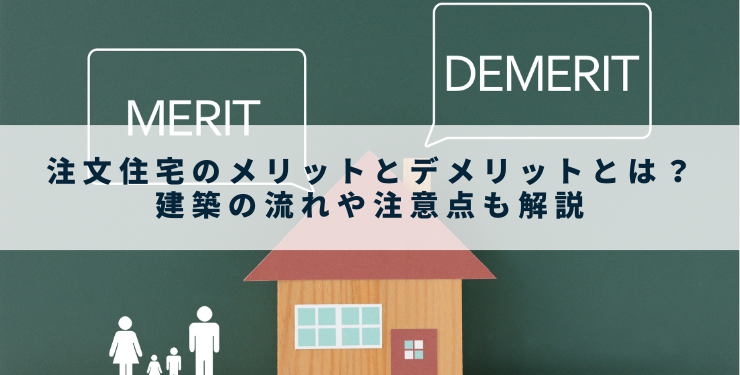「自分たちの理想通りのマイホームを建てたい」と考えたとき、多くの方が憧れるのが注文住宅です。
家族のこだわりを形にし、世界に一つだけのデザインを実現できるのは、注文住宅ならではの大きな魅力と言えるでしょう。
しかし、その一方で費用や手間、完成までの期間など、知っておくべきデメリットや注意点も存在します。
マイホーム購入は一生に一度の大きな買い物だからこそ、メリットとデメリットの両方を正しく理解し、ご自身の家族に本当に合った選択をすることが重要です。
この記事では、これから家づくりを始める初心者の方に向けて、以下の点を分かりやすく解説します。
- 注文住宅の具体的なメリットとデメリット
- 建売住宅との決定的な違い
- 後悔しないためのポイントと対策
- 費用相場や家が建つまでの流れ
この記事を読めば、注文住宅の全体像が掴め、ご家族にとって最良の選択をするための一歩を踏み出せるはずです。
一目でわかる注文住宅と建売住宅のメリット・デメリット比較表

まずは、注文住宅と建売住宅の主な違いを比較表で見てみましょう。
それぞれの特徴を大まかに把握するのに役立ちます。
| 比較項目 | 注文住宅 | 建売住宅 |
| 設計の自由度 | ◎ 非常に高い | △ 低い(変更不可が基本) |
| 費用 | △ 高くなる傾向 | ◯ 比較的安い |
| 入居までの期間 | △ 長い(8ヶ月~) | ◎ 短い(最短1ヶ月未満も) |
| 手間 | △ かかる | ◎ 少ない |
| 品質の安定性 | ◯ 建築過程を確認できる | ◯ 完成品を確認できる |
このように、自由度を最優先するなら注文住宅、費用やスピードを重視するなら建売住宅が主な選択肢となります。
どちらが良い・悪いということではなく、ご自身の価値観やライフプランに合わせて選ぶことが大切です。
注文住宅のメリット5選

注文住宅には、建売住宅にはない多くの魅力があります。
ここでは代表的な5つのメリットをご紹介します。
間取り・デザイン・外観の完全な自由設計
注文住宅最大のメリットは、何と言っても設計の自由度が非常に高いことです。
「リビングは日当たりの良い南向きに広く取りたい」「夫婦それぞれの書斎が欲しい」「子供の成長に合わせて将来間仕切りできる子供部屋にしたい」といった、家族一人ひとりの希望を間取りに反映できます。
また、ペットが快適に過ごせる動線や、趣味の自転車を飾れるビルトインガレージ、友人たちと集まれる広いウッドデッキなど、ライフスタイルに合わせた特別な空間づくりも可能です。
外観デザインや素材も自由に選べるため、まさに「世界に一つだけの我が家」を実現できるのは、注文住宅ならではの醍醐味と言えるでしょう。
常識にとらわれない、家族だけの理想の住まいを形にできます。
キッチン・風呂・壁紙まで選べる住宅設備と建材
間取りだけでなく、キッチンやお風呂、トイレといった住宅設備から、壁紙、床材、ドアノブといった細かな建材に至るまで、自分たちの好みや予算に合わせて自由に選べるのも大きなメリットです。
例えば、「料理が好きだからキッチンは最新のIHコンロと食洗機を導入したい」「お風呂はリラックスできる大型のユニットバスにしたい」「子供部屋の壁紙はアレルギー対策の自然素材を使いたい」など、こだわりたい部分にしっかりと予算をかけることができます。
逆に、寝室や収納スペースなど「あまり人に見られない場所は標準仕様でコストを抑える」といったメリハリのある予算配分ができるのも注文住宅の賢い建て方です。
数多くの選択肢の中から、家族で話し合いながら一つひとつ選んでいくプロセスは大変ですが、その分、完成した我が家への愛着も一層深まります。
希望エリアでの土地探しから家づくりができる
建売住宅は土地と建物がセットで販売されるため、気に入った建物があっても立地が希望と合わないケースが少なくありません。
一方、注文住宅は先に土地を探してから、その土地に合わせて家を建てるのが一般的です。
そのため、「子供の学区を変えたくない」「夫婦それぞれの職場への通勤に便利な場所が良い」「自然豊かな郊外でのびのびと暮らしたい」といった、家族のライフプランに合わせた希望のエリアで家づくりを進められます。
土地の形状が少し特殊な「変形地」であっても、その土地の個性を最大限に活かした設計プランの提案を受けられるのも注文住宅の強みです。
住みたい場所を優先できることは、長年にわたる暮らしの満足度を大きく左右する重要なポイントになります。
建築過程を確認できる透明性と安心感
建売住宅はすでに完成した状態で購入するため、壁の内側や基礎部分など、見えない部分の構造がどうなっているかを確認することは困難です。
その点、注文住宅は基礎工事から骨組みの組み立て、内装工事に至るまで、家が建つまでの全ての工程を自分の目で確認できます。
工事の進捗状況を見守ることで、職人さんたちとの信頼関係が生まれ、家づくりに参加している実感も湧いてきます。
特に、家の強度や断熱性能に直結する基礎や構造躯体、断熱材の施工状況などを直接チェックできるのは、大きな安心材料となるでしょう。
希望すれば第三者機関による施工品質チェック(ホームインスペクション)を依頼することも可能で、品質に対する透明性が高い点も大きなメリットです。
高気密・高断熱など住宅性能を追求できる
長く快適に、そして経済的に暮らすためには、家の「性能」が非常に重要です。
注文住宅では、断熱材の種類や厚み、窓のサッシ(複層ガラスやトリプルガラス)、換気システムなどを自由に選ぶことで、住宅の断熱性・気密性を高めることができます。
高気密・高断熱の家は、外気の影響を受けにくいため「夏は涼しく、冬は暖かい」という快適な室内環境を保ちやすく、冷暖房の効率が上がることで光熱費を大幅に削減できるメリットがあります。
また、国の定める省エネルギー基準を満たすZEH(ゼッチ)仕様の住宅を建てることも可能です。
暮らしの快適性だけでなく、環境への配慮や長期的な資産価値という観点からも、住宅性能を自分たちで追求できるのは注文住宅の大きな魅力です。
後悔しないための注文住宅のデメリット4選と対策

魅力的なメリットが多い注文住宅ですが、契約後に「こんなはずじゃなかった」と後悔しないために、知っておくべきデメリットと、その対策を解説します。
建売より割高な費用と予算オーバーのリスク
注文住宅は、一軒ごとに設計し、資材も個別に手配するため、同じ規模・仕様の建売住宅に比べてトータルコストが割高になる傾向があります。
また、自由度が高いがゆえに、打ち合わせを進める中で「キッチンをグレードアップしたい」「床材は無垢材にしたい」といった希望が増え、当初の予算を大幅に超えてしまう「予算オーバー」のリスクも常に伴います。
【対策】
まず、家づくりを始める前に「絶対に譲れないこだわり」と「妥協できる部分」の優先順位を家族で明確に話し合っておくことが最も重要です。
グレードの選択で迷ったときに、この優先順位が判断の基準になります。
また、建物本体の工事費以外にも、屋外の給排水工事や外構工事などの「付帯工事費」や、登記費用、各種税金などの「諸経費」も必要です。
これらを考慮した総額での資金計画を最初にしっかりと立て、予算を超えないように自己管理することが後悔しないための鍵となります。
入居まで最短8ヶ月以上かかる長い期間
建売住宅であれば、契約から引き渡しまで1ヶ月程度で済むこともありますが、注文住宅はゼロから家づくりを始めるため、入居までに長い時間がかかります。
土地探しから始める場合は、土地が決まるまでの期間も加わるため、一般的には相談から入居まで1年から1年半程度を見ておく必要があります。
お子様の入学や転勤など、入居したい時期が決まっている場合は特に注意が必要です。
【対策】
まずは「いつまでに入居したいか」という希望日から逆算して、余裕を持ったスケジュールを組むことが大切です。
特に、詳細なプランを決める打ち合わせ期間は、家族の意見がまとまらずに長引いてしまうことも少なくありません。
現時点での家族の希望がまとまっていない場合は、検討期間も計算に入れて、さらに余裕を持つと安心です。
工事が始まってからも、天候不順などで工期が延長する可能性も考慮しておきましょう。
土地探しや設計で膨大な打ち合わせの手間がかかる
注文住宅は、土地探し、資金計画、建築会社の選定、間取りや内外装の設計、設備の仕様決めなど、決断しなければならない項目が非常に多く、膨大な手間と時間がかかります。
特に共働きの夫婦の場合、休日のたびに打ち合わせに時間を取られ、精神的に疲れてしまうケースも少なくありません。
家族間でも意見が食い違い、話し合いがスムーズに進まないこともあります。
【対策】
家づくりを始める前に、家族で「どんな暮らしがしたいか」という理想のイメージを共有しておくことが大切です。
雑誌の切り抜きやSNSで見つけた好みの写真をまとめておくと、建築会社の担当者にもイメージが伝わりやすくなります。
また、何でも相談できる信頼関係を築ける担当者を見つけることも、打ち合わせの手間を軽減する上で非常に重要です。
家づくりのプロセスそのものを楽しむくらいの気持ちで臨むことが、後悔しないためのコツかもしれません。
完成形がイメージしにくい不安
建売住宅は実際の建物を見て購入を決められますが、注文住宅は図面や模型、サンプルなどから完成形を想像するしかありません。
そのため、「実際に建ってみたら、思っていたよりリビングが狭く感じた」「壁紙の色がイメージと違った」など、完成後に想像とのギャップを感じてしまうリスクがあります。
特に、日当たりや風通し、隣家との距離感などは、図面だけでは把握しにくい部分です。
【対策】
最近では、コンピューターグラフィックスを使った3DパースやVR(バーチャルリアリティ)で、完成後の室内を立体的に体験できる住宅会社が増えています。
こうしたツールを積極的に活用し、家具を置いた際の広さや生活動線などをリアルに確認しましょう。
また、建築を依頼する会社が建てた他の物件(完成見学会など)をできるだけ多く見学し、その会社がつくる家の雰囲気やスケール感を肌で感じておくことも、イメージのズレを防ぐのに有効です。
そもそも注文住宅とは?建売住宅との3つの決定的違い
ここで改めて、「注文住宅」とは何か、建売住宅と何が決定的に違うのかを3つのポイントで整理しておきましょう。
フルオーダーから規格型まで選べる自由度の違い
注文住宅と一言で言っても、実は設計の自由度によっていくつかの種類に分かれます。
これが建売住宅との最も大きな違いです。
| 種類 | 間取り | 設備 | 特徴 |
| フルオーダー住宅 | 自由 | 自由 | 最も自由度が高く、 理想を追求できるが、 コストや期間がかかりやすい。 |
| セミオーダー住宅 | 自由 | 一部選択肢から選ぶ | 基本的な仕様は決まっており、 間取りや一部の設備を選べる。 自由度とコストのバランスが良い。 |
| 規格住宅 | 選択肢から選ぶ | 選択肢から選ぶ | 予め用意されたプランから選ぶ形式。 自由度は低いが、品質が安定しコストを抑えやすい。 |
このように、注文住宅には幅広い選択肢があり、予算やこだわりに合わせて自由度を調整できるのが特徴です。
一方、建売住宅は完成済みの住宅を購入するため、基本的に間取りや仕様の変更はできません。
土地と建物を別々に考える費用の違い
費用の考え方も大きく異なります。
建売住宅は土地と建物がセットで「総額〇〇円」として販売されるため、価格が明快で資金計画を立てやすいのが特徴です。
一方、注文住宅は「土地代」と「建物代(建築工事費)」を別々に考えて契約するのが一般的です。
そのため、土地の購入費用と建物の建築費用、それぞれのローン手続きや諸経費が必要になります。
全体の総額が見えにくい面もありますが、土地と建物のそれぞれに予算を配分できるという見方もできます。
契約から入居までの期間の違い
前述の通り、入居までの期間も全く違います。
建売住宅はすでに完成しているか、建築中であっても仕様が決まっているため、契約後は住宅ローンの手続きなどが済めばすぐに入居できます。
対して注文住宅は、建築会社と「工事請負契約」を結んでから設計の打ち合わせが始まり、その後工事に着手します。
この設計と建築の期間が必要なため、どうしても入居までの期間が長くなります。
この時間差が、それぞれのライフプランにどう影響するかを考えることが重要です。
あなたはどっち?注文住宅と建売住宅が向いている人の特徴
メリット・デメリットを踏まえた上で、あなたがどちらのタイプに向いているか、具体的な人物像でチェックしてみましょう。
注文住宅がおすすめな人
- 家づくりそのものを楽しみたい、こだわりを実現したい人
- 家族のライフスタイルに合わせた特別な間取りや動線が必要な人
- アレルギー対策などで、建材や素材を自分で選びたい人
- 希望の学区や通勤に便利な場所など、住みたいエリアが決まっている人
- 入居時期を急いでおらず、家づくりに時間をかけられる人
建売住宅がおすすめな人
- 子供の入学に合わせてなど、できるだけ早く新居に引っ越したい人
- 実際の建物や日当たり、周辺環境などを確認してから購入を決めたい人
- 土地探しや設計の打ち合わせにかかる手間や時間を省きたい人
- 「土地+建物」の総額を明確にし、追加費用の心配なく資金計画を立てたい人
- 標準的で暮らしやすい、万人向けの家を求めている人
注文住宅の費用相場と家が建つまでの流れ
最後に、注文住宅を建てる際の具体的な費用相場と、相談から入居までの一般的な流れを確認しておきましょう。
全国平均は4,694万円|2023年度の土地付注文住宅費用相場
住宅金融支援機構が公表している「2023年度 フラット35利用者調査」によると、土地の購入を含めた注文住宅の全国平均費用(融資区分)は4,694.1万円でした。
また、エリア別に見ると以下のような結果になっています。
- 全国 4,694.1万円
- 首都圏 5,122.3万円
- 近畿圏 4,821.1万円
- 東海圏 4,639.9万円
やはり首都圏をはじめとする都市部では土地の価格が高いため、総額も高くなる傾向にあります。
これはあくまで平均値ですが、ご自身の資金計画を立てる上での一つの目安として参考にしてください。
(参考:住宅金融支援機構 2023年度 フラット35利用者調査 )
相談から引き渡しまで|家づくりの8ステップ
注文住宅の建築は、一般的に以下のようなステップで進んでいきます。
全体の流れを把握しておくと、計画が立てやすくなります。
- 情報収集・相談
まずは理想の暮らしをイメージし、インターネットや住宅展示場で情報収集。
気になる建築会社に相談します。 - 資金計画
自己資金や世帯年収から、無理のない予算を算出。
住宅ローンの事前審査もこの段階で行うとスムーズです。 - 土地探し
希望エリアや条件を不動産会社や建築会社に伝え、土地を探します。
(すでに土地がある場合は不要) - 建築会社の選定・契約
複数の会社からプランと見積もりを取り、比較検討。
依頼先を決定し「工事請負契約」を結びます。 - 詳細設計・プランニング
契約した会社と、間取りや内外装、設備などの詳細な仕様について打ち合わせを重ね、最終的な設計図を完成させます。 - 着工・建築工事
地鎮祭などを行い、いよいよ工事がスタート。
基礎工事から上棟、内装工事と進んでいきます。 - 完成・検査
建物が完成したら、契約通りに施工されているか、不具合がないかを施主と会社、第三者機関などが厳しくチェックします。 - 引き渡し・入居
住宅ローンの最終手続きや登記を済ませ、鍵を受け取ります。
いよいよ新しい暮らしのスタートです。
まとめ
今回は、注文住宅のメリット・デメリットから、建売住宅との違い、後悔しないためのポイントまでを詳しく解説しました。
注文住宅は、自由度が高く理想を追求できる一方で、費用や手間、時間がかかるという側面も持っています。
その特性を十分に理解した上で、ご自身の家族構成やライフプラン、そして家づくりにおける価値観と照らし合わせることが、後悔しないマイホーム選びの第一歩です。
この記事が、あなたの理想の家づくりを実現するための助けとなれば幸いです。
広島・東広島・福山で理想の注文住宅を建てたいなら、広島を中心に累積1万棟を超える注文住宅を手がけてきた山根木材にご相談ください。
私たちはお客様の住まいと暮らしに寄り添うライフパートナーとして、ご家族の思いに耳を傾け、ライフステージの変化も見据えた、お客様の暮らしに寄り添ったプランをご提案します。
お問い合わせ・資料請求は、下記お問い合わせフォームからお気軽にご連絡ください。