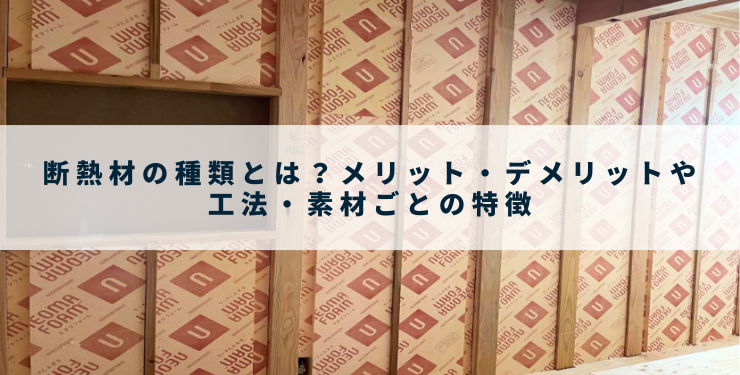「夏は涼しく、冬は暖かい家に住みたい」 これからマイホームを建てる多くの方が、そう願っているのではないでしょうか。
その快適な暮らしを実現する上で、最も重要なカギを握るのが住宅の断熱性能です。
そして、その性能を客観的に示す”ものさし”が「断熱等性能等級」です。
最近では「2025年から断熱等級4が義務化される」といった情報も聞かれるようになり、家づくりを検討し始めた方にとっては、決して無視できない重要なキーワードになっています。
しかし、専門用語も多く、等級ごとの違いや、結局どのレベルを目指せば良いのか、分かりにくいと感じている方も多いはずです。
この記事では、住宅の断熱性能について全く知識がない初心者の方でも理解できるよう、以下の点を徹底的に解説します。
- 断熱等性能等級の基本的な意味と、性能を決めるUA値との関係
- 等級1から最新の等級7までの具体的な性能の違いと基準
- 2025年に迫った省エネ基準義務化のポイント
- 等級ごとのメリット・デメリットと、かかる費用の目安
- あなたの家が目指すべき推奨等級の選び方
この記事を最後まで読めば、断熱等性能等級のすべてが分かり、自信を持ってハウスメーカーと打ち合わせを進められるようになります。
断熱等性能等級とは?住宅の断熱性を示す7段階の指標
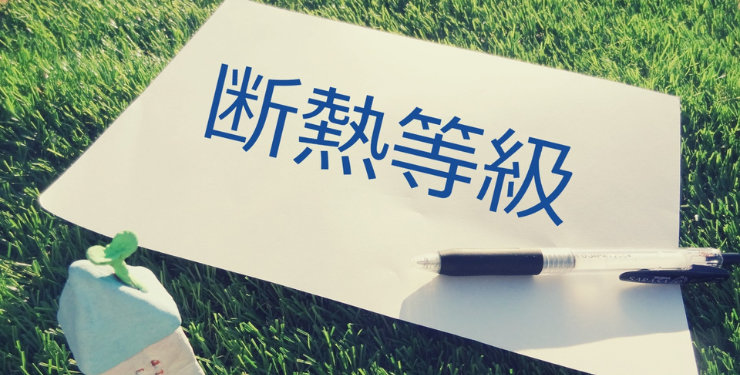
断熱等性能等級とは、その名の通り「住宅の断熱性能がどのくらいのレベルにあるか」を示す等級のことです。
「住宅の品質確保の促進等に関する法律(品確法)」に基づいて定められた公的な指標で、等級の数字が大きいほど、断熱性能が高いことを意味します。
2022年の改正で上位の等級6と7が新設され、現在は全部で7段階の等級に分かれています。
この等級は、省エネ性能はもちろん、住む人の快適性や健康にも直結するため、家づくりにおいて非常に重要な基準となります。
UA値(外皮平均熱貫流率)で性能が決まる
断熱等性能等級を理解する上で絶対に欠かせないのがUA値(外皮平均熱貫流率)という数値です。
これは「建物の中から、壁・床・天井・窓などを通して、どれくらいの熱が外に逃げやすいか」を客観的に示した指標で、数値が小さいほど熱が逃げにくく、断熱性能が高いことを意味します。
現在の断熱等性能等級は、このUA値が地域ごとに定められた基準値をクリアしているかどうかで判断されます。
例えば、同じ等級5であっても、寒い北海道と温暖な沖縄では求められるUA値の基準が異なります。
以前は断熱材の厚さなどで判断する「仕様基準」もありましたが、現在はより正確な性能を示すUA値を用いた「性能基準」が主流です。
ハウスメーカーや工務店と打ち合わせをする際には、必ず「この家のUA値はいくつですか?」と確認することが、家の断熱性能を正確に把握するための第一歩となります。
このUA値という物差しがあるからこそ、私たちは家の性能を客観的に比較・検討できるのです。
一次エネルギー消費量等級との違い
断熱等性能等級とセットでよく耳にするのが「一次エネルギー消費量等級」です。
この二つは密接に関係していますが、評価する対象が異なります。
断熱等性能等級が「家の断熱性」、つまり家の“魔法瓶”としての性能を評価するのに対し、一次エネルギー消費量等級は、その断熱性を土台として、さらに冷暖房・換気・照明・給湯設備などの燃費の良さまで含めて総合的に評価します。
等級は6段階あり、数字が大きいほど省エネです。
例えば、同じ断熱性能の家でも、高効率な給湯器(エコキュートなど)や省エエネ性能の高いエアコンを導入すれば、一次エネルギー消費量等級は高くなります。
長期優良住宅の認定などでは、この二つの等級がセットで基準とされることが多く、「断熱等性能等級5以上、かつ一次エネルギー消費量等級6」といった条件が求められます。
家づくりにおいては、まず断熱性能を高め、その上で省エネな設備を選ぶという順番で考えるのが基本です。
断熱等性能等級1から7までの基準とUA値の目安

それでは、具体的に各等級がどのくらいの性能レベルなのかを見ていきましょう。
ここでは、UA値の目安(6地域・東京などを想定)や、関連する省エネ基準との関係性を一覧表にまとめました。
| 等級 | UA値の目安(6地域) | 性能レベルの概要 |
| 等級7 | 0.26 | HEAT20 G3グレード相当。 暖房の一次エネルギー消費量をG2から更に約25%削減。最高水準。 |
| 等級6 | 0.46 | HEAT20 G2グレード相当。 暖房の一次エネルギー消費量をZEH水準から約30%削減。 |
| 等級5 | 0.60 | ZEH水準。 長期優良住宅の認定基準(2022年10月〜)。 |
| 等級4 | 0.87 | 2025年4月からの義務化基準。 1999年制定の「次世代省エネ基準」に相当。 最低限のレベル。 |
| 等級3 | 1.54 | 1992年制定の「新省エネ基準」に相当。 現在の基準では性能が低い。 |
| 等級2 | 1.67 | 1980年制定の「旧省エネ基準」に相当。 断熱材が入っている程度。 |
| 等級1 | – | 無断熱。 断熱に関する対策が特に講じられていない住宅。 |
等級4 2025年から義務化される省エネ基準
等級4は、1999年に定められた「次世代省エネルギー基準」に相当するレベルです。
長い間、日本の住宅における断熱性能の一つの目標とされてきましたが、世界基準で見ると決して高いレベルとは言えません。
そして、2025年4月からは、すべての新築住宅でこの等級4への適合が義務化されます。
つまり、今後の家づくりにおいて、等級4は「目指す」レベルではなく「クリアしなければならない最低限のライン」となります。
壁や天井だけでなく、熱の出入りが最も大きい窓などの開口部にも一定の断熱対策が求められます。
しかし、冬場には暖房をつけたリビングと、そうでない廊下やトイレとの間に大きな温度差が生まれやすく、快適性や健康面では物足りなさを感じる可能性があるレベルです。
等級5 ZEH水準・長期優良住宅の基準
等級5は、現在の家づくりにおける一つの重要なベンチマークと言える性能レベルです。
これは、国が普及を推進するZEH(ゼッチ、ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス)に求められる断熱性能に相当します。
ZEHとは、高い断熱性による省エネと、太陽光発電などによる創エネを組み合わせ、年間の一次エネルギー消費量をおおむねゼロ以下にする住宅のことです。
また、2022年10月の制度改正により、長期間にわたり良好な状態で使用できる「長期優良住宅」の認定を受けるためにも、断熱等性能等級5かつ一次エネルギー消費量等級6を満たすことが必須となりました。
これにより、等級5は単なる高性能の指標ではなく、税制優遇や補助金など、さまざまなメリットを享受するための「パスポート」としての役割も持つようになりました。
これから家を建てるなら、まずはこの等級5をクリアすることを目標に計画を進めるのが賢明な選択です。
等級6 HEAT20 G2グレードに相当
等級6は、より高いレベルの断熱性能を求める民間団体「HEAT20」が定める「G2」グレードに相当する、非常に高い断熱性能です。
HEAT20とは、健康維持や快適性向上を主な目的として、断熱性能に関する先進的な基準を提言している団体です。
等級6のレベルになると、冬でも家の中のほとんどの部屋で室温がおおむね13℃を下回らないとされています。
これは、暖房を止めた後も室温が下がりにくく、朝起きる時の寒さや、廊下に出た時のヒヤッとする感覚が大幅に軽減されるレベルです。
ZEH基準である等級5よりもさらに暖冷房にかかるエネルギー消費量を約30%削減できるとされており、高い省エネ性と、ホテルにいるかのような一年中安定した室温環境を求める方におすすめのハイレベルな基準です。
等級7 HEAT20 G3グレードの最高等級
等級7は、2022年10月に新設された、現行制度における最高等級の断熱性能です。
これは「HEAT20」の基準の中でも最上位の「G3」グレードに相当します。
等級7の住宅では、冬の寒い日でも、家の中のほとんどの部屋で室温がおおむね15℃を下回らないとされており、無暖房でも活動に支障がないほどの驚異的な性能を誇ります。
暖房にかかるエネルギー消費量を等級6からさらに約25%削減できるとされ、まさに究極の省エネ住宅と言えるでしょう。
このレベルを実現するためには、断熱材や窓サッシに最高品質のものを採用するだけでなく、設計や施工にも極めて高度な技術とノウハウが求められます。
建築コストは大幅に上がりますが、光熱費を最小限に抑え、最高レベルの快適性と健康的な暮らしを追求したいと考える方にとっての理想的な選択肢となります。
【2025年4月施行】断熱等性能等級の義務化とは?

これまで何度か触れてきたように、日本の住宅の省エネ基準は大きな転換点を迎えています。
ここでは、家づくりを考えているすべての方が知っておくべき「義務化」について、ポイントを解説します。
全ての新築住宅で等級4以上が必須に
2050年のカーボンニュートラル実現に向けた国の政策の一環として、2025年4月1日以降に建築確認申請を行うすべての新築住宅・建築物に対して、断熱等性能等級4以上への適合が法律で義務付けられます。
これまでは、省エネ基準への適合は一部の大規模な建物を除いて努力義務に留まっていましたが、これからは戸建て住宅を含むすべての新築建物が対象となります。
つまり、基準を満たさない家は建てられなくなるということです。
これにより、日本の住宅全体の省エネ性能の底上げが図られます。これから住宅会社と契約する方は、そのプランが2025年以降の基準をクリアしているか、必ず確認するようにしましょう。
2030年には等級5(ZEH水準)へ引き上げ予
国の政策は2025年で終わりではありません。
政府はさらにその先のロードマップとして、2030年を目途に、省エネ基準をZEH水準である等級5まで引き上げることを目標に掲げています。
これは、遅れていると言われる日本の住宅の断熱性能を世界基準に近づけるための重要なステップです。
2025年に等級4が義務化された後、わずか5年でさらに高いレベルが求められることになります。
この流れを考えると、これから家を建てるのであれば、最低ラインである等級4を目指すのではなく、将来のスタンダードとなる等級5以上を視野に入れておくことが、資産価値の維持という観点からも非常に重要であると言えるでしょう。
(参考:脱炭素社会に向けた住宅・建築物における省エネ対策のあり方・進め方の概要|国土交通省)
断熱等性能等級を上げるメリット・デメリットと費用目安
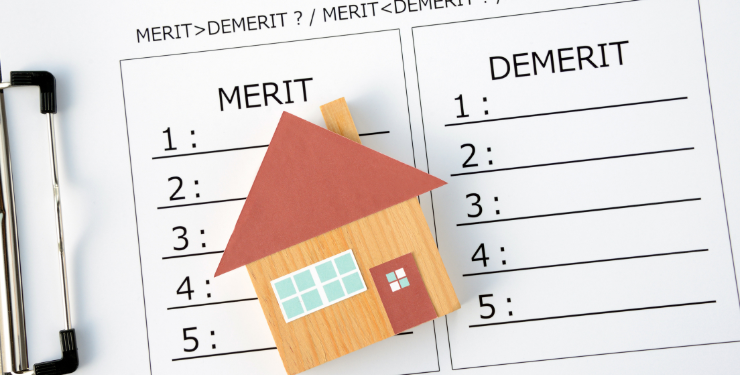
断熱等級を上げることで、私たちの暮らしには具体的にどのような良いことがあるのでしょうか。
もちろん、メリットだけでなく、知っておくべきデメリットも存在します。
両方を理解した上で、最適な選択をしましょう。
メリットは光熱費削減と快適・健康な暮らし
断熱等級が高い家の最大のメリットは、「少ないエネルギーで一年中快適に過ごせる」ことです。
高断熱の家は外の暑さや寒さの影響を受けにくく、一度エアコンで調整した室温が魔法瓶のように保たれます。
これにより、冷暖房の運転時間を大幅に短縮でき、光熱費を大きく節約できます。
特に、近年の電気代高騰を考えると、この経済的なメリットは非常に大きいと言えるでしょう。
さらに、家の中の温度差が少なくなることで、冬場の危険なヒートショックのリスクを大幅に軽減できます。
リビングは暖かいのに廊下や脱衣所が極端に寒い、といったことがなくなり、高齢者から小さなお子様まで家族全員が安心して暮らせます。
また、結露の発生も抑制されるため、アレルギーの原因となるカビやダニの繁殖を防ぎ、健康的な室内環境を維持することにも繋がります。
デメリットは建築コスト増と設計の制約
一方で、断熱等級を上げるためには、高性能な断熱材や気密部材、樹脂サッシやトリプルガラスといった高価な建材が必要になるため、建築コストが上昇します。前述の通り、等級4から等級5へ上げるだけでも、仕様によりますが数十万円から100万円程度の追加費用が見込まれます。
この初期投資をどう考えるかが一つの判断ポイントです。
また、性能を追求するあまり、設計に制約が生まれる可能性も考慮する必要があります。
例えば、大きな窓や開放的な吹き抜けは熱が逃げる原因になりやすいため、採用が難しくなったり、非常に高価なサッシが必要になったりする場合があります。
さらに、家全体の気密性が高まるため、適切な24時間換気システムの導入と運用が不可欠です。
換気を怠ると、シックハウス症候群の原因となる化学物質や二酸化炭素が室内に滞留し、健康を害する恐れがあるため注意が必要です。
断熱等性能等級の選び方

ここまで様々な等級について解説してきましたが、「結局、我が家はどの等級を目指せばいいの?」というのが一番知りたいことだと思います。
ここでは、具体的な選び方の指針をご紹介します。
コストと性能のバランスが良い「等級5」が最初の目安
これから新築を建てる多くの方にとって、まず目指すべき推奨基準は断熱等性能等級5です。
これはZEH(ゼッチ)基準に相当するレベルであり、2022年10月から長期優良住宅の認定を受けるための最低基準にもなりました。
等級4が2025年からの義務化ラインであるため、「最低限」のレベルであるのに対し、等級5はそれよりもワンランク上の性能を持ち、光熱費の削減効果や冬の暖かさを明確に実感できるレベルです。
等級6や7はさらに高性能ですが、その分、建築コストも大きく上昇します。
そのため、多くのハウスメーカーが標準仕様として採用し、補助金制度の対象にもなりやすい等級5は、コストと快適性のバランスが最も取れた現実的な選択肢と言えるでしょう。
国が2030年にはこの等級5を義務化基準に引き上げる方針を示していることからも、将来を見据えた家づくりとして、等級5を一つの目安に設定することをおすすめします。
【重要】お住まいの地域区分で必須のUA値を確認
断熱等性能等級を語る上で絶対に忘れてはならないのが「地域区分」です。
日本全国は、気候条件に応じて1から8の地域に分けられており、同じ等級でも地域によって求められるUA値の基準が異なります。
例えば、東京(6地域)で等級5を満たすにはUA値0.60以下が求められますが、より寒冷な長野(4地域)で等級5を目指すなら、UA値0.56以下という、より厳しい基準をクリアしなければなりません。
これは、寒い地域ほど高い断熱性能が必要になるためです。
家を建てる際は、まずご自身の建築地がどの地域区分に該当するのかを必ず確認してください。
この確認を怠ると、せっかく高性能な家を建てたつもりでも、その地域の基準では「等級5に満たない」といった事態も起こり得ます。
地域区分は国土交通省のウェブサイトで確認できますので、ハウスメーカーに任せきりにせず、ご自身でも把握しておくことが重要です。
(参考:住宅性能表示制度における省エネ性能に係る上位等級の創設|国土交通省)
断熱等性能等級に関するよくある質問

最後に、断熱等性能等級についてお客様からよくいただく質問とその回答をまとめました。
等級を上げると建築費用はどれくらい上がる?
断熱等級を上げるための追加費用は、仕様や施工会社によって大きく異なりますが、一般的な目安として、等級4から等級5へ上げる場合、30坪程度の住宅で50万円から100万円程度のコストアップが見込まれます。
主な内訳は、高性能なグラスウールや吹付断熱材への変更費用、そして熱が出入りしやすい窓をアルミサッシから樹脂サッシやトリプルガラスといった高性能なものへ変更する費用です。
さらに等級6や等級7を目指す場合は、より高性能な断熱材やサッシが必要になるため、追加で100万円以上の費用がかかることも珍しくありません。
ただし、これはあくまで初期投資です。
等級を上げることで光熱費が年間数万円単位で削減できるため、長期的に見れば投資分を回収できる可能性は十分にあります。
補助金制度をうまく活用することも、初期費用を抑えるための重要なポイントです。
等級の確認方法は?住宅性能評価書をチェック
新築住宅の断熱等性能等級を正確に確認するには「住宅性能評価書」を見るのが最も確実です。
これは、第三者機関が客観的に住宅の性能を評価した「家の通信簿」のようなもので、「温熱環境・エネルギー消費量に関すること」の項目に等級が明記されています。
もし住宅性能評価書を取得していない場合は、「設計図書(仕様書や矩計図など)」で断熱材の種類や厚さ、窓の仕様などを確認し、そこから性能を推測することになります。
中古住宅の場合はこれらの書類が揃っていないことも多く、正確な等級の確認は困難です。
どうしても知りたい場合は、インスペクション(住宅診断)の専門家に依頼し、図面や現地調査から性能を推定してもらう方法がありますが、費用がかかります。
これから家を建てる方は、後々の資産価値にも関わるため、ぜひ住宅性能評価書の取得を検討しましょう。
リフォームで等級を上げることはできる?
はい、既存の住宅でも断熱リフォームによって断熱等性能等級を上げることは可能です。
最も効果的なのは「窓」のリフォームです。
家の中で最も熱の出入りが激しいのは窓であり、既存の窓の内側にもう一つ窓を追加する「内窓」の設置や、サッシごと高性能なものに交換する方法があります。
壁や天井、床の断熱リフォームは、壁を剥がすなど大掛かりな工事になり費用も高額になりがちですが、これも断熱性能の向上に大きく寄与します。
例えば、壁の内側に断熱材を吹き込んだり、天井裏に断熱材を敷き詰めたりします。
国や自治体は、断熱リフォームに対して手厚い補助金制度を用意していることが多いです(例:先進的窓リノベ事業)。
これらの制度を活用すれば、費用を抑えながら自宅の性能を等級4相当や等級5相当に引き上げ、快適で省エネな暮らしを実現することができます。
マンションの断熱等級はどうなってる?
マンションにも戸建て住宅と同様に断熱等性能等級の基準は適用されます。
ただし、一般的にマンションはコンクリートで造られており、多くの住戸が隣接しているため、戸建てに比べて元々の断熱性や気密性が高い傾向にあります。
特に最上階の天井や角部屋の外壁、そして窓が断熱性能のキーポイントとなります。新築マンションの場合、住宅性能評価書があれば等級を確認できます。
中古マンションの場合は、図面などで断熱材の仕様を確認するのは難しく、正確な等級を知るのは困難です。マンションで断熱リフォームを行う場合、共用部である窓のサッシ本体の交換は管理規約で制限されていることが多いですが、ガラスのみの交換や内窓の設置は専有部のリフォームとして認められるケースがほとんどです。
これらのリフォームだけでも、住戸の断熱性能を大きく向上させることが可能です。
最適な暮らしに合わせて断熱等性能等級を決めよう
今回は、住宅の快適性と省エネ性を左右する「断熱等性能等級」について、その基本から2025年の義務化、そして目指すべき等級の選び方までを網羅的に解説しました。
最後に、この記事の重要なポイントを振り返ります。
- 断熱等性能等級は7段階あり、UA値という数値が小さいほど高性能。
- 2025年4月から、すべての新築住宅で等級4以上が義務化される。
- 将来の資産価値も考えると、推奨される目安はZEH水準である等級5以上。
- 必要な性能は地域区分によって異なるため、必ず確認が必要。
- 高い等級は初期コストがかかるが、光熱費削減と快適・健康という大きなメリットがある。
断熱性能は、後から簡単には変更できない、家の基本性能そのものです。
目先のコストだけで判断せず、将来にわたる暮らしの質やランニングコストまで含めて、ご家族にとって最適な等級を選択することが後悔しない家づくりの秘訣です。
この記事で得た知識を元に、ぜひ住宅会社の担当者にあなたの希望を伝え、納得のいく家づくりを実現してください。
お問い合わせ・資料請求は、下記お問い合わせフォームからお気軽にご連絡ください。