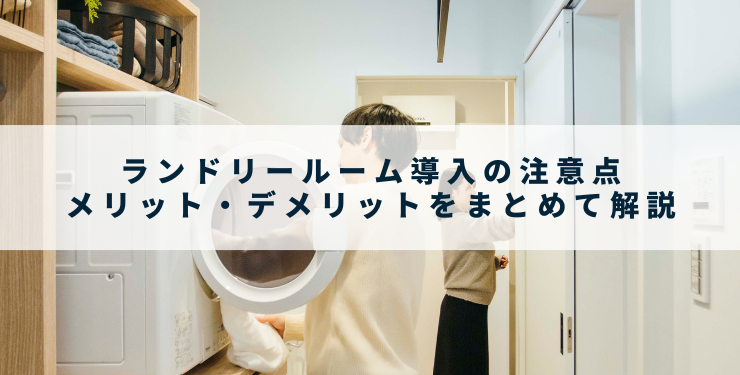注文住宅を建てる際、愛車との暮らしを豊かにする「インナーガレージ」は多くの方にとって憧れの空間です。
しかし、その寸法、特に高さの決定は、後から変更できないだけに非常に重要です。
「設計士に提案された高さで本当に十分だろうか?」 「将来、SUVやミニバンに乗り換えても大丈夫かな?」 「せっかく作るなら、後悔しない最適なサイズを知りたい!」
そんな悩めるあなたのために、この記事ではインナーガレージの高さと寸法で失敗しないための具体的な数値とポイントを徹底解説します。
この記事を読めば、あなたの愛車とライフスタイルにぴったりの、理想的なガレージハウスを実現するための知識がすべて手に入ります。
【結論】インナーガレージの推奨天井高は最低2.5mから

インナーガレージの計画で最も重要な天井高。
結論から言うと、将来のことも見据えた推奨の高さは2.5m以上です。
なぜその高さが必要なのか、3つの基準から具体的に見ていきましょう。
建築基準法が定める最低限の高さ2.1m
まず知っておきたいのが、法律で定められた基準です。
建築基準法施行令では、人が継続的に使用する「居室」の天井高は2.1m以上と定められています。
インナーガレージは一定の条件下では居室と見なされませんが、人が出入りし、洗車やメンテナンス作業を行う空間であるため、この2.1mが事実上の最低ラインとなります。
しかし、この高さはあくまで最低限の数値です。
例えば、人気のミニバンであるトヨタ・ヴォクシーの全高は約1.9mあり、乗り降りするだけでもかなりの圧迫感を感じるでしょう。
また、照明器具の厚みや将来の乗り換えを考慮すると、この寸法で設計してしまうと後悔する可能性が非常に高くなります。
家づくりにおいては、この2.1mという数値を「クリアすべき最低基準」ではなく、「避けるべき寸法」と捉えることが後悔しないための第一歩です。
一般的な乗用車に最適な推奨高さ2.5m
後悔しないための現実的な選択肢として、多くのハウスメーカーが標準仕様とすることが多い推奨の高さが2.5mです。
この天井高があれば、セダン(全高約1.5m)や一般的なSUV(全高約1.7m)はもちろん、ほとんどの国産ミニバンでも安心して駐車できます。
2.5mの高さを確保することで、ガレージ内でタイヤ交換などの軽いメンテナンス作業を行う際にも、常に腰をかがめる必要がなくなり、作業のストレスが大幅に軽減されます。
また、ダウンライトやシーリングライトといった照明器具を設置しても圧迫感がなく、空間全体を明るく開放的に感じさせることができます。
趣味の道具を壁に飾ったり、簡単なDIY作業をしたりするにも十分な高さであり、駐車スペース+αの価値を生み出すバランスの取れた寸法と言えるでしょう。
アルファードや大型SUVなら余裕のある高さ3.0m
もし、あなたがトヨタ・アルファード(全高約1.95m)のような大型ミニバンや、メルセデス・ベンツ Gクラスのような大型SUV(全高約1.97m)を所有している、あるいは「いつかは乗りたい」と考えているのであれば、天井高は3.0m以上を強く推奨します。
この高さを確保しておけば、ルーフボックス(高さ約0.4m)を載せた状態でも、高さを気にすることなくスムーズに入庫が可能です。
さらに、この開放的な天井空間は、単なる駐車スペースにはとどまりません。
使わないタイヤはもちろん、サーフボードやスノーボード、キャンプ用品などを天井収納としてスマートに格納できるようになり、居住スペースを圧迫せずに趣味の道具を整理できます。
まさに「見せる収納」も楽しめる、こだわりの趣味空間が実現するのです。
このようなビルトインガレージは、構造計算上で梁を太くするなどの工夫が必要になりますが、その価値は計り知れません。
高さだけじゃない!快適性を決める幅・奥行・間口の必須寸法

インナーガレージの快適性は、高さだけで決まるわけではありません。
「幅」「奥行き」「間口」という3つの寸法が、日々の使いやすさを大きく左右します。
ドアの開閉と作業性を考慮した「幅」の決め方
ガレージの「幅」は、毎日の乗り降りの快適さに直結します。
車のドアを気にせず全開にできるか、荷物を持ったままスムーズに通り抜けられるかは、このガレージ幅次第です。
国土交通省の指針では駐車ますの横幅を2.5mとしていますが、これはドアの開閉を考慮しない最小基準です。
壁に囲まれたインナーガレージでは、車の全幅に加えて、ドアを十分に開けるスペース(片側約0.8m)と人が通るスペースを考慮し、最低でも「車の全幅+1.2m」を確保しましょう。
例えば、全幅1.85mの車なら、ガレージの幅は3.05m以上が理想です。
特にビルトインガレージで2台を並列駐車する場合は、車と車の間に人が余裕をもって立てるスペース(約1.0m)を確保することで、隣の車にドアをぶつける心配なく、家族みんながストレスフリーで利用できます。
車の全長プラスαで考える「奥行き」の決め方
見落としがちなのがガレージの「奥行き」です。
車の全長ぴったりに設計してしまうと「シャッターが車に当たって閉まらない」「ガレージ奥の収納棚から物が取り出せない」といったトラブルの原因になります。
車の前後に人が立って作業できるスペースや、シャッターの厚みを考慮し、最低でも「車の全長+0.8m」の奥行きを確保することが重要です。
例えば、全長約5.0mのミニバンなら、奥行きは5.8m以上、できれば6.0mあると安心です。
さらに、ガレージの奥にタイヤや工具、アウトドア用品を置くための収納棚を設置する計画があるなら、その棚の奥行き(約0.5m〜1.0m)を追加で確保する必要があります。
長期的な視点で、ガレージ内で何をしたいかをイメージしながら寸法を決めていきましょう。
駐車のしやすさに直結する「間口」の決め方
ガレージの「間口(入り口部分の幅)」は、駐車のしやすさを決める最重要ポイントです。
特に、家の前の道路幅が狭い場合、この間口が狭いと何度もハンドルを切り返す必要があり、毎日の駐車が大きなストレスになってしまいます。
一般的に、駐車が苦手な方でも安心して停められる間口の広さは「車の全幅+1.2m」以上とされています。
例えば、全幅1.85mの車なら、間口は3.05m以上が目安です。
ビルトインガレージで2台分を計画する場合は、中央に構造上の柱が必要になるケースが多くあります。
その柱が死角にならないか、2台がスムーズに出入りできるかなど、設計段階で入念なシミュレーションを行うことが、使いやすい「車庫」を実現する鍵となります。
【駐車台数別】インナーガレージに必要な寸法と面積の目安4

所有する車の台数によって、必要となるガレージのサイズや広さは大きく変わります。
ここでは台数別の具体的な寸法と坪数の目安を見ていきましょう。
自動車1台用の寸法(幅3m×奥行6m)と坪数
自動車1台用のインナーガレージを計画する場合、最も標準的な寸法は「幅3.0m × 奥行き6.0m」です。
このサイズであれば、大型のセダンやSUVでも余裕をもって駐車できます。
面積にすると18㎡となり、坪数に換算すると約5.5坪となります。
このスペースがあれば、車の両側に多少の余裕が生まれるため、乗り降りもスムーズです。
さらに、ガレージの奥や壁面に収納棚を設置して、タイヤや洗車用品、趣味の道具を置くことも可能になります。
都市部の限られた敷地でも実現しやすい、最もベーシックな大きさと言えるでしょう。
自動車2台用の寸法(幅6m×奥行6m)と坪数
ご夫婦で車を所有している場合など、自動車2台用のビルトインガレージを並列で駐車する場合、推奨される寸法は「幅6.0m × 奥行き6.0m」です。
これは、1台あたりの幅を3.0mと考えた計算で、2台の間にドアを開閉するための十分なスペースが確保できます。面積は36㎡、坪数では約11坪となります。
この広さがあれば、乗り降りで隣の車に気を遣う必要がなくなります。
もし敷地の形状で幅が6.0m取れない場合は、5.5m程度まで詰めることも可能ですが、その分乗り降りが窮屈になることは覚悟しておきましょう。
快適なカーライフのためには、できる限り余裕を持ったビルトインガレージ 2台 幅を確保することが大切です。
自動車3台用の寸法と坪数
自動車を3台所有している、あるいは将来的にその可能性がある場合、ガレージの計画はより慎重に行う必要があります。
3台を並列で駐車する場合、理想的な寸法は「幅9.0m × 奥行き6.0m」です。
面積は54㎡、坪数では約16.5坪という広大なスペースが必要となり、住宅全体の間取りにも大きく影響します。
単純に1台分の3倍の幅と考えるのではなく、それぞれの車のドア開閉スペースを十分に確保することが重要です。
敷地面積やコストの観点から「ビルトインガレージ 3台」の実現が難しい場合は、2台を並列+1台を縦列にする、あるいは1台は屋外のカーポートにするなど、柔軟な発想で計画することも検討しましょう。
インナーガレージの寸法でよくある失敗例と後悔しないための対策

憧れのインナーガレージも、寸法計画を誤ると「こんなはずじゃなかった」という後悔につながりかねません。
ここでは、よくある失敗例とその対策をご紹介します。
失敗例1 将来の車買い替えで高さが足りなくなる
最も多い失敗例が、現在の愛車のサイズだけで寸法を決めてしまうケースです。
「今のコンパクトカーに合わせて設計したら、数年後に欲しくなったSUVの高さが入らなかった」「子供が生まれてミニバンに乗り換えたら、ルーフキャリアが天井にぶつかってしまった」といった声は後を絶ちません。
ライフステージの変化によって、車のサイズや種類は変わる可能性があります。
対策としては、設計段階で将来乗りたい車の候補をいくつか挙げ、その中で最も大きいサイズの車に合わせて寸法を決めることです。
特に高さは後からの変更が困難なため、少し余裕かなと感じるくらいの天井高を確保しておくことが、将来の選択肢を狭めないための賢明な判断と言えます。
失敗例2 ドアが全開できず乗り降りが不便になる
ガレージの幅が足りないと、毎日の乗り降りがストレスになります。
「壁や隣の車が気になってドアを少ししか開けられない」「チャイルドシートから子供を降ろすのが大変」「雨の日に荷物を濡らしながら、狭い隙間を通らなければならない」といった状況は、せっかくのインナーガレージのメリットを半減させてしまいます。
この失敗を防ぐためには、車の全幅だけでなく、ドアを全開にしたときの幅を考慮して設計することが不可欠です。
設計士との打ち合わせの際には、実際にメジャーなどを使って、乗り降りに必要なスペースを体感しながら確認することをおすすめします。
少しの幅の差が、日々の快適さを大きく左右します。
失敗例3 耐震性やコスト面での見落とし
インナーガレージは、1階部分に大きな開口部を設けるという構造上の特徴があります。
そのため、壁や柱の量が少なくなり、通常の住宅に比べて耐震性の確保に特別な配慮が必要です。
この点を理解せずに設計を進めると、地震に弱い家になってしまう危険性があります。
また、広い空間を支えるために太い梁や強固な基礎が必要となるため、建築費も高くなる傾向にあります。
これらのデメリットを知らずに計画を進め、後から耐震補強で追加費用が発生したり、予算オーバーになったりするケースも少なくありません。
対策としては、インナーガレージの施工実績が豊富で、高い耐震性能を持つ家づくりを得意とする会社を選ぶことが最も重要です。
例えば、私たち山根木材では、国の定める最高基準である「耐震等級3」を標準仕様としており、安心安全なガレージハウスをご提案しています。
高さを最大限に活かす!快適なガレージ空間の作り方
-38.png)
インナーガレージは単なる駐車スペースではありません。
余裕のある高さを活かせば、暮らしを豊かにする多目的な空間に進化します。
天井高を活かした収納計画と間取りのアイデア
インナーガレージの天井高を活かせば、驚くほどの収納スペースを生み出せます。
壁一面に棚を造作してメンテナンス工具やカー用品を「見せる収納」として飾れば、こだわりの趣味空間を演出できます。
また、高さを活かした天井収納を設ければ、スタッドレスタイヤやキャンプ用品、サーフボードといったかさばる物もスマートに格納可能です。
さらに、スキップフロアを採用し、ガレージの直上に書斎や収納スペースを設ける「ビルトインガレージの上に部屋」を作る間取りも人気です。
ガレージと居住空間を緩やかにつなげることで、家全体に一体感と遊び心が生まれます。
こうした工夫で、ガレージは秘密基地のような特別な場所に変わるのです。
必須の換気・照明・水道設備とEV充電コンセント
インナーガレージを快適で安全な空間にするためには、いくつかの設備が欠かせません。
まず、換気扇は、エンジンをかけた際の排気ガスを排出し、家族の健康を守るために必須です。
また、湿気がこもりやすいガレージ内の空気を循環させ、愛車や工具が錆びるのを防ぐ役割も果たします。
次に照明は、夜間の安全な駐車や作業性の向上のために重要です。
人感センサー付きの照明にすれば、防犯対策としても効果的です。
そして、あると格段に便利になるのが水道・排水設備。
ガレージ内で気軽に洗車ができるほか、汚れたアウトドア用品を洗ったり、DIYで汚れた手を洗ったりと、様々なシーンで活躍します。
最後に、将来を見据えて必ず設置したいのが電気自動車(EV)用の200V充電コンセントです。
後から設置するのは大変な工事になるため、新築時に備えておくことを強くおすすめします。
インナーガレージの高さと寸法に関するQ&A
ここでは、インナーガレージを計画する上でよくある専門的な疑問にお答えします。
容積率緩和の特例とは?高さや床面積との関係
家を建てる際には、敷地面積に対する延床面積の割合を示す「容積率」の上限が定められています。
インナーガレージ(ビルトインガレージ)を設ける場合、ガレージ部分の床面積を、建物全体の延床面積の5分の1を上限として、この容積率の計算から除外できるという「容積率緩和の特例」があります。
これにより、特に土地の価格が高い都市部など、規制が厳しいエリアでも、ガレージの面積分だけ広い居住スペースを確保することが可能になります。
この特例の適用条件はガレージの床面積であり、天井高に直接的な規定はありません。
賢く活用すれば、理想のガレージハウスを実現するための大きな助けとなる制度です。
固定資産税は高くなるのか
はい、インナーガレージを設置すると、屋外のカーポートに比べて固定資産税は高くなる傾向にあります。
固定資産税は、家屋の構造や使われている建材、設備などによって評価額が算出されます。
インナーガレージは、シャッターや照明、換気扇を備え、三方を壁で囲まれた堅固な構造物と見なされるため、「資産価値が高い」と評価され、課税対象の床面積に含まれます。
特に電動シャッターのような高価な設備は評価額を上げる一因となります。
ただし、愛車を雨風や盗難から守れる安心感や、天候を問わず快適に使える利便性を考えると、十分にその価値はあると考える方が多いようです。
建築後の高さ変更は可能か
結論から申し上げますと、一度建てたインナーガレージの高さ変更は、構造上ほぼ不可能です。
インナーガレージの柱や梁は、建物全体の構造と一体化して家を支えています。
そのため、天井を高くするということは、1階部分を解体して丸ごと作り直すのに等しい、非常に大掛かりで非現実的な工事となってしまいます。
だからこそ、家づくりの最初の段階で、「ビルトインガレージ 高さ変更」で後悔しないよう、10年後、20年後のライフプランや家族構成の変化、乗りたい車の夢まで想像しながら、十分に余裕を持った高さと寸法を決定することが何よりも重要なのです。
【施工実例】山根木材が叶える理想のインナーガレージ
最後に山根木材が手がけた注文住宅のなかから、インナーガレージを上手に取り入れた実例を紹介します。
二世帯住宅に設けられたこちらのインナーガレージは右が車用、左がバイク用に分かれています。
左右とも車両を置いても余裕のある広さで、壁面に沿って収納棚を設置しました。
メンテナンスやカスタム用の道具を一式収納してあり、いつでも趣味に没頭できる夢の空間です。
内装には濃淡のある壁紙を使用し、ただの「駐車スペース」ではなく「こだわりの趣味空間」という雰囲気を演出しています。
まとめ
インナーガレージの計画、特に高さと寸法は、一度決めたら簡単に変えることができません。
だからこそ、現在の愛車だけでなく、将来のライフスタイルの変化まで見据えた、余裕のある設計をすることが後悔しないための最大のポイントです。
- 天井高は最低でも2.5m、大型車を視野に入れるなら3.0mが理想。
- 幅・奥行・間口は、車のサイズ+αのゆとりを確保する。
- 耐震性や実績を考慮し、信頼できる住宅会社を選ぶ。
私たち山根木材は、広島の地で長年にわたり、お客様一人ひとりの夢を形にする家づくりをお手伝いしてきました。
広島・東広島・福山周辺でインナーガレージ付きの注文住宅を建てたいなら、ぜひ山根木材にご相談ください。
山根木材の家は、耐震等級1(建築基準法で定められた耐震基準と同等レベルの耐震性)の1.5倍という高い耐震性を有する「耐震等級3」を標準仕様に設定しており、インナーガレージがあっても地震に強い家づくりを叶えられます。
お問い合わせ・資料請求は、下記お問い合わせフォームからお気軽にご連絡ください。