土地を売却したり、新しく家を建てたりすることを考えたとき、「境界確定」という言葉を耳にしたことはありませんか?
「なんだか難しそう」「自分には関係あるのかな?」と感じる方もいらっしゃるかもしれません。
しかし、土地の境界確定は、大切な資産である土地を守り、将来のトラブルを未然に防ぐために非常に重要な手続きです。
特に不動産の売買においては、境界がはっきりしていないことが原因で、スムーズに取引が進まないケースも少なくありません。
この記事では、不動産の専門知識がない方にもご理解いただけるように、境界確定の基本的な意味から、よく似た言葉との違い、なぜ必要なのか、そして具体的な費用や手続きの流れまで分かりやすく解説していきます。
境界確定とは隣接する土地所有者全員の合意で境界を決めること

境界確定とは、かんたんに言うと「ご自身の土地と、お隣さんの土地との境目(境界)を、関係者全員で確認し、公式に合意すること」を指します。
法務局にある図面や現地にある境界標(境界を示す杭やプレート)など、あらゆる資料をもとに専門家が測量を行います。
その結果に基づいて、ご自身の土地に隣接するすべての土地所有者(個人の場合もあれば、道路を管理する市町村の場合もあります)に立ち会ってもらい、「ここが境界で間違いないですね」と全員の同意を得て、その証として書類を取り交わします。
この「関係者全員の合意」が境界確定の最も重要なポイントです。
一方的な主張ではなく、公式な手続きを経て境界をはっきりと定めることで、将来にわたってその土地の範囲が明確になり、安心して土地を活用したり、次の世代に引き継いだりすることができるのです。
境界確認・筆界確認・確定測量との違い
境界確定について調べていると、「境界確認」や「筆界確認」、「確定測量」といった似た言葉が出てきて混乱してしまうかもしれません。
それぞれ少しずつ意味合いが異なりますので、ここで違いを整理しておきましょう。
- 境界確認 これは、既存の資料や現地のブロック塀、境界標などから、おおよその境界を「確認する」作業を指します。隣人との合意までは行わないため、公的な証明力は境界確定に比べて弱いものとなります。
- 筆界(ひっかい)確認 筆界とは、法務局に登記されている公的な境界線のことです。この登記された筆界が現地でどこになるのかを確認する作業が筆界確認です。境界確定は、この筆界をベースに行われます。
- 確定測量 これは、境界確定を行うために実施される精密な測量のことを指します。土地家屋調査士が専門的な機器を使って測量し、境界確定の基礎となる正確な「確定測量図」を作成します。
つまり、「確定測量」という技術的な作業を行い、登記された「筆界」を明らかにし、隣人との「境界確認」を経て、最終的に全員の合意を得る手続き全体が「境界確定」と考えると分かりやすいでしょう。
官民境界と民民境界の2種類
確定すべき境界には、大きく分けて2つの種類があります。
- 民民境界(みんみんきょうかい) これは、個人の土地と個人の土地との間の境界です。一般的に「お隣さんとの境界」というと、この民民境界を指します。
- 官民境界(かんみんきょうかい) これは、個人の土地と、国や都道府県、市町村が所有する公的な土地との間の境界です。例えば、ご自身の土地が道路や水路に面している場合、その道路や水路との境界が官民境界にあたります。
土地を売却したり建物を建てたりする際には、多くの場合、この民民境界と官民境界の両方を確定させる必要があります。
境界確定をしないと売却や建築ができないリスク

「うちの土地は昔からこうだから大丈夫」と思っていても、境界確定をしていないと、思わぬところでリスクが生じることがあります。
なぜ境界確定の必要性が高いのか、具体的なリスクを見ていきましょう。
| リスク | 内容 |
| 土地の売却がスムーズに進まない | 買主の立場からすると、境界がはっきりしない土地を購入するのは非常に不安です。 購入後に隣人とトラブルになったり、思っていたより土地が狭かったりする可能性があるからです。 そのため、不動産売買では、売主の責任で境界を明示することが契約条件となるのが一般的です。 境界確定ができていないと、買主が見つかりにくかったり、契約が白紙になったりする恐れがあります。 |
| 新築や増改築の建築確認が下りない | 建物を建てる際は、法律(建築基準法)に基づいて、敷地面積に対する建物の大きさや、境界線からの距離などが厳しく定められています。 境界が曖昧なままでは、これらの基準を満たしているか判断できないため、役所が建築確認申請を受理してくれないことがあります。 つまり、家を建てたり、増改築したりすることができなくなってしまうのです。 |
| 土地の売却がスムーズに進まない | 買主の立場からすると、境界がはっきりしない土地を購入するのは非常に不安です。 購入後に隣人とトラブルになったり、思っていたより土地が狭かったりする可能性があるからです。 そのため、不動産売買では、売主の責任で境界を明示することが契約条件となるのが一般的です。 境界確定ができていないと、買主が見つかりにくかったり、契約が白紙になったりする恐れがあります。 |
| 土地の担保価値が低くなる | 土地を担保に金融機関から融資を受ける際、境界が確定していないと土地の正確な価値を評価できません。 そのため、融資が受けられなかったり、融資額が低くなったりする可能性があります。 |
このように、境界確定は、ご自身の資産価値を守り、円滑な土地活用を実現するために不可欠な手続きなのです。
境界確定の費用相場は35万円~80万円

境界確定を専門家に依頼する場合、どれくらいの費用がかかるのかは最も気になるところだと思います。
境界確定にかかる費用は、土地の状況によって大きく変動しますが、一般的な住宅地の場合、おおよその相場は35万円~80万円程度とされています。
ただし、これはあくまで目安です。費用が変動する主な要因には、以下のようなものがあります。
- 土地の面積や形状(広い、複雑な形だと高くなる)
- 隣接する土地の数(隣人が多いほど調整に手間がかかる)
- 官民境界の確定が必要かどうか(役所との協議が必要なため高くなる)
- 法務局や役所に保管されている資料の有無
- 隣人との関係性(協力が得られやすいか)
正確な費用を知るためには、必ず事前に土地家屋調査士に見積もりを依頼しましょう。
複数の事務所から見積もりを取ることで、費用の妥当性を判断しやすくなります。
測量費や筆界確認書作成費などの費用内訳
見積もりを見ると、さまざまな項目が並んでいます。主な費用の内訳は以下の通りです。
| 項目 | 内容 |
| 資料調査費 | 法務局や役所で、登記簿、公図、地積測量図、道路の図面など、境界を特定するために必要な資料を収集・分析するための費用です。 |
| 測量費 | 現地で測量を行うための費用です。事前調査のための測量や、境界標を設置するための測量などが含まれます。 |
| 書類作成費 | 隣人との合意内容をまとめた「筆界確認書(境界確認書)」や、測量結果をまとめた「境界確定図」など、各種書類を作成するための費用です。 |
| 境界標設置費 | 境界点にコンクリート杭や金属プレートといった、永続的な境界標を設置するための実費や作業費です。 |
| 日当・交通費 | 専門家が現地調査や役所での手続き、隣人への説明などに赴くための費用です |
費用負担は原則として土地の売主
不動産売買において境界確定を行う場合、その費用は原則として売主が負担するのが一般的です。
これは、売主には、売却する土地の範囲を明確にして買主に引き渡す責任がある、という考え方に基づいています。
買主が安心して土地を購入できるよう、売主側で境界を確定し、その証明となる書類を準備するのが通例です。
ただし、これは法律で決まっているわけではないため、売買契約の際の特約で、買主が一部を負担したり、売主と買主で費用を按分したりするケースもあります。
手続き期間の目安は3ヶ月から半年
境界確定の手続きにかかる期間は、費用の変動要因と同じく土地の状況によって異なりますが、スムーズに進んだ場合でも3ヶ月から半年程度を見ておくとよいでしょう。
特に、隣接するのが道路や水路などで官民境界の確定が必要な場合は、役所の担当者との協議や承認に時間がかかるため、期間が長くなる傾向があります。
また、隣人の協力がなかなか得られない、相続で所有者が複数いるなど、権利関係が複雑な場合は、1年以上かかることもあります。
土地の売却などを検討している場合は、時間に余裕をもって早めに手続きを開始することが大切です。
境界確定の依頼から完了までの全6ステップ
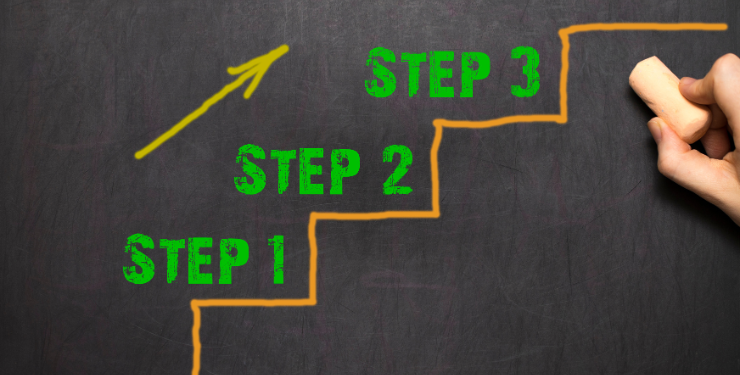
では、実際に境界確定はどのような流れで進んでいくのでしょうか。
ここでは、専門家である土地家屋調査士に依頼した場合の一般的な手順を6つのステップでご紹介します。
Step1. 専門家である土地家屋調査士への相談・依頼
境界確定を考え始めたら、最初のステップは専門家である土地家屋調査士を探し、相談することから始まります。
土地家屋調査士は土地の測量と登記のプロフェッショナルです。
相談の際には、所有している土地の登記済権利証や登記識別情報、固定資産税の納税通知書、古い図面など、手元にある資料を持参すると話がスムーズに進みます。
土地の場所や大きさ、どのような経緯で境界確定が必要になったのか(例えば、売却を予定している、隣家との間に塀を建てたいなど)を具体的に伝えましょう。
土地家屋調査士は、あなたの話や資料をもとに、どのような調査が必要か、おおよその費用はどれくらいか、どのくらいの期間がかかりそうか、といった見通しを説明してくれます。
内容に納得ができたら、正式に業務委任契約を結び、手続きがスタートします。
Step2. 法務局や役所での入念な資料調査
契約後、土地家屋調査士はまず「机上での調査」に着手します。
これは、境界確定の根拠となる公的な資料を徹底的に集める、非常に重要な工程です。
調査は主に、その土地を管轄する法務局や市町村役場で行われます。法務局では、土地の所有者や面積が記録された登記記録、土地のおおまかな形状と隣接関係がわかる公図(こうず)、過去に測量が行われていればその地積測量図などを収集します。
役所では、土地が道路や水路に接している場合に、その境界の根拠となる道路査定図などの資料を調査します。
これらの資料をパズルのピースのように組み合わせ、分析することで、土地が作られた歴史的背景や、過去の境界の状況を読み解き、現地調査に向けた仮説を立てていきます。
Step3. 現地での事前調査と仮の境界点を出すための測量
資料調査で得た情報をもとに、いよいよ土地家屋調査士が現地に赴き、現地の状況と資料を照らし合わせる調査と測量を行います。
まずは、過去に設置された境界標が残っていないか、ブロック塀やフェンスなどの構造物はどこにあるのかを目で見て確認します。
そして、トータルステーションといった精密な測量機器を使い、現地の地形や構造物の位置をミリ単位で正確に測量します(現況測量)。
この測量結果と、事前に調査した資料のデータをコンピューター上で重ね合わせることで、図面上の境界線が、現実の土地のどこにあたるのかを専門的な見地から割り出します。
この段階で算出された境界点が、次のステップである「立会い」のたたき台となります。
Step4. 全ての隣接土地所有者との現地での「立会い」
ここが境界確定手続きにおける最も重要な核心部分です。
算出した仮の境界点をもとに、依頼者であるあなたと、隣接する土地の所有者全員に現地に集まってもらい、境界を確認する「立会い」を実施します。
土地が公道に面していれば、役所の担当者も参加します。土地家屋調査士は、中立的な専門家の立場で、収集した資料や測量結果を全員に分かりやすく説明し、「調査の結果、境界点はここになります」と現地でポイントを示します。
参加者はその説明を受け、自分の認識と相違がないかを確認します。
もし疑問点や意見があれば、その場で質問し、協議を行います。
全員が「この境界で間違いありません」と納得し、合意することがこのステップのゴールです。
Step5. 境界標の設置と「筆界確認書」の取り交わし
立会いによって関係者全員の合意が得られたら、その合意内容を永続的な形で残す作業に入ります。
まず、合意した境界点に、将来にわたって境界の位置が誰の目にも明らかになるよう、コンクリート杭や金属プレートといった耐久性の高い境界標を設置します。
これにより、境界が物理的に明確になります。
次に、合意内容を証明する正式な書類として「筆界確認書(ひっかいかくにんしょ)」または「境界確認書」を作成します。
この書類には、境界を確定した測量図が添付され、立会いに関わった所有者全員が署名と捺印をします。
作成された筆界確認書は、各自が1通ずつ大切に保管します。
この書類があることで、将来世代が変わっても「境界について合意した」という事実が証明されます。
Step6. 最終的な「境界確定図」の作成と法務局への登記申請
すべての手続きが完了したら、土地家屋調査士は今回の成果物として最終的な「境界確定図」を作成し、依頼者に納品します。
この図面は、全ての隣接所有者と合意した境界情報が記載された、非常に信頼性の高いものです。
また、今回の正確な測量の結果、法務局の登記記録に記載されている土地の面積(地積)と差異があることが判明した場合、土地家屋調査士は登記記録を正しい面積に修正する「地積更正登記」を法務局に申請することができます。
この登記を行うことで、登記記録も現況と一致した正確なものとなり、不動産としての価値がより明確になります。ここまで完了すれば、境界確定に関するすべての手続きが終了となります。
境界確定の相談・依頼先は土地家屋調査士

境界確定の手続きは非常に専門性が高く、個人で行うのは困難です。相談や依頼をする際の窓口は、国家資格者である「土地家屋調査士」になります。
土地家屋調査士は、不動産の表示に関する登記や土地の測量を専門とする唯一の資格者です。
豊富な知識と経験に基づき、資料調査から測量、隣人との調整、書類作成まで、境界確定に関する一連の業務を代理で行ってくれます。
お近くの土地家屋調査士を探す場合は、各都道府県にある土地家屋調査士会のウェブサイトで検索したり、不動産会社や司法書士から紹介してもらったりする方法があります。
(参考:日本土地家屋調査士会連合会)
土地の境界確定に関するよくある質問
最後に、境界確定に関して多くの方が疑問に思う点について、Q&A形式でお答えします。
隣人が立会いに協力してくれない場合の対処法
残念ながら、隣人との関係がうまくいっていなかったり、境界に対する考え方が異なったりして、立会いに協力してもらえないケースもあります。
まずは土地家屋調査士から、境界確定の必要性や客観的な測量結果を丁寧に説明してもらい、対話を試みることが第一です。
それでも合意が難しい場合は、以下のような公的な制度を利用する方法があります。
- 筆界特定制度 法務局の専門家(筆界調査委員)が、資料や測量結果をもとに職権で筆界の位置を特定する制度です。裁判に比べて費用が安く、手続きも早く進みますが、所有権の範囲までを確定するものではありません。
(参考:法務省) - ADR(裁判外紛争解決手続) 弁護士や土地家屋調査士といった専門家が中立な立場で間に入り、話し合いによる解決を目指す手続きです。
これらの方法でも解決しない場合は、最終的に「境界確定訴訟」という裁判で争うことになります。
古い地積測量図がある場合も境界確定は必要か
法務局に古い「地積測量図」が保管されている場合があります。
しかし、特に昭和の時代に作成された測量図は、現在の測量技術に比べて精度が低く、現況とズレが生じていることが少なくありません。
そのため、たとえ古い地積測量図があったとしても、不動産売買や建築確認のためには、現在の高精度な技術で測量し直した「境界確定図」を求められるのが一般的です。
古い地積測量図は、あくまで境界を調査するための一資料として活用されます。
相続した土地の売却に境界確定は必須か
相続した土地を売却する場合、法律で境界確定が義務付けられているわけではありません。
しかし、現実的には、境界確定をしなければ買主が見つからない、あるいは大幅に価格を下げないと売れないというケースがほとんどです。
買主は、境界が曖昧な土地のリスクを負いたくないからです。 相続した土地を適正な価格で、かつスムーズに売却するためには、境界確定は実質的に必須の手続きと言えるでしょう。
土地を売却する前に、境界確定を忘れずに実施しましょう
この記事では、土地の境界確定について、その基本的な意味から必要性、費用、流れまでを解説しました。
境界確定は、時間も費用もかかるため、少し大変に感じるかもしれません。
しかし、それはご自身の、そしてご家族の大切な資産を守り、将来にわたって安心してその土地と関わっていくための、いわば「安心への投資」です。
もし土地の境界について少しでも不安や疑問があれば、まずは専門家である土地家屋調査士に相談することから始めてみてください。
きっと、あなたの状況に合った最適なアドバイスをもらえるはずです。
山根木材では、たった60秒で無料で不動産を査定できるサービスをご提供しております。
広島エリアを拠点に、累計1万棟を超える注文住宅の実績があり、安心と安全をお約束します。
不動産や土地の売却をご検討の方は、ぜひ下記ページにて無料査定を行ってみてください。
















