「そろそろマイホームが欲しいな」と住宅情報サイトを眺めていると、魅力的な物件がたくさん見つかりますよね。
しかし、表示されている物件価格だけでは家は買えないという事実に、不安を感じていませんか?
物件価格とは別に必要になるのが「諸費用」です。これは、税金や手数料など、住宅購入に付随して発生するさまざまな費用のことです。
金額は決して安くなく、場合によっては数百万円にものぼります。
「一体、何にいくらかかるんだろう?」
「自己資金はどれくらい準備すればいいの?」
「できれば諸費用も住宅ローンでまとめて支払いたい…」
この記事では、住宅購入の諸費用について、相場から具体的な内訳、そして多くの方が気になる住宅ローンとの関係まで、専門家が分かりやすく徹底解説します。
住宅購入の諸費用相場は物件価格の3~10%

住宅購入時にかかる諸費用の総額は、購入する物件の種類によって大きく変わります。
まずは、大まかな目安を把握しておきましょう。一般的に、新築物件で物件価格の3~7%、中古物件で6~10%程度が相場といわれています。
なぜ中古物件の方が割合が高いかというと、多くの場合で「仲介手数料」がかかるためです。
新築物件(建売・注文住宅)の諸費用目安
新築物件の諸費用は、物件価格の3~7%が目安です。
例えば、3,000万円の新築物件を購入する場合、諸費用は約90万円~210万円となります。
主な内訳は、登記費用や住宅ローン関連費用、各種税金などです。
不動産会社が売主となっている新築建売住宅などでは、仲介手数料がかからないケースが多く、その分諸費用を抑えられます。
中古物件の諸費用目安
中古物件の諸費用は、物件価格の6~10%が目安となり、新築物件よりも高くなる傾向があります。
同じく3,000万円の中古物件を購入する場合、諸費用は約180万円~300万円にのぼる可能性があります。
これは、新築ではかからないことが多い仲介手数料(最大で物件価格の3%+6万円+消費税)が発生するためです。
住宅購入の諸費用内訳一覧チェックリスト

それでは、諸費用の具体的な内訳を見ていきましょう。住宅購入にかかる費用は多岐にわたるため、何にいくらくらいかかるのかを事前に把握しておくことが大切です。
ここでは、主な費用を4つのカテゴリーに分けて解説します。
税金(印紙税・登録免許税・不動産取得税)
住宅購入では、さまざまな税金を納める必要があります。
印紙税:不動産売買契約書や住宅ローンの契約書(金銭消費貸借契約書)に貼る印紙代です。
- 契約金額によって税額が決まっており、数万円程度かかります。(参考 国税庁 No.7140 印紙税額の一覧表(その1)第1号文書から第4号文書まで https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/inshi/7140.htm)
- 登録免許税:購入した土地や建物を自分の所有物として法的に登録(所有権移転登記)したり、住宅ローンを組む際に金融機関の権利(抵当権設定登記)を登録したりする際にかかる税金です。
税額は固定資産税評価額に基づいて計算され、司法書士への報酬と合わせて支払うのが一般的です。 - 不動産取得税:土地や家屋などの不動産を取得した際に、一度だけ課税される都道府県税です。
入居後しばらくしてから納税通知書が届きます。要件を満たせば大幅な軽減措置を受けられるため、必ず手続きを確認しましょう。
住宅ローン関連費用(事務手数料・保証料)
住宅ローンを利用する際には、金融機関に支払う費用が発生します。
ローン事務手数料:住宅ローンの手続きを行う金融機関に支払う手数料です。
数万円の「定額型」と、借入額の2.2%(税込)など「定率型」の2タイプがあり、金融機関や商品によって異なります。
- ローン保証料:万が一、住宅ローンの返済が困難になった場合に、保証会社に返済を肩代わりしてもらうための費用です。
- 数十万円から百万円以上になることもありますが、一括前払いか、金利に上乗せして分割で支払うかを選べる場合があります。
保証料が不要な住宅ローン(フラット35など)もあります。
不動産会社や専門家への支払い(仲介手数料・司法書士報酬)
不動産取引をサポートしてくれた会社や専門家への報酬も必要です。
- 仲介手数料:中古物件や一部の新築物件を、不動産会社の仲介で購入した場合に支払う成功報酬です。法律で上限が定められており、「売買価格の3% + 6万円 + 消費税」が一般的な上限額となります。
- 司法書士報酬:所有権移転登記や抵当権設定登記など、専門知識が必要な法的手続きを代行してくれる司法書士に支払う報酬です。報酬額は依頼する司法書士によって異なり、10万円前後が目安です。
保険料(火災保険料・地震保険料)
万が一の災害に備えるための保険料も、諸費用に含まれます。
- 火災保険料・地震保険料:多くの金融機関では、住宅ローンを組む際の条件として火災保険への加入を義務付けています。
火災だけでなく、水災や風災など、補償の範囲をどこまで広げるかによって保険料は変わります。
地震保険は火災保険とセットで加入します。保険期間は1年更新や、5年一括などがあり、長期契約の方が割安になる傾向があります。
諸費用は住宅ローンに組み込める?メリットとデメリット
「数百万円もの諸費用を、現金で用意するのは難しい…」そう考える方は少なくありません。
実は、多くの金融機関では諸費用も住宅ローンに含めて借りることが可能です。
これを「諸費用ローン」や「オーバーローン」と呼ぶこともあります。
ただし、安易に利用を決めるのではなく、メリットとデメリットをしっかり理解しておくことが重要です。
諸費用をローンに組むメリットと注意点
最大のメリットは、手元に現金を残せることです。住宅購入後も、固定資産税の支払いや急な出費、教育費など、何かとお金は必要になります。
諸費用をローンに組み込むことで、自己資金に余裕を持たせ、ライフプランの変化に備えることができます。
一方、注意点は、借入額が増える分、毎月の返済額や総返済額が増加することです。
金利がわずかでも変われば、35年間の総返済額は大きく変わります。
また、借入額が増えることで、将来的に住宅の売却を考えた際に、売却価格よりもローン残高が上回る「担保割れ」のリスクも高まります。
ローンに組み込める費用と現金で必要な費用
金融機関によって対応は異なりますが、一般的に以下の費用が住宅ローンに組み込めるとされています。
- ローンに組み込めることが多い費用
- ローン事務手数料
- ローン保証料
- 印紙税
- 登録免許税・司法書士報酬
- 仲介手数料
- 火災保険料・地震保険料
- 原則として現金での準備が必要な費用
- 手付金 不動産売買契約時に、物件価格の一部(5~10%が目安)を売主に支払うお金です。
これは契約が成立した証拠金となり、原則として現金で用意する必要があります。
- 手付金 不動産売買契約時に、物件価格の一部(5~10%が目安)を売主に支払うお金です。
このほか、引っ越し費用や家具・家電の購入費用などは、原則として住宅ローンの対象外ですが、一部の金融機関ではこれらの費用もカバーするローン商品を用意している場合があります。
【物件価格3000万円】諸費用シミュレーション

ここでは、3,000万円の物件を購入した場合の諸費用がいくらになるか、具体的にシミュレーションしてみましょう。
あくまで一般的な目安であり、条件によって金額は変動します。
新築戸建て(建売)の諸費用計算例
| 費用項目 | 金額の目安 |
| 印紙税 | 1万円 |
| 登録免許税 | 約15万円 |
| 司法書士報酬 | 約10万円 |
| ローン事務手数料(定率型) | 約66万円(借入額3000万円×2.2%) |
| ローン保証料 | 約62万円(35年返済の場合) |
| 火災保険料・地震保険料(5年) | 約15万円 |
| 合計 | 約169万円 |
中古マンションの諸費用計算例
| 費用項目 | 金額の目安 |
| 仲介手数料 | 約105万円(3000万円×3%+6万円+消費税) |
| 印紙税 | 1万円 |
| 登録免許税 | 約20万円 |
| 司法書士報酬 | 約10万円 |
| ローン事務手数料(定率型) | 約66万円(借入額3000万円×2.2%) |
| ローン保証料 | 約62万円(35年返済の場合) |
| 火災保険料・地震保険料(5年) | 約10万円 |
| 合計 | 約274万円 |
住宅購入の諸費用を安く抑える5つの方法

少しでも負担を減らしたい諸費用。ここでは、賢く節約するための5つの方法をご紹介します。
- 仲介手数料が割引・無料の不動産会社を選ぶ 中古物件を探す際は、仲介手数料の割引キャンペーンなどを実施している不動産会社を探してみるのも一つの手です。
- 火災保険のプランを見直す 不動産会社や金融機関に勧められたプランにそのまま入るのではなく、複数の保険会社から見積もりを取り、自分に必要な補償内容を吟味することで、保険料を抑えられる可能性があります。
- 司法書士を自分で探す 不動産会社から紹介された司法書士に依頼するのが一般的ですが、自分で探して相見積もりを取ることで、報酬が安い司法書士を見つけられる場合があります。
ただし、ローン利用時は金融機関の指定が必要な場合もあるため、事前に確認が必要です。 - ローン保証料が不要な住宅ローンを選ぶ 「フラット35」のように、ローン保証料がかからない住宅ローン商品もあります。
その分、事務手数料が割高な場合もあるため、総支払額を比較して検討することが大切です。
(参考:住宅金融支援機構 【フラット35】 ) - 各種税金の軽減措置を最大限活用する 登録免許税や不動産取得税には、一定の要件を満たす住宅に対して税負担を軽くする軽減措置があります。
適用されるか否かで数十万円の差が出ることもありますので、必ず要件を確認し、忘れずに手続きを行いましょう。
諸費用に関するよくある質問
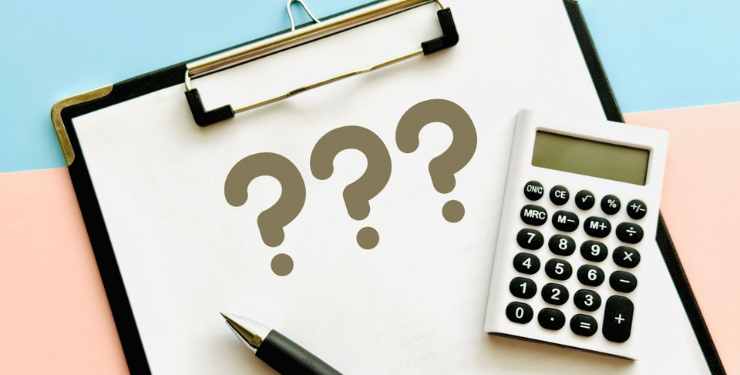
最後に、住宅購入の諸費用に関して多くの方が抱く疑問にお答えします。
諸費用はいつ支払う?タイミングの解説
諸費用は、一度にまとめて支払うわけではありません。住宅購入のプロセスに合わせて、さまざまなタイミングで支払いが発生します。
- 売買契約時 手付金、印紙税(契約書貼付分)
- 住宅ローン契約時 印紙税(ローン契約書貼付分)
- 引き渡し時(決済時) 仲介手数料の残金、登録免許税、司法書士報酬、ローン事務手数料、ローン保証料、火災保険料、固定資産税清算金など
特に、引き渡し時には多くの費用をまとめて支払うことになるため、事前にしっかり準備しておく必要があります。
自己資金(現金)は最低いくら必要?
諸費用をローンに組み込む場合でも、手付金は現金で用意するのが原則です。
物件価格の5~10%が目安となるため、3,000万円の物件なら150万円~300万円となります。
これに加えて、ローンに組み込めない費用や、引っ越し代、家具・家電の購入費用なども考慮すると、最低でも物件価格の10%程度の自己資金があると、安心して計画を進められるでしょう。
引っ越しや家具・家電の費用はローン対象?
前述の通り、引っ越し費用や家具・家電の購入費用は、原則として住宅ローンの対象外です。
しかし、金融機関によっては、これらの費用も含めて借り入れができる「諸費用ローン」や「フリーローン」を住宅ローンとセットで提供している場合があります。
ただし、住宅ローン本体よりも金利が高く設定されていることが多いため、利用は慎重に検討しましょう。
住宅の諸費用を把握した上で、自分らしい住宅を手に入れよう
今回は、住宅購入の際に必要となる「諸費用」について、相場から内訳、ローンとの関係まで詳しく解説しました。
- 諸費用の相場は**新築で物件価格の3~7%、中古で6~10%**が目安。
- 主な内訳は税金、ローン費用、手数料、保険料など多岐にわたる。
- 多くの金融機関で諸費用を住宅ローンに組み込むことが可能だが、総返済額が増える点に注意が必要。
- 手付金など、現金で用意する必要がある費用も存在する。
マイホームの購入は、人生で最も大きな買い物の一つです。物件価格だけでなく、諸費用がいくらかかるのかを事前にしっかりと把握し、無理のない資金計画を立てることが成功への第一歩です。
あなたの理想のマイホーム探しの助けとなれば幸いです。
山根木材では、たった60秒で無料で不動産を査定できるサービスをご提供しております。
広島エリアを拠点に、累計1万棟を超える注文住宅の実績があり、安心と安全をお約束します。
不動産や土地の売却をご検討の方は、ぜひ下記ページにて無料査定を行ってみてください。














